近畿– tag –
-

和気清麻呂 土木と都市計画のテクノクラート
教科書に登場する和気清麻呂は、忠誠心だけのおもしろみのない人物だった。 平城京で女帝・称徳天皇の寵愛をうけた僧の道鏡が、豊前国(大分県)の宇佐八幡宮で「道鏡を天皇にせよ」という神のお告げがあったと言って皇位につこうとした。それを確認す... -

空海が星を降らせた獅子窟寺
平安時代の弘仁年間(810~824)、大阪府交野市の山中で弘法大師が秘法を唱えると、七曜の星(北斗七星)が、現在の星田妙見宮など3カ所に落ちたという。実際、弘仁7(816)年には隕石が落下した記録があり、日本の隕石落下の記録で2番目に古い... -

神武に徹底抗戦した英雄ゆかりの地
九州から攻めてきたイワレヒコ(神武天皇)は大和をめざして大坂に上陸するが、生駒山地を根城とする長髄彦(ナガスネヒコ)に撃退され、兄のヒコイツセ(彦五瀬命)が重傷を負い、その後死亡する。 神武の軍は熊野へ迂回して今度は南から大和にむかう... -

安政の津波災害を今につたえる地蔵盆の行事 大阪・大正橋
岩崎橋から大正橋 「大正区」は橋の名 大阪市大正区と浪速区の境をながれる木津川の河口は1576(天正 4)年と78年、籠城する石山本願寺へ兵糧をはこぼうとした毛利水軍と包囲する織田軍が 2 度にわたって合戦をくりひろげた。 江戸時代に入ると、... -

怨霊が支配する古代 怨霊をよぶ現代
長岡京を廃絶させた親王の怨霊 上御霊神社 京都市上京区の上御霊神社(御霊神社)は、まちなかなのに社叢はうっそうとして薄暗い。十三柱の祭神の中心は桓武天皇の弟で、冤罪で非業の死をとげた早良(さわら)親王(崇道天皇)だ。 桓武は奈良から長岡... -

「方丈記」 3メートル四方のすみかの意味
ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ消え、かつ結びて、久しくとどまりたる例なし 「方丈記」の冒頭は暗記していたけど、これにつづく一節が 世の中にある、人と栖(すみか)と、またかくのごとし だと... -

若冲の五百羅漢は縄文系?
岡本太郎が縄文を「発見」したのと同様、辻惟雄は、伊藤若冲や長沢蘆雪を「発見」した。辻が1968年に「美術手帖」で紹介した当時、若冲らは「傍流」「異端」とされ、国内では評価されず、多くの作品が海外に流出していた。 若冲は、古画の模写ばか... -

ディープ大阪ツアー 釜ヶ崎・飛田・新世界
大阪観光といえば、大坂城やUSJが定番だけど、私が知人をよく案内するのは「ディープ大阪」です。30年前から歩いているけど、時代とともに様変わりしてきたので、備忘録がわりに記録しておきます。 JR環状線の新今宮駅に集合し、まずは日本最大... -

谷崎潤一郞記念館特別展「潤一郎、終活する~文豪谷崎 死への挑戦~」
無類の女好きだった谷崎がどんな「終活」をしたのか興味があって、芦屋市の谷崎潤一郞記念館を20年ぶりにたずねた。 谷崎は1915年、30歳で千代子と結婚して娘・鮎子が生まれた。だが、良妻賢母の妻とはあわず、奔放な妻の妹のせい子にいれあげ... -
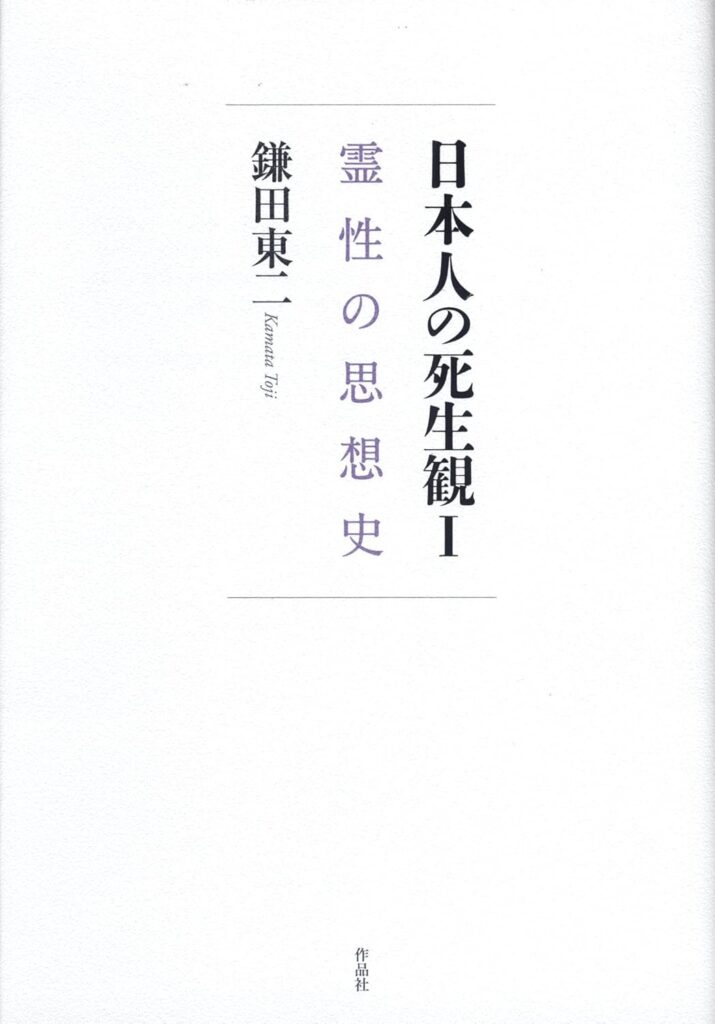
日本人の死生観Ⅰ 霊性の思想史<鎌田東二>
■作品社250330 日本の宗教は多神教文化で、その根幹には神々の融合や統合がある。大国主神が古事記で5つの名をもち、日本書紀で7つの名をもつのはそのためだ。 4つのプレートと寒流・暖流がぶつかりあう複雑な自然が、異質な他者を結びつける多様な...