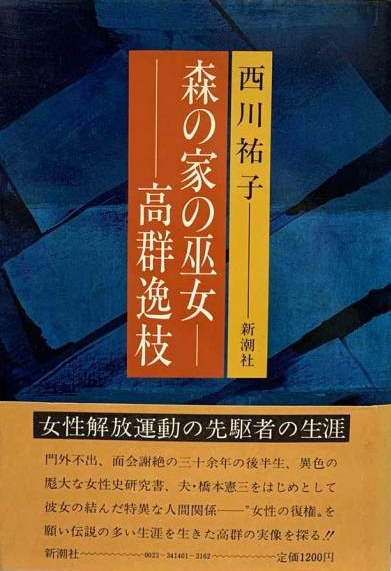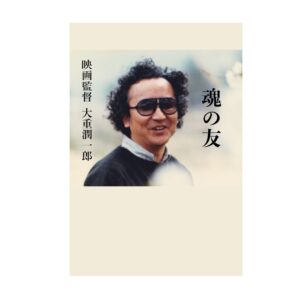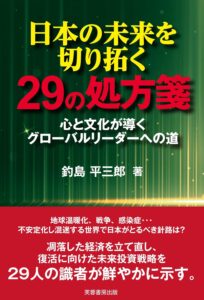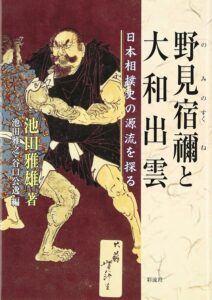■新潮社 2509
高群逸枝は「娘巡礼」から読みはじめた。みずみずしい感性にひかれた。その感性にひかれて多くの男が彼女に恋をした。男をふりまわす魔性の女でもあった……とはこの本でわかった。ほれてしまうと客観的になれない。以前に【こんな文章】を書いた私もまた高群逸枝の魔性にとらわれていた。
著者の西川さんは文学者であり人類学者でもある。10年間かけて膨大な資料を調べたから高群の魔性にとらわれず、戦前のアナキストや戦争協力者としての姿も描きだした。
敗戦前の2年余は、大日本婦人会の機関誌「日本婦人」で神国日本をたたえ、銃後の守りと殉死さえよびかけた。
無政府主義から日本主義へ、さらに戦後民主主義へと立場をかえた。
過去の「日本」に加担したゆえに戦後沈黙した知識人もいたが、高群は、原始的で「女性的な日本」を「封建的な日本」から切りはなし、他方ではアジアとの心情的連帯を強調して西欧的近代と対抗することで彼女自身の戦前・戦中・戦後の矛盾をねじふせた。どの時代でも高群は、抜群の感応力を発揮して大衆の願望を表現した。抵抗とか転向といった観念の通用しない、自己否定とは無縁のたくましい感性こそ「民衆の思想家」の本領だった−−。転向を批判するのは簡単だが、転向の経験をもふくめて高群の座標を明確にする西川さんの視点は独創的だ。
高群逸枝は、子どものころから、おとなしくてのろまだけど、弱虫をせめられると「あたい観音の子よ」ととんでもないことを叫んで立場を逆転させる。ことばを自在にあやつる巫女のような能力をもっていた。
師範学校の寮生活に耐えられず退学し、4カ月余の女工生活を送ったが、夜の勉強室に電灯を要求するなどして、最後は校長の娘だることがばれてやめさせられる。
代用教員になると、モンテッソーリの自由教育法を実践し、生徒には人気だったが、お茶くみもせず、酒席にもはべらないから、同僚には「御令嬢」とあだ名をつけられた。
そんななか後に結婚する橋本憲三と出会い、永遠の恋を誓って書き送る。それにたいして憲三は「この世には永遠というものはあり得ない。瞬間のみがある。まあ行けるところまで行きましょう」と恋愛瞬間説を説く。
熊本で知りあった別の青年からの恋文を同封して、どうしましょうかと相談すると、憲三は「勝手にしろ」とすねてしまう。
三角関係になやんだ逸枝は24歳で巡礼の旅に出る。
年齢と名前をたずねられると「花枝と申します。18になります」と答えた。この後10年間、読者の前では「18歳」をとおした。彼女は大衆がどのようなイメージにひきつけられるかよく知っていた。まさに「魔性の女」だった。
巡礼記を新聞に連載すると、ファンレターが次々に届いた。会いに来て結婚を申し込み、ききいれられずに投身自殺を図った青年もいた。「人間関係において特殊な感応力をもっていること、即興の才があること、マスメディアの魔力を知りこれを扱う能力を具えていることがよくわかる」と西川さんは分析する。彼女の巡礼記にのめりこんだ私は、ほれた弱みでそんなことにはまったく気づかなかった。
逸枝は連載のなかで、私はあなたが恋しい、あなただけを想っています……と、橋本憲三への誘いの信号をおくりつづけた、
多感の恋になやみ、大切なひとにあこがれ、支離滅裂にくるしんだ半年の旅。高群逸枝は晩年まで、この旅のことをくりかえしさまざまな文体で書きつづけた。旅行記を書くことは高群にとって納経帳をくるのと同じく、再び旅することだった。
1919年、妹を伴って家をでたが、熊本市までくると妹を旅館におき、橋本憲三のところへあいさつを告げに寄ってそのまま共同生活をはじめてしまう。
1919年暮れから1920年にかけて「感情革命」を体験する。結婚生活にともなう動揺した心理から吐きだされる詩を、朝日新聞の短歌の選者だった柳沢健は激賞した。
柳沢健は「20歳に足りない少女で、頽廃した村の貧しい家に育った」と逸枝を紹介した。逸枝は「娘巡礼」のつづきを演じていた。
東京で発表した長編詩「日月の上に」は、娘巡礼が、時代の予言者あるいは「神」としての詩人となってゆく経過をえがいた自叙伝という。
「娘はまだ、性格をもたないかもしれない」「詩人はまだ 性格をもたないかもしれない」と最終節につづる。
平塚らいてうは、性格を「ゆがみ」ととらえ、ゆがみのない人こそ天才、真正の人と呼んだ。高群逸枝の最終行は、性格をもたないからこそ、(私は)天才であるかもしれない、真正の人であるかもしれないという意味になる。逸枝の「天才宣言」だった。
その後、橋本憲三は、逸枝をともなって熊本の海辺で暮らす。これは、逸枝と生田長江のあいだに、恋愛に似た気持ちがうまれたことに気づいたからだった。逸枝は他人と、常識からみれば恋愛とみられる結びつきしかつくれない。魔性の女なのだった。
次の長編詩「東京は熱病にかかっている」ではたとえば第一次共産党事件をとりあげ、「1923年6月5日、地裂け天落つるとばかりに 大活字の人工的発作は、都下全新聞紙の個性を奪いぬ」と記す。知識人でもっとも民衆の方へ向いていた有島武郎が畑野秋子と情死すると「ふざけるな有島武郎」と罵倒する。
詩が書かれた1923年から発表された25年にかけて、プロレタリア文学は全盛期にあり、「民衆」は実態ある存在とみなされていた。
詩は第二次世界大戦による終末を予言していた。「……待ちくたびれた戦争がやってきて、科学的な方法で、全世界の都会をめちゃめちゃにした上でなくては自覚できないというのなら、この上何をいおう」と、世の右傾化を憂えた。 脱稿直後の9月1日に関東大震災が襲った。
橋本憲三は、上京する友人、文学青年たちを新世帯に次々に同居させた。家事が不得手な逸枝は、合宿のような生活をきりまわす主婦の役割に疲れはてた。同居人のひとり、平凡社社員の藤井久市と家出をした。
「同行の人には巡礼の道を教えたのちに別れ、自分は寺に籠もって恋愛論を書きます」という置き手紙をした。四国遍路の二番煎じをこころみたのだが、世を騒がすスキャンダルとなってしまった。
橋本憲三と下中弥三郎という2人の編集者は、事件を忘れるのではなく「書く」ことをすすめた。「家出の詩」が生まれ、「東京は熱病にかかっている」の付録となった。
「家出の詩」のなかで、結婚生活の破綻は性格の不一致などではなくて「結婚制度」からくるものだと断じた。「女の真の自覚は 結婚制度の改革などでなく、 結婚制度の撤廃を要求する」と。
「青鞜」発刊時の平塚らいてうは霊感詩人だったが、「青鞜」以後は神のことばを吐くことができなかった。らいてうの火を消したのは結婚と育児だった。だから、家庭を放棄する高群の蛮勇にたいしてらいてうは敬意を表しつづけた。
下中弥三郎(平凡社創設)は階級対立よりも都市ー農村の対立を重視し、高群と渋谷定輔を農民自治会という運動に参加させ、運動をになうべき農民と婦人を代表する象徴的人物とした。
階級闘争が性別の問題に優先し、社会主義政権のもとで家事と育児が社会化されれば婦人問題は解決するというマルクス主義者にたいして、逸枝はアナキストの立場から論争を挑みつづけた。
だが人生の折り返し点の36歳でいっさいの社会関係を断つように「森の家」にこもる。雑誌「婦人戦線」は廃刊となった。その原因は資金難でも内部論争でもなく高群逸枝の恋愛だった。恋の相手は、ずっと年下の松本正枝の夫である延島英一だった。瀬戸内晴美の小説「日月二人」がこの恋をとりあげた。
「森の家」の費用は橋本憲三が整えたが、軽部家は地所を貸しただけでなく、さる宮家とも、あるいはかつての鹿鳴館ともいわれる建物を解体した古建材を提供してくれた。
森の家で生みだされる高群逸枝の「母系制の研究」は、父系の家族という生活の実体は存在しなかったと主張する。その独創は、母系制遺制の発見そのものよりも、実証のための資料に「新撰姓氏録」(815年)をえらんだ着眼と、膨大な資料分析の方法、さらには推論のたてかたにあった。
出雲国造は、名祖族なので、一祖をつづけて祖変がない。逆に、遠国の国造の多祖のなかに出雲系が数多くみいだされる。中央名祖族が地方の豪族の女を妻問して、生まれた子をとおして女の一族に勢力をひろげていた。
オオクニヌシノミコトの子181神とは、ミコトが各地の女神、つまり母系氏族の女酋を妻問して生まれた子であり、彼らが母族をひきいて父神に従った結果、国作りすが行われたと神話を読み解く。
津田左右吉の「古事記及日本書紀の新研究」「神代史の研究」などは発禁処分になったが、その2年前の「母系制の研究」は弾圧をのがれている。津田が起訴された1940年に、高群逸枝は、皇紀2600年式典のために「女性2600年史」を執筆した。
1931年に森の家へ入居し、32年以降、「戦争の必然性をも信じる」「日本主義」「ファッショ」肯定の発言が増えていく。
婦選大会は、自主的な婦人団体が、議会主義と男女平等を否定するファシズムに抵抗するための共同戦線の場だったが、1935年から参政権問題と平和問題をとりあげる比重が減り、市政参加、母子扶助法設定、婦人労働立法といった具体的な問題に重点がうつされた。
官製・半官製の婦人団体は、戦争の進展とともに急膨張をとげた。反戦を掲げていた市民的婦人団体は解散に追いこまれた。1938年には、毎年婦選大会が行われた時期に時局婦人大会が開かれ、「起ちて負へ総動員の秋」と掲げた。非常時の協力は女性の地位向上につながるという判断にもとづいて、反戦から戦争協力へと集団による方向転換が行われた。
戦争協力は女の地位向上につながると信じたい国民精神総動員運動に加わった女性たちにとって、女性史研究成果をよりどころとした高群の文章は支えになった。全国の女性にとってほとんど唯一の情報源となった「日本婦人」の、ただひとつの連続読み物を高群逸枝が執筆し、終戦直前の廃刊までつづいた。
下中弥三郎は1931年以後、急速に右傾し、戦争中には大政翼賛会の中心人物となった。彼がよりどころにした集団は「農民」→「日本」→「大亜細亜」と拡大した。戦後は賀川豊彦らと世界連邦運動に熱中した。「大東亜共栄圏」から「世界連邦」へと集団は再び拡大された。
高群逸枝も、近代と西欧に対抗して女性と農民(すなわち民衆)の側に立っているという意識はかわらなかった。あるべき民衆が国民にかわり、あるべき「村」が巨大な村である「日本」へと拡大しただけだった。戦後は国民が再び大衆となり、自分は大衆と共に苦しみ共に歩んできたという意識が高群を戦後民主主義に無理なく結びつけた。
家父長制家族制度の思想に反論して、国体の思想をゆさぶると共に、母系制の側からの血縁国家論を展開し、万世一系の天皇統治については支持した。
59歳で完成させた「招婿婚の研究」は高群逸枝の頂点の作品である。
柳田国男は、婚姻は歴史を通じて男性主体の一夫一婦婚が原則だったと考え、婿が女の家に労役に入ることもあるが、その期間の後は男が女を男家に連れて帰ると主張した。
だが進化説でなければ女の「家」からの解放はあり得ないと考える高群逸枝は、婚姻は、群婚(ツマドイ)ー招婿婚(ムコトリ)ー娶嫁婚(ヨメトリ)ー相互婚と進化し、招婿婚と娶嫁婚のあいだで婚姻の主体は女から男ないし男の家にかわり、その後の相互婚で両性の寄り合いとなると考えた。
それを論証するため、藤原定家「明月記」をはじめとする漢文体日記約50部600年分を中心資料とした。
招婿婚の研究を開始して2年で4000冊を読破(すごい!)、カードを1万枚とったところで破棄して再出発した。「招婿婚の研究」は2600枚で脱稿。「平均10時間の日課で13年9カ月かかりました」。すさまじい知的肺活量だ。
高群は、有史以前から室町期までつづいた招婿婚の本質は、「自然婚」であり、恋愛のように離合できる一時の一夫一婦制とみている。ただしこの自由は生活の氏族保障によって支えられており、近代的な個人の自由ではない。
研究は、「自然」と「制度」とのあいだの長年にわたる闘いとして描いている。
そのせめぎあいは、平安朝の純婿取期にいたって頂点に達する。夫婦同居となり、婚姻は女の父親がつかさどる。両親は住居を娘に提供し孫を養育する。娘夫婦はある時期以後は独立する。夫婦は同族同士でないかぎり死後はそれぞれ自族の墓に入る。
高群は、源氏物語の姦通例にみられる罪の意識を、後世の制度を冒した不義密通を罰せられる恐怖と同一視してはならないと注意する。女房層にみられる多夫あるいは自由恋愛は男性側の多妻と同じ性質のものだからだ。そこには制度でなく、なるがままの自然を旨とする招婿婚の本質があるという。
純婿取婚期につづく経営所婿取婚と擬制婿取婚の章は「自然」が「制度」との闘いにやぶれる過程だ。そして娶嫁婚になると、自然にして自由な一夫一婦婚から、法律その他の強制力を借りた制度的一夫一婦婚、一夫多妻婚があらわれ、公娼制も制度化された。
高群は「自然」の生命生産の立場から、産業本位に編成され私有財産の容れ物となった父系の「家」に対抗する。その一方で、子育て中心の母系家族の共同生活は閉鎖性と停滞をまぬがれられないから、父系氏族と闘争的な個人に敗れて当然であるとも論じた。
「招婿婚の研究」は、「自然」と「制度」の抗争が主題だ。「自然」とは、男性にたいする女性、都市にたいする農村、工業にたいする農業、文明にたいする原始など、彼女が加担した遅れているものの側を指す。
原始楽園説をふくむ高群固有の基本図式は「女性の歴史」にもうけつがれる、原始・古代をあつかう上巻は「女性中心の社会」、封建時代の中巻は「性の地獄」、近現代にあたる下巻は戦後の解放気分を反映して「解放のあけぼの」とした。
高群逸枝は、原始婚の遺制や女性的文化という最古層こそが日本文化の本質と考えた。神道・仏教・儒教を同化吸収して形成された武士道を日本文化の華とする新渡戸稲造の男性的日本とは対照的だった。
高群の女性的な文化とは、無文字的な文化をさす。古事記、万葉のうたの数々、室町以後は五木の子守歌のような民謡他のうたいもの、らいてうの「青鞜」発刊宣言、中山みき、出口なおなど新興宗教の教祖のお筆先が女性的文化としてあげられている。
敗戦によって、農民は小作人ではなく、婦人も法律上の無能力者ではなくなった。戸主権は消えた。
戦後に増大する核家族は、独立した人格をもつ男女の寄合婚がたてまえだが、現実には家父長制家族の最終段階である夫権小家族の「ホーム」にすぎない、と高群は位置づけている。
女性はしだいに独立した労働力となって家庭から独立し、核家族はこわれて、孤立した個人にまで細分はすすむと高群は予想した。「夫や父は奴僕化され、妻は無為有閑者となり、子どもは不良化」という予想は1980年代を予見しているようだ。
ひとびとは孤独になる自由を得て、孤独の集まりが大衆となる社会が生まれる。孤立化がきわまったとき、あらたな共同性をさがしはじめ、独立した男女の寄合婚による単婚家庭がつくられる、と予言し希望を託した。
もうひとつ、子を連れて家庭からさまよい出た女性たちの保障の要請にもとづく大規模な社会編成が起こり、経済は共産制、族制は母系型になるだろうと「高次の原始復活」を予測した。今現実にシンママの貧困が問題になっているが、残念ながら大規模な社会再編は起きていない。
「女性の歴史」の最終章は、母親たちによる平和運動、社会主義諸国の存在、科学技術の進歩による「平和と愛の世紀」という希望をつづった。だが、あかるい予言は1958年に「女性の歴史」を書きあげた前後から、社会主義諸国間の対立など次々に崩れていった。
高群逸枝は1964年に亡くなる。橋本憲三は、67年に「高群逸枝全集」を完結させると「森の家」をひきはらい、水俣市秋葉山に移住し、逸枝の墓をつくった。チッソ工場をみおろす場所だった。
早い時期に「森の家」をひきはらった原因のひとつは、逸枝の最後の入院と葬儀をめぐって橋本憲三と市川房枝ら後援者との間に、生活感情、経済観念、彼女の仕事の成果の所属についての考え方のちがいが明らかになったためだったという。
入院のために「森の家」を出たとたん、「森の隠者は人びとの心をつなぐ力を失ったかのようである」と西川さんは記す。
橋本は、逸枝のことばを森の神秘に深くつつみ、あくまでも娘巡礼であり、女詩人、予言者、連綿の糸を紡ぐ老媼というイメージを守りぬこうとしたのだ。