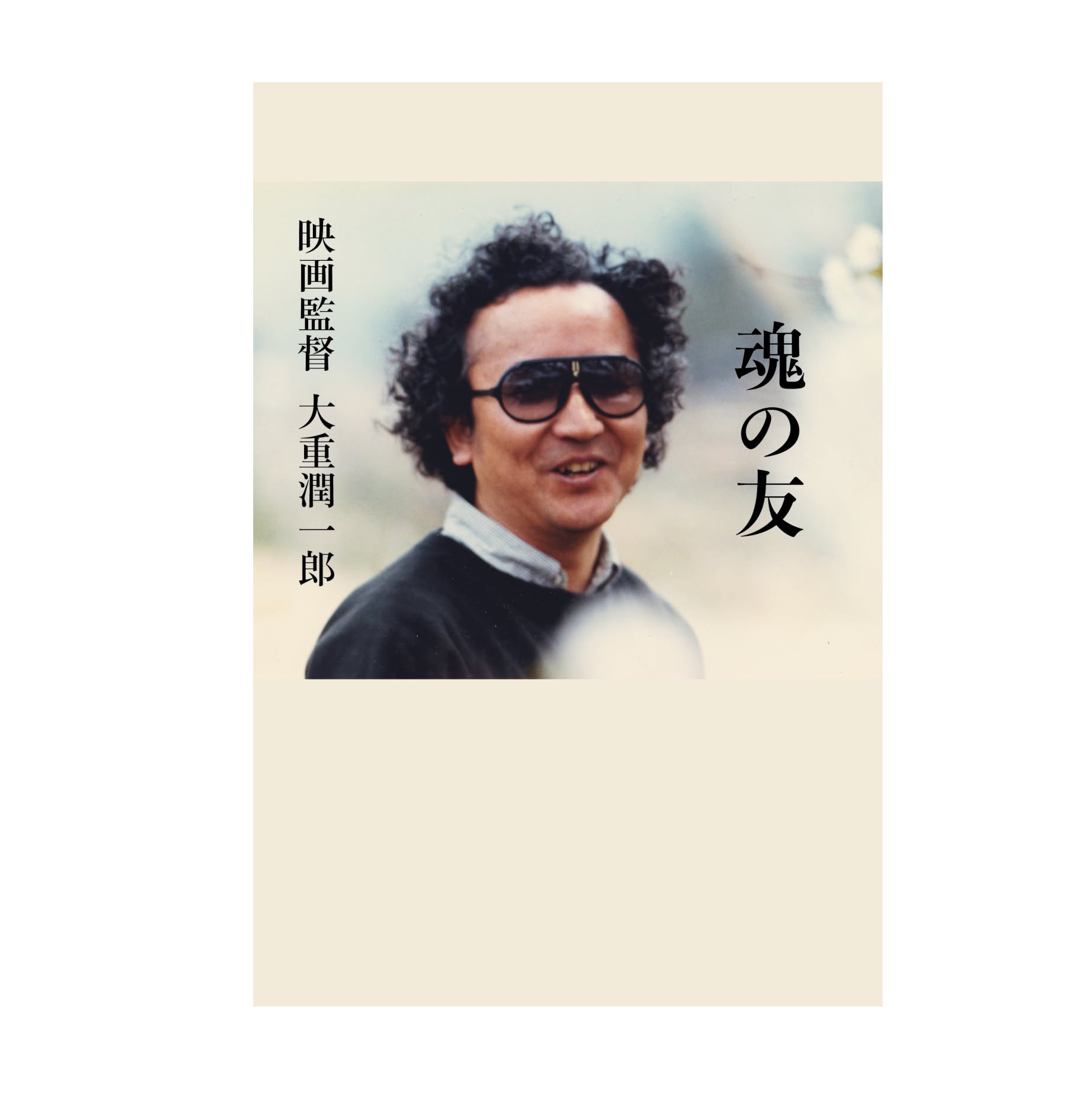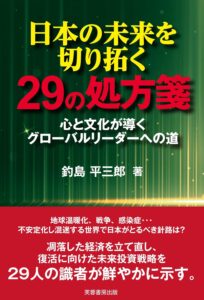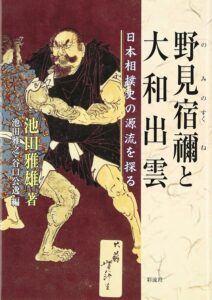■<高橋慈正編>250922
「われらが海民 映画監督大重潤一郞著作集」と同時に編まれた。大重監督は「久髙オデッセイ」を仕上げてまもない2015年7月22日に、8人の友人たちに看取られて旅立った。そうした人々の文章からは、大地や海や地球につながる命を感じとり、それを映像にしてきた監督の姿が立ちあがってくる。
鎌田東二さんは、カトリック司祭で上智大学教授だった故トマス・イモースさんは、「詩人の存在意義というのは、太古からの人間の普遍的な体験を言葉で表現するところにある」という言葉を引用する。詩人は「いのち」を感知する人である。この本に文章をよせた人たちは詩人の力で「世直し」をしようとしている。
大重監督は阪神大震災に直面してこんな言葉を残した。
「地球から、次の千年の未来の人々へ贈られた啓示であったのではないかと思えてならないのです。今そう思うことで、ようやくこの現実に対峙し始めています。そしてそれが小生にも訪れている確かな未来なのです」
「街が壊れ、家の壁が崩れたら、人を隔てる壁がなくなった。エレベーターが止まったマンションの階段を、金髪にピアスの若者が何度も行き来して上階にいるおばあさんに水を届ける姿をみて、まさにここが極楽浄土だと思ったのも束の間、3年経って街が復旧したらみんな何もかも忘れてしまった」
大きな災害は、ふだんは隠されている「生命」「浄土」のようなものを大地の裂け目から現出させる。東日本や能登の被災地を歩くと、悲惨な状況なのだけど、菩薩のようにやさしい人や命を支え合う共同体が見えてくる。
でもほとぼりがさめると消えてしまう。だからこそ、災害を記録し記憶しなければならないのだ。
高木慶子さんの言葉も、災害のそんな側面をとらえている。
--大自然がちょっと動くだけで地球の上にいるものはとっても辛く悲しい思いをするのだけど、でも、大自然はこんなに静かで豊かなものなんだ、その「大自然の中のいのちへの讃歌」、(「光りの島」は)先生のお祈りだったと思うのです--
大重コミュニティの人たちは「身体性」を大切にする。
映画「縄文」に出演した天人純さんは、断食をして、部屋のブレーカーも切って,素足で砂利の上を歩いて、下着はフンドシにして、麻のゴワゴワ衣装を着てしばらく生活した。靴にズボンの現代人とは動き方がぜんぜんちがうことがわかった。「現代人は、身体内部に個人に固有の意識の構造があるのだが、縄文人の場合、巨大な意識の中に身体が浮いて大地と繋がっているという状態」という。「今、縄文という生命根底に流れるものを取りもどさないと我々は人間本来に帰還もできないし、未来にも進めないのだ」と大重監督は言った。
島薗進さんは「大地」と「海」のちがいを指摘する。
--大地と共に生きる人との共振は大重監督の多くの作品にあるものだが、久髙オデッセイは、さらにそれを開かれた海のかなたへの憧憬を結びつけた。海と共に生きる人びとの開放性が見る者を元気づける。そして、いつしか大重監督が語る「地下水脈」を自らのうちに感じとるようになるだろう--
なるほど。ほかの作品にはない「久髙オデッセイ」独特の明るさは「開かれた海」とのつながりによるのか。能登でも、山里の伝承よりも、海の伝承のほうがそこはかとない明るさを感じたのを思いだした。
最後に印象に残った言葉を2つ。
深海で生きる魚族のように 自らが燃えていなければ 何処にも光はない
(ハンセン病詩人、明石海人の言葉)
あきらめぬ 生き抜く先に いのちあり 大地空海 足元の愛