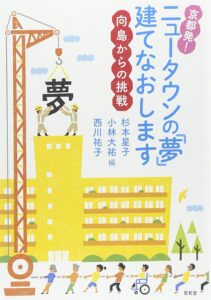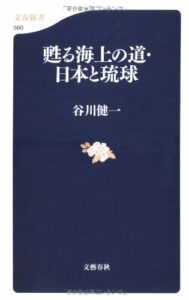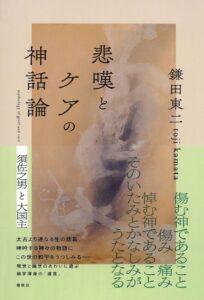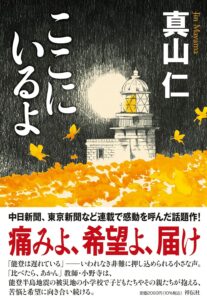安藤さんの彫刻は、円空仏とどこかにているなぁと思った記憶があり、奈良県立美術館に行ってみた。
1961年、東京の下町生まれ、29歳のときいわき市へ。東日本大震災による津波で自宅もアトリエも失って、原発事故とともに奈良へ避難してきた。

「営みの祈り」という畳数枚分もある横長の作品は、右には生業(営み)として田畑をたがやす人びとがえがかれ、左には津波と火災、原発が爆発する場面だけ色をつけている。

「福島原発爆発ドローイング」は原発の廃墟の無機質な不気味さを黒い線だけで表現する。
丸木夫妻の原爆の絵を彷彿とさせるけど、安藤氏の真骨頂は津波と原発爆発によるカタストロフィーと対比するように彫られた木彫りにある。

ヒノキから彫りだした「3.11 光りのさなぎたち」、トーテムポールのような「宇宙の果実の梯子」、狛犬の木像……。

「歩く富士山」は富士山に足がはえている。ユーモラスだけど、山は生きているがゆえに怒れば大惨事がひきおこすことも暗示しているようだ。大地からめばえ噴きだす生命の力をかんじる。「コスミックフェイス」は中米マヤの遺跡のように宇宙とのつながりをあらわしたのだろう。


一番の大作は「約束の船」。円空仏のような人型の木像が地面に無数に横たわって船を形づくり、その上に、神仏や人間、動物、異形の生物がたちあがっている。

ノアの方舟のイメージだろうか。横たわる木像は死者であり、それが養分やエネルギーとなって新たな生命をうみだす。「約束の船」は、生命の循環をつかさどる地球のあり方なのかもしれない。

昔は抽象絵画はさっぱり理解できなかったが、中年になって抽象芸術と縄文とのつながりを意識しはじめて、一部の現代美術に心がうごかされるようになった。たぶん安藤さんは、技巧をこらすのではなく、かんじるままに「命」の形を彫っているのだろう。
安藤さんはインタビューでこんな話をしていた。
「最近のアーティストはおりこうさんになって、アートなんて余裕がある世界の産物だと言う作家もいる。佐藤忠良(1912〜2011年)という彫刻家はシベリア抑留を体験した。『極限状況でも死なない人っているんですよ。詩を書いたり、歌をうたったり、ものをつくったり……創造行為をする人は最後まで生き残るんですねー』と彼は話していたんです」
ナチスの強制収容所を生きぬいたフランクルの文章とおなじだ。吉田さん自身も、3.11でなにもかもが破壊されたときに創造の意味を体感したという。
「どんなめちゃくちゃの時でも創造することを忘れないで。頭で考えるのではなく強靭なデザイン力と直感力が大切。自分のリアルを目の前に生みだして、それをだれかにプレゼントしていく。お金の問題ではない。芸術家って本来は究極のボランティア人間なんですよ」
なるほど。芸術ってボランティアなんだ。文章を書くのもいっしょで、自分のかんじたリアルを目の前に表現する。必要とする人がいればそれをプレゼントする。それが自分の天命につながっていく。そういう原点を再認識させられる作品群だった。