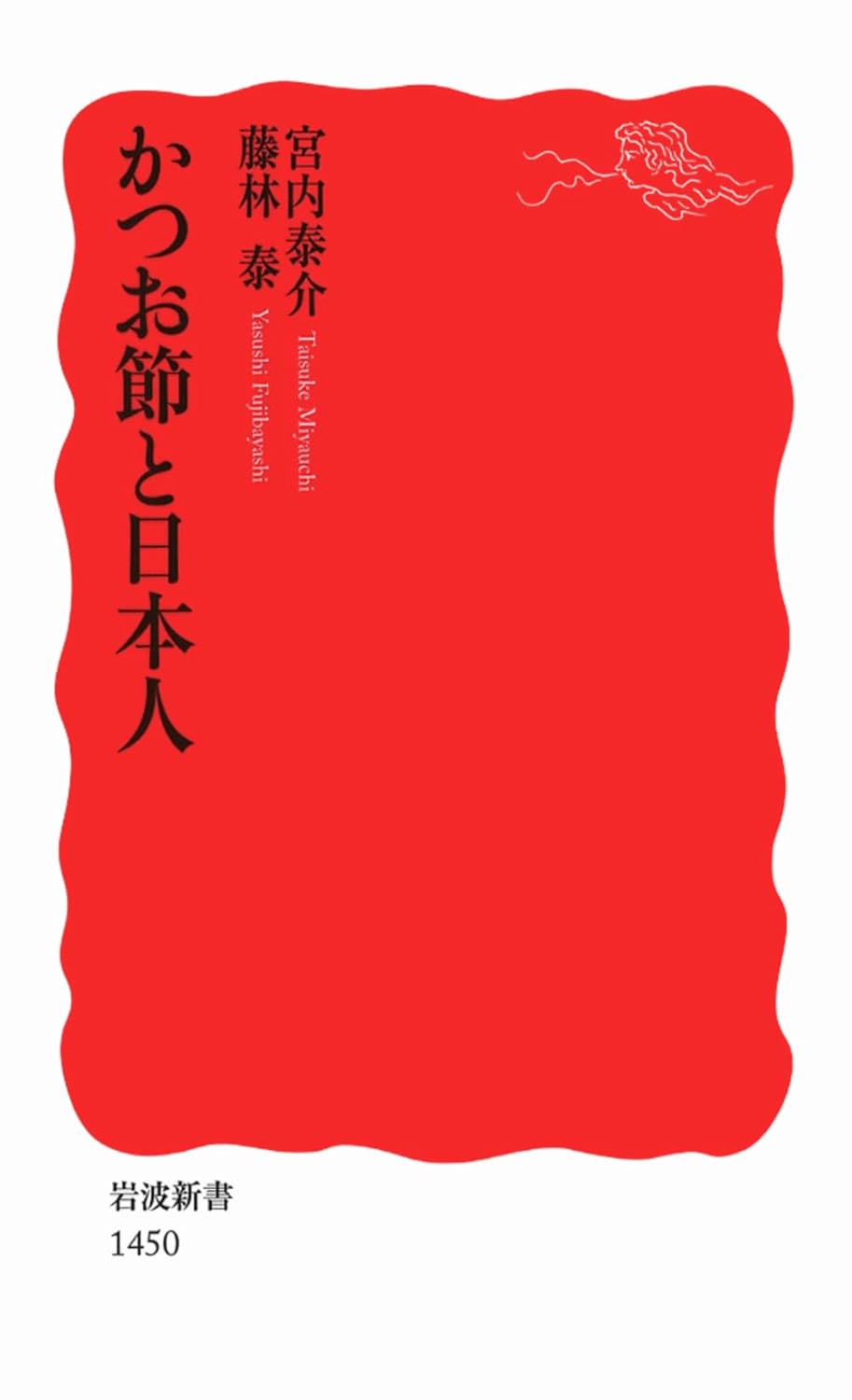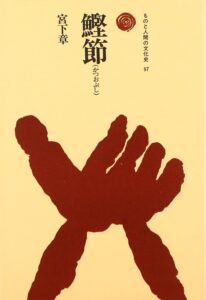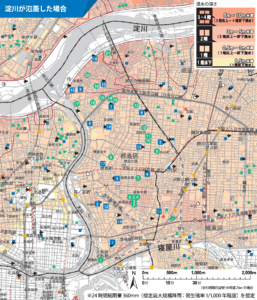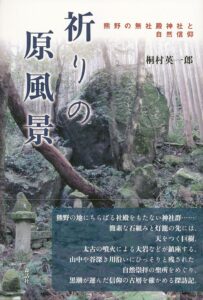■岩波新書250810
かつお節とモルジブの関係を知りたかったが、この本は明治以降の話が中心だった。でも知らない話が次々に出てきておもしろかった。
乾燥しただけのかつお節の原形は上代につくられていたが、生産地が増え、流通と販売の担い手が登場し、庶民の手に届きはじめたのは約300年前、江戸中期だった。
焼津市は、枕崎市、指宿市(山川町)とならぶ日本三大産地だが、明治前期には同じ静岡の田子にも負けていた。明治政府が博覧会や共進会、品評会に力を入れていたのをうけ、地域で団結して博覧会に出品することで一気に成長した。
鰹節は戦国時代の武士が糧食としたが、日清・日露戦争で鰹節の味を覚えた兵士たちが復員後、故郷に伝えたことも全国に広がる原因のひとつとなった。フランス生まれの缶詰がアメリカの南北戦争で普及したのと同様、戦争が密接にかかわっていた。
沖縄・宮古島のわきの池間島の漁師は1894年ごろから、八重山諸島で貝をとり、貝は大阪などの貝ボタン工場に運ばれた。ボタンはヨーロッパに輸出され、貝の需要が増大したため、和歌山県などから多くの人が貝を求めてオーストラリア・トレス海峡の木曜島やフィリピンへ渡った。
沖縄は、かつお節では最後発だったが、1922年には、岩手・静岡・鹿児島とならんで1000トンを超え、池間島は大正年間、かつお節ブームにわいた。だが昭和の恐慌で組合の経営が行き詰まり、多くの人が南洋移民となった。戦後、池間のかつお節は再開し、1970年代には、商社や水産会社が南洋でカツオ漁をはじめて池間の漁民がリクルートされた。だが2007年には、池間島のカツオ漁船はゼロになった。
ほかの伝統食品とちがって、鰹節は21世紀にいたるまで生産量が増えつづけている。1969年、かつお節問屋の老舗にんべんが「フレッシュパック」という削り節の小口パックを発売した。これが起爆剤になった。
昔ながらのカビ付けをした「本枯節」ではなく、表面を削る整形やカビつけの工程がない「荒節」が主流になった。透明パック入り削り節によって、「シュッシュッ」というかつお節を削る音は家庭から消えた。
きれいな「花」をつくるには、脂が乗っていない熱帯のカツオが好ましい。そこで大手漁業会社が主導して「南進」が再開する。冷凍カツオを日本へ送るようになった。
さらに1980年代以降は、めんつゆ、だしの素などが広まり、1990年代以降は、健康志向で醤油や塩を控え、そのかわり、かつお節や昆布による「こく」が重視される。ミツカンはめんつゆに入れるだし原料を1990年代からの10年間で3倍に増やした。そのぶん醤油を減らすから、日本の醤油生産量は、1990年代以降、減りつづけている。
かつお節全体に占める荒節の割合は1970年代は50%だったが、今では90%を占める。仕上節、とくに本枯節を製造する業者は、零細業者が残るのみになった。
かつお節生産地は、削り節や調味料の原料生産地になり、大手加工メーカーが、焼津・枕崎・山川のかつお節製造業者たちを系列下に収めるという図式になった。カツオの値段や油代が上がっても製品価格は、大手メーカーやスーパーの力で低く抑えられたままだ。インドネシアやフィリピンからの輸入増も産地を苦しめている。
戦前、多くの沖縄の漁師が北スラウェシに渡ってカツオ漁や南洋節づくりに携わった。現在も、インドネシアから輸出されるかつお節のほぼ全量が北スラウェシ(ビトゥンとその近郊)で生産されている。
茨城県・大洗では1990年代、水産加工の工場で多くの日系インドネシア人が働いていた。そのほとんどが北スラウェシ州出身で、祖父たちの大多数が沖縄出身のカツオ漁師だったという。