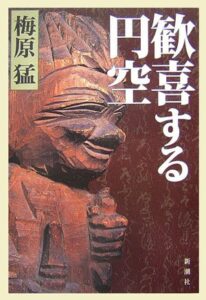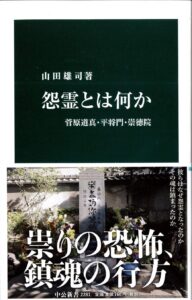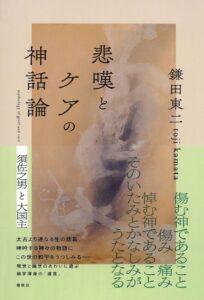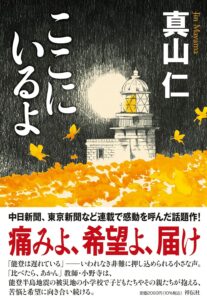■神道史学会 251031
上賀茂神社と神奈備山の神山の関係、さらには貴船神社との関係を知りたくて手に取った。上賀茂神社の宮司が1972年書いた。
奈良の葛城には、出雲関係の神々が祀られ、その中心は鴨都味波八重事代主命神社と高鴨阿治須岐詫彦根命神社だった。
建角身命を中心とする部族は葛城から北上してきた。高野川と賀茂川のうち、高野川を選ばなかったのは、小野氏が高野川上流にいたからだ。
賀茂県主族は、「庚午年籍」に、現在の上賀茂太田神社の東方の神坂に居住していたとされている。彼らがこの地を開拓するため、守護神として賀茂別雷神を招きくだした。
上賀茂神社の2キロ北にある神山は、頂上に巨大な岩石が密集して磐座をなしている。最初はここに神が降臨すると信じられたが、後に神山全体が天降り坐す場所と考えた。山上の祭祀を山麓に移した斎場の跡地が「貴船神社」になった。上賀茂神社(上社)の本殿は神山を拝む遥祭殿だった。
賀茂川上流の貴船神社と神山と上賀茂神社は直線上にある。上賀茂神社の祭神の賀茂別雷神は、母のタマヨリヒメが賀茂川で遊んでいるときに流れてきた丹塗の矢をそばにおいて寝たことで別雷神を妊娠した。
賀茂川上流には貴船神社がある。丹塗矢は貴船の祭神をあらわしている。つまり賀茂別雷は貴船の神とタマヨリヒメの息子なのだ。
賀茂社は里宮、貴船社は奥宮という関係だったと筆者は言う。
だが、賀茂の勢力が増大すると、賀茂側は「貴船神社は往古より賀茂社の摂社だ」と主張し、「鎮座当初から独立している」と主張する貴船側と土地争いがおきた。争いは平安から江戸まで数百年にわたってつづいた。
権力をもつ上賀茂が訴訟ではいつも勝ち、江戸末期まで貴船は上賀茂の摂社あつかいだったが、明治維新後に独立することになったという。