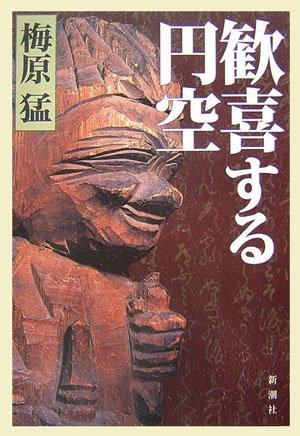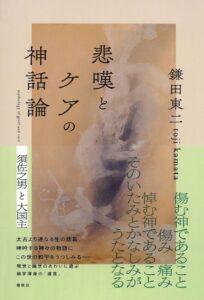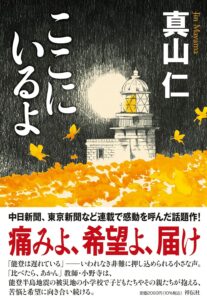■新潮社251030
奈良時代の泰澄や行基の後継者として円空をとらえる。
泰澄は白山信仰をつくりだした。白山の神は、稲作と養蚕に結びついている。白山の主峰・御前峰の本地仏が十一面観音であるという信仰は、仏教を農民に定着させるのに大きな役割を果たした。
奈良時代の仏教は、藤原氏の氏寺である興福寺が支配していた。聖武天皇はその興福寺をしのぐ規模の、天皇家の氏寺というべき東大寺を建立しようとした。伊勢の神は(藤原氏の)春日神と蜜月関係にあるから助けてくれない。そんなとき、応神天皇とその母の神功皇后をまつる宇佐八幡宮の八幡神が聖武天皇の前にあらわれた。東大寺建立という大国家事業によって行基がひっぱる八幡信仰が国家宗教となった。そして空海の真言密教によってほぼ完全に仏教にとりいれられた。
奈良時代の仏像は、金剛仏、乾漆仏、塑像仏が主流で、行基や泰澄の木彫仏は例外的だった。
行基仏は、素木で彩色がなく、木の生々しさを残し、神像と仏像が同居する。円空仏とおなじだ。円空が白山信仰の修験者となったと思われる高田寺には行基仏の薬師如来坐像があり、円空の中興した弥勒寺の本尊は、行基作の弥勒菩薩坐像だった。
円空の思想は、天台密教、華厳思想、法華思想と結びつくが、その中心に泰澄の白山信仰があった。円空は神仏習合の思想と木彫仏の制作において、泰澄・行基・空海の流れをうけつぐ存在だった。
平安時代の仏像は木彫仏ばかりになる。木には神が宿るとされ、木から仏をつくることは神仏習合の思想とむすびつく。
木彫仏の技術は寄木細工の技術を生み、精密な技術で知られた平安中期の定朝らが平等院鳳凰堂の本尊などの傑作を生む。定朝様式がマンネリ化すると、鎌倉初期に運慶による剛健な像が登場する。
修験道は鎌倉・室町に全盛期をむかえ、木彫仏も完成期をむかえるが、その後衰えていく。仏像を必要としたのは奈良・平安の真言密教や天台密教だった。鎌倉時代の法然・親鸞らの口称念仏による浄土教は、名号が礼拝の対象となり、仏像は不要になる。本尊も来迎印を結ぶ阿弥陀如来の立像にかぎられた。禅は人間そのものが仏になるという教えであり、礼拝の対象としての仏像はいらない。日蓮宗も日蓮上人像だけが重んぜられる。江戸初期に生きた円空は、泰澄・行基の伝統を復活し、木彫り仏制作の原点に帰ろうとした。
修験道は、江戸時代の檀家制度で僧の移動が禁じられて衰え、明治の廃仏毀釈・神仏分離によって壊滅した。武士と同様に山伏も姿を消した。
梅原は、円空仏を3つの時期にわける。1671年までの第1期は白山信仰を忠実に守った。1679年までの第2期は「弥勒信仰と護法神出現の時代」で特徴ある円空仏が誕生した。第3期は、十一面観音を本尊として脇侍に善女龍王と善財童子を置く、独自の白山信仰が完成した。
円空は、芭蕉の「奥の細道」の24年前に、アイヌの住む北海道にまで足を延ばした。円空が訪問した3年後にシャクシャインの乱が起こった。
厳寒の大峰山で修行したあと滞在した志摩半島には184枚の絵が残されている。これらは円空の作風の変化を示しているという。円空彫刻のエッセンスといえる護法神があらわれ、絵柄は次第に簡略化される。絵の簡略化を彫刻に活用することで、12万体造顕の夢を実現できると円空は確信した。竜泉寺(名古屋市)で馬頭漢音や千体仏を彫り、荒子観音寺で、3メートル超の仁王像とその余材で木端仏など千数百体を彫った。
絵を時系列でならべると、途中から釈迦の光背が消える。釈迦は大寺の奥深くで金色の光背に包まれているのではなく、庶民のかたわらにいるという思想だ。この絵を描いた5年後の1679年に白山神の「ここに釈迦あり」という託告をうけた。庶民の釈迦になることで、円空に乗り移ることができた、と梅原は見る。キリストはおれたちといっしょに汗をかいている、とうたう中南米の解放の神学と通ずるものがある。
法然は、末法の世では「南無阿弥陀仏」の念仏が救われる唯一の仏の道だと言い、日蓮は、「南無妙法蓮華経」という題目こそ仏になる唯一の道と考えた。禅は、寺院も経典も滅びる末法の世では自分が仏になることだけが成仏の道であると説いた。
円空は、末法の仏教を護るのは龍女と護法神だと考えた。人間以外の宇宙的な力、龍の力を借りずには仏法は護りきれない。神々はすべて護法神となって仏法を護らなければならない……と。その証拠に龍泉寺の馬頭観音像の脇侍には熱田大明神、天照大神がついている。末法の世では、天照大神さえも仏法の守護者となるべきだと考えたのだ。サムシング・グレイトを想定する古代的・縄文的な感覚といえないだろうか。
「円空和歌集」には「楽」「喜」「歓」という言葉がしばしば登場する。円空の思想の中心は生きている喜び楽しみを礼讃することであり、神々の清らかな遊びであるという。空海は密教の最高の境地を「大笑」とよんだ。現実を絶対肯定する空海の精神を円空は体現したと梅原は見る。
円空の歌と西行の歌の比較も興味深い。西行は京での自分の歌の評価をしきりに気にした。その自然観は「古今集」をうけつぐものだった。円空と同時代の芭蕉の自然観も「古今集」の枠から出なかった。
円空の自然観はちがう。どのような日本人の歌にも見られない、超古代人の声がきこえてくるような雄大な世界観が脈打っている、という。たとえば……
やすやすと 伊勢御神 遊ふらん 竹馬にのりて 春来らん
(アマテラスが竹馬に野って遊んでいる。それを見れば春の到来がかんじられる)
遊(ぶ)らん 浮世の人(ハ) 花なれや 春の初(め)の 鶯の声
(梅の花を愛でて遊ぶ人自身が花である……円空は人生の深い闇を生きてきたが、心に花を絶やさず、心はいつも春であった)
古今集以来の歌人は世界をすべて美的享楽の対象とするから、民が従事する生産と労働の世界は目にはいらない。円空はちがう。
御空より 玉そ降(り)ける 清浄(きよき)地の 神の御前の 新田(あらた)成(り)けり
(空から待望の雨が降った時の歌……新田の開拓が成功した喜び)
一方でこんな歌もある。
白紙に 血ぬる人の 多くして 霊のおもたち 世々モたちなん
「白紙に血を塗る」というのは人を殺したりすることを意味するのであろうと梅原は解釈し「殺された人の霊がどのように恨みを晴らして世を乱すか分からない。円空は人間のすさんだ心を深く嘆いている」と解説する。
円空と同時代、かれの地元尾張藩でキリシタン弾圧が吹きあれた。
「そのような闘争の世界は彼の好むところではなかったであろう。和合の世界こそ彼の理想の世界だった」と梅原はかくが、それだけではないような気がする。
円空ほどの人物が、尾張藩だけで数千人が斬首された弾圧から目をそむけるはずがない。伊藤治雄は、切支丹禁制に苦しむ人々の心の救済に円空は心を砕いたとみる(「円空とキリスト教」)。「白紙に血を塗る」というのはキリシタンの悲劇を表しているのではないだろうか。
梅原は、高田寺の薬師仏などに「縄文」を見る。「縄文の文様も風の流れ、水の流れに象徴される霊の流れを表すものであると私は思うが、……この衣文の流れには、縄文時代以来の日本の霊が復活したような感がある」
また円空の絵は棟方志功につうじるという。棟方志功の絵もまた縄文系だ。円空の歌を「超古代人の声がきこえてくるような雄大な世界観が脈打っている」というのも縄文的なひびきをあらわしているのだろう。
円空=木地師説をとり、円空を単なる職人とみてその技術のみを考察すればよいと考えた五来重を、「五来氏は詐欺師であったと思わざるを得ない」とこきおろすのも梅原らしくて心地よかった。
梅原は、幼くして両親を亡くした円空に自分との共通点を見る。彼自身の人生と重ねてつづる部分も興味深かった。