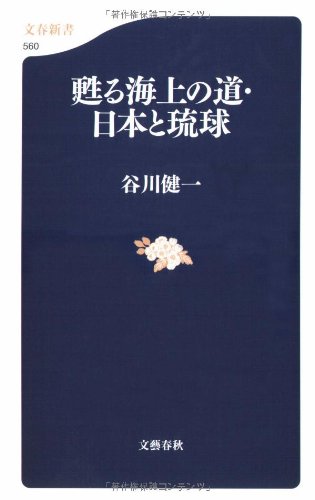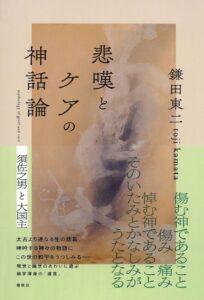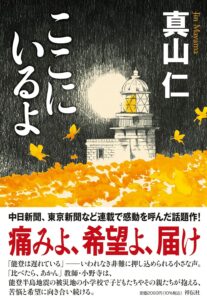■文春新書251022
土器のない旧石器時代の生活をしていた琉球を文明化したのは九州の石鍋の導入とそれを模倣する土器の出現であり、それを介在したのが家舟にすみ交易をにない「倭寇」ともよばれた海人たちだった。さらに、琉球の第一尚氏王朝は、熊本・八代の海人系の武装集団が打ちたてた……という。ダイナミックな展開に目が白黒した。
福岡には志賀島の阿曇、宗像市の宗像、それに鐘崎の海人がいた。日本の代表的海人族の発祥の地が集中していた。鐘崎の枝村は、壱岐や対馬、長門、さらには能登の輪島まで広がっていた。黒潮にのれば山陰、北陸まで進出することのできる地の利があった。
同一形式の土器や黒曜石が韓国南部から沖縄本島まで出土していることから、縄文時代から弥生時代にかけて、沖縄本島が九州と交流関係があったことがわかった。
対馬は、多くの古墳があるが五島列島には古墳は存在しない。対馬は平地にとぼしく、朝鮮に食料を求めてきた。なだらかな五島で銅剣銅鉾が1本も出土せず古墳もないのは、五島が海人の島だったからだ。
鹿児島でも、志布志湾は古墳が集中しているが、川内川以南の薩摩半島には古墳はほとんどない。阿多隼人の拠点で東シナ海に面して漁撈文化がおおっている。淡路島の古墳の大半が後期のものであり、熊野に古墳がないのも、海人族の拠点だったためだ。
南方産のセグロウミヘビは黒潮によって出雲の海岸にたどりつき、出雲神社や佐太神社の神有祭りにはなくてはならぬものだった。
保元の乱に負けた源為朝が沖縄に行ったという伝説がある。「保元物語」では源為朝が阿多忠景の娘婿となって九州で活躍したと記されている。その後に阿多が南方へ逃亡したことが為朝伝説にすりかわったと考えられる。
12世紀の琉球は原始社会から脱してまもなくだった。第一尚氏の統一王国以後は奄美は琉球に服属するが、それ以前11、2世紀のグスク時代黎明期は奄美の方が沖縄本島よりも先進地帯だった。
八重山では紀元前には土器が出土したが、土器のない時代が1000年以上つづいた。12世紀、長崎県の西彼杵半島を主な産地とする石鍋がもちこまれ、それにそっくりの形態の外耳土器が誕生した。これによって無土器時代は終わり、グスク時代が訪れた。石鍋は、琉球列島に石器模倣土器を出現させ、新石器時代を終焉させ、農耕社会の成立にかかわった。琉球社会を1000年の眠りからゆり覚ましたのは九州産の石鍋だった。
瀬戸内海における家船の根拠地は能地(三原市)、二窓(竹原市)、吉和(尾道市)で一本釣りを主体とした。西北九州の長崎の家船や釣り漁をおこなわず、銛や鉾を使って魚貝をとる。潜水して魚をとった。
(九州の)家船のグループは、海にもぐって、敵の船腹に穴を開けるのを特技とした。もぐるから髪の毛は黄色く脱色する。朝鮮人からは海賊「倭寇」と怖れられた。
彼らの根拠地は、九州では西彼杵半島の大瀬戸や﨑戸であり、大瀬戸は滑石製石鍋の一大産地だった。それを沖縄にはこぶのも家船が利用されたと考えられる。
石鍋や鉄器を家船で運んだ交易集団のなかには武士団の残党らも加わっていた。家船じたいが海賊まがいの存在だった。
そのなかで抜きんでていたのが肥後八代の名和氏一統だった。南朝の敗北によって海賊となり、南下して沖縄本島にわたり、知念半島の一角に上陸。肥後の佐敷にあやかって、その地を佐敷(南城市佐敷)と称した。ここを根拠地にして権力を樹立したのが第一尚氏のはじまりだと折口信夫は説いた。古いグスクである玉城付近の洞窟から日本本土の鎧が見つかったというのは、折口説を補強する材料といえる。
第一尚氏には八幡信仰が熱烈にみられた。さいごの尚徳王が1466年に喜界島を征伐した際、八幡大菩薩の加護をうけたとして安里に八幡宮をたてた。慶長年間、琉球には6カ所の熊野権現と1カ所の八幡大菩薩が祀られていた。為朝伝説は、九州西海岸から渡来したと考えられる第一尚氏の八幡信仰によって定着したと考えられる。
石鍋の次に歴史をうごかしたのは「鉄」だった。
沖縄では、新しい王朝は鉄と関わりのある伝承をもっていた。鉄は輸入するしかない。政治権力をにぎる者は、武器や農具として決定的な意味をもつ鉄器をいちはやく島外から入手することに敏感だった。16世紀半ばごろまで、琉球社会は鉄器類を喉から手が出るほどほしがっていた。鹿児島の坊津や秋目などは、鍛冶技術や鉄製品を南の島々に向けて送りだす拠点だった。秋目の鍛冶屋の大半は奄美の島々で鍛冶屋をしていた。