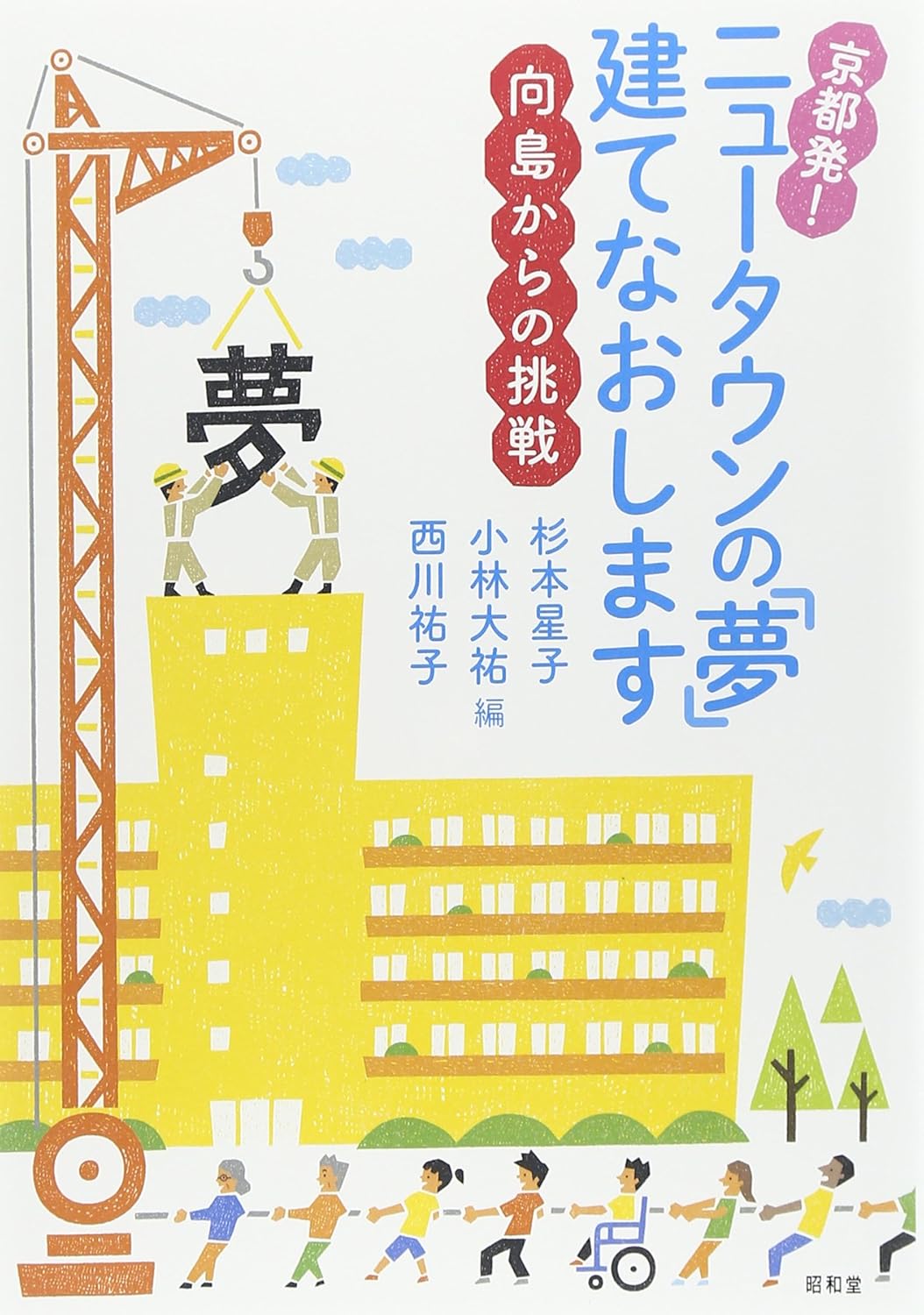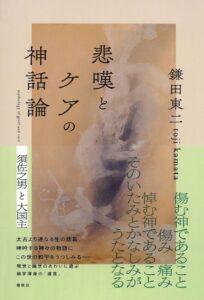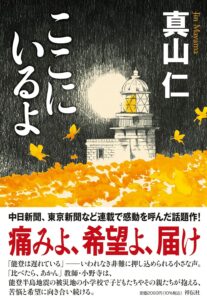2024年6月に亡くなった西川祐子・京都文教大名誉教授の追悼シンポにおじゃました。フランス文学から文化人類学、歴史学、フェミニズムまで幅広い研究を手がけてきた。「ことば」「記録」に徹底的にこだわる人だった。今回は研究者になった3人の教え子が西川さんからなにを学んだかを語った。
ふつうの追悼イベントは第一人者を集めて故人の功績を言祝ぐものだけど、今回の登壇者は無名の教え子研究者たち。そうきたか、と思った。研究者としての魅力だけでなく、教育者としてのすごみも見ることができた。
研究手法を伝授
ひとりめは2003年に大学院に入った佐藤量(広島修道大学人文学部准教授)さん。就職氷河期で「勝ち組・負け組」という言葉に違和感を感じていた。
中国を何度も旅して、中国の学生と自分たちの「戦争」観のちがいに興味を覚えた。西川さんから「あなたにとって、植民地や戦争ってなんなの?」と問われ、「勝ち組・負け組」と植民地の日本人・中国人は構図が似ているのではないかと思い、満州の日本人と中国人の関係をテーマに選んだ。
西川さんは、事細かに研究の進め方を指導した。①文献を読み込んで住所や電話があれば会いに行きなさい。電話をして手紙を書きなさい ②文学を通して社会構造をイメージし、日記、会報、看板、行政資料……あらゆる資料を活用しなさい ③しっかりあいさつし、手土産をもっていき、インタビューを文書におこしたらチェックしてもらい、直しがあったらさらにチェックしてもらう、とくり返すように……。
修士論文は何度も何度もはげしく添削された。
博士課程は立命館に進学し、西川さんの夫の長夫さんに学んだから、西川家にしばしば出入りした。博論は植民地の学校同窓会をテーマにした。女学校も調査した。「あなたはいつもよいテーマを捕まえるのに、それがどんなに重要なテーマかを自覚していないのがもったいない。男子校と女子校同窓会を調べたら、ジェンダー問題をどうしてもっと深めないのかなぁ、もったいない」
何度も何度も「もったいない」と言われたという。
西川さん宅に通うなかで、西川さんの家はさまざまな人が出入りし、「生活と研究が地続き」になっていることを知る。外に開かれた家だった。そういう空間をいろいろな場につくっていきたい……という。
そういう空間は能登の復興の過程にこそ必要だと私は思った。
自分の老いも記録
2人目の中林基子さんは2000年に大学院に入学した。富山の田舎で、祖母の畑仕事や母の家事が、父の稼ぎより下に見られることに疑問を感じていた。バイトの通勤時間が時給に換算されないのもおかしいと思った。労働について関心をもっていたら、「あなたは介護保険でおやりなさい。今年はじまったばかりの制度だから最初からすべて見ていける」と西川さんは言った。ヘルパー2級をとり、ヘルパーステーションで参与観察をする。ヘルパーってやりがいがある仕事だなぁ、と思った一方で、賃金が低くて「女給さん」「お手伝いさん」と呼ばれ、嫁の地位の低さがそのまま反映していた。
ヘルパー兼事務職員として就職後も西川さんはしばしば電話をくれた。「仕事だけど、観察の目を忘れないように」「日々の気持ちを必ず記録に残してね。1日1行でも書きなさい」と何度も言われた。
介護保険スタート当初、ヘルパーは、利用者が買うものを自分でも買って使うことで、その人の食生活や履歴、金銭感覚などを理解しようとした。ヘルパーと家族がいっしょに介護して、いっしょに調理することや、家族から調理を教えてもらうこともあった。
今ケアマネをしているが、「お金を払っているのになぜ、私が教えないといけないの」と言われる。家族にもヘルパーにも、いっしょに料理する余裕がない。利用者「個人」への支援になってきた。
2003年、訪問介護への締めつけがきびしくなる。訪問先に調味料がないことがあるのに「鍋・釜・調味料持参」が禁止された。サービスの標準化、マニュアル化が進み、介護がタスク化していった。ケアマネの仕事は当初「その人にまるごとかかわること」だったが、かかわる範囲がどんどん狭められていった。
こうした変化に気づき、批判的に描けたのも、西川さんの「記録しなさい」という助言があったからなのだ。
「その場でできる研究をしっかりやりなさい」「あなたはそこで生きぬかなければならない」と西川さんは言っていた。
西川さんは「介護をうける準備」と、自ら地域包括支援センターに話を聞きに行き「自分のフィールドワーク」と言っていた。
「あなたは私の言うことを記録しておかないといけない」とも。鎌田東二さんが弟子の三澤さんに「終末期の患者の姿を君に見せたい。きみには最強の臨床実習だ」と語ったのと重なる。西川さんは、自分が老いるということも記録に残そうとしていた。
「怒り」をコトバに
3人目の黒澤祐介(大阪青山大学子ども教育学部准教授)さんは、1998年に学部に入学した。父は高学歴だけどギャンブルで何千万円の借金をつくって離婚。母と姉と3人で生活保護をうけて公営住宅で暮らしてきた。
勉強する気になれず、授業はいつも遅刻する。あてられると「べつにー」「どーでもいい」。西川さんは「私はあなたのお母さんじゃない、おばあちゃんじゃない」と怒った。そして、「あなたがなぜそんな態度をするのか知りたい」「あなたの言葉には重みがある。修羅場を経験している」と言った。
「なぜ研究しているんですか」と問うと「私は自分が何にだまされて生きてきたのか知りたい」と答えた。
西川ゼミは当時、向島ニュータウンを研究していたが、障がい者が多いのに向島駅にはエレベーターがなく、障がい者団体は、エレベーター設置を要求していた。「研究するくらいなら、大学の先生がエレベーターをつけろと言ってくれ」と黒澤さんは怒り、低所得者の公営住宅と公団(UR)を「ニュータウン」でくくることに「いっしょにするな!」と怒りをぶちまけた。
そんなルサンチマンのような怒りを、西川さんの指導で言語化して研究の原動力にしていった。
大学の役割は「記録」
杉本星子・名誉教授は同僚として西川さんと接してきた。
大学は「学ぶ場」であり「教える場」ではない。大学教員は、教師である前に「研究者」だ。研究者とは 「自分が知らないことがあることを知っている人」である。
「大学が地域のなかでできることは、地域の人がやっていることをしっかり見て記録すること」と西川さんは位置づけていた。渦中の人には記録はできない。あとになって記録は役立つ。そして成果は「出版」しなければならないと考えていた。
市民が怖い
ほかにも印象深い言葉は多かった。
「相手の話を聴くことは一生をかかえこむことだ。その後も関係性をつづけていくこと」
社会学で脚光を浴びている「生活史」について「なんで「誌」じゃないの?」と言った。国民の歴史、男性の歴史に対峙するものをつくるべきなのに……と。
「市民が怖い。研究者は生活の感度が弱すぎる」