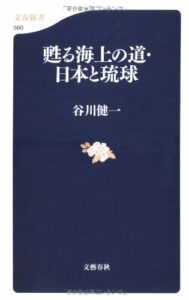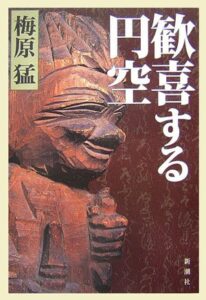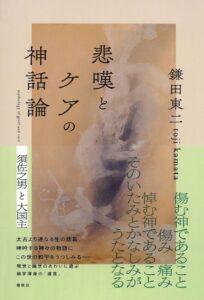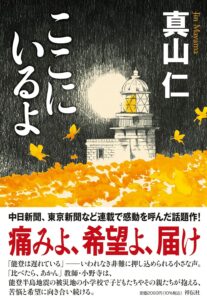舟のルーツをさぐるとロマンがいっぱい。老若男女が楽しめる展示だった。
原初の舟は、①筏とあし舟 ②皮舟ないし獣皮舟 ③樹皮舟 ④くり舟・丸木舟があった。(チベットの牛皮舟)




台湾から与那国島まで黒潮を横切っての225キロをわたったのは、そのいずれだったのか。その実験がおもしろい。
草葦舟と竹筏舟は安定感は抜群だったが、黒潮をこえる機動力や耐久力に難があって失敗した。丸木舟は速度は速いが浮力が強すぎて不安定という特徴がある。少しずつ改良し、操船技術を向上させることで、45時間で225キロの渡航に成功した(2019年)。

ホモサピエンス最初の遠洋航海は5万年前の旧石器時代、サフル大陸(オーストラリアのニューギニア)への渡航で、筏だったと考えられるらしい。

丸木舟に竪板と舷側板を継ぎ足すと準構造船になる。日本の弥生時代や古墳時代の埴輪からその構造がわかる。

北洋のベーリング海峡をわたったのはカヌーだった。白樺樹皮やアザラシの皮がつかわれている。

南洋圏のメラネシアや東南アジアの島世界では旧石器時代から筏や舟がつかわれていた。舟を安定させるアウトリガーは、風上にむけて重りの役割をはたした。アウトリガー部分に小さな屋根をつけて休息スペースにする工夫も。

1975年の沖縄海洋博では、ミクロネシアのサタワル島から沖縄まで3000キロを40日かけて航海した。その映像も、古代人の冒険の様子がわかってわくわくする。

マレーシアのの家舟もおもしろいが、できれば瀬戸内海や九州の家舟と比較してほしかった。
茂在寅男はカヌーというコトバは欧州起源ではなく、太平洋にあった言葉であり、伊豆の狩野川のカノなども同根であると説いていた。あまりにも話が大きすぎて真偽不明だが、彼の説が現在どう位置づけられているのか知りたい。
舟とあの世とのつながりや、舟の形をした棺なども興味深いが、補陀落渡海の舟にもふれてほしかった。
カツオ釣り用の手こぎカヌー、台湾のタタラ、クラ交易につかわれたパプアニューギニアのクラカヌーなども興味深い。

佐渡島のたらい舟は磯でサザエやアワビをとるためにつかわれるが、洗濯桶を改良して誕生した、という出自がおもしろい。沖縄のサバニはもとは丸木舟だったが、1880年代に糸満で漁業用に特化され、それが大型化して、複数の材木をつぎあわせる「ハギンニ(接ぎ舟)に変化した。(1737年に琉球王府が山林保護のために大木の伐採を禁止したことで、小さな木材を組み合わせて造る「ハギンニ」が発展した、という説も)
島根県の中海ではアカガイなどをとる「きりこ舟」が1950〜60年代まであった、というのもはじめて知った。展示されている舟は1980年に大根島で収集されたという。

米軍機のジュラルミン製補助燃料タンクからつくった沖縄の「タンク舟」にもびっくりした。