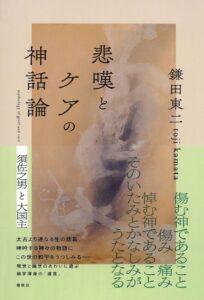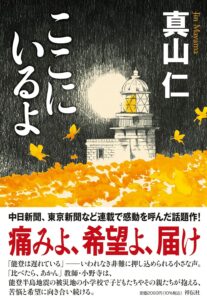神戸学院大の安富信さんの「ボランティアを考える」という講演は痛快だった。能登半島地震におけるボランティアのあり方について感じたモヤモヤしたものがいったいなんだったのか。霧を吹き飛ばすように解説してくれた。あと、メモを一切見ないで芸人のように語りつづけるのは芸人みたいだった。
以下、備忘録。
地震から40日後の2024年2月に現地を訪ねた際、大規模な被災地なのにボランティアの姿はまばらでシーンと静まりかえっていた。輪島市中心のその日の公式ボランティアは金沢からの40人。しかも昼前に到着して午後3時ごろには引きあげてしまう。
どれだけボランティアが少なかったか。
阪神淡路大震災では最初の3カ月で100万人のボランティアが入った。東日本大震災は、はるかに広大な被災だったのに50万人。当初「ボランティア自粛」が叫ばれたことが影響した。熊本地震は10万人。能登は……3カ月時点でわずか1万2500人。石川県は地震から4カ月後も「ボランティア自粛」を呼びかけつづけていた。
阪神淡路大震災はボランティア元年といわれ、NPOやNGOが誕生してボランティアが根づくと思われた。
ところが東日本大震災は「自粛して」「自己責任で」と呼びかけれ、「ボランティアがいくと迷惑がかかる」論がはびこった。
また、避難所での性暴力や盗難はごくまれな事件でしかなかったのに、過大にあつかわれ、「ボランティアをコントロールしなければ」という発想が生じ、ボランティア登録制度がつくられた。
市町村の社協が設けるボランティアセンターがボランティアのマッチングをする制度がつくられたが、社協は福祉が専門で、小規模なら対応できても大規模災害ではスタッフも被災してセンター運営は困難になる。
能登はさらにひどかった。市町村単位ではなく石川県が、ボランティア希望者を登録して各地域にふりわける形になった。県に窓口を一本化する「石川方式」によって、ますますボランティアが現地に入りしにくくなった。
能登の避難所をボランティアが訪ねたら市役所の職員から「許可をもらってるのか」と言われた例も。避難所を行政がしきると、人が足りないから手が回らない。なのにヨソモノを排除する。ふだんから地域コミュニティを自分たちで運営し、避難所も当事者が運営し、ボランティアが手伝う形にしなければならない。
「無償の行為」「ボランティアは立派、えらい」というボランティア観が日本にボランティアが根づくのを阻んでいる。
交通費も宿泊費もかかるのに「無償」ではカネのない学生は参加できない。
ボランティアは「立派でえらい」行為ではなく、支援をする側もうける側も「お互い様」という気持ちが大切。
「とりあえず現地に行って、ニーズがなければ何もせずに帰ってくればいい。押しつけなければよい」
「能登に泊まってカネを落とすだけでもよい。ボランティアは行ってボーッとしとるだけでもええんやで」
能登にも、公には認められていないボランティアが「ひそかにしなやかに」入っていた。コントロールされたボランティアではなく、そういう原点を大切にしなければならない。