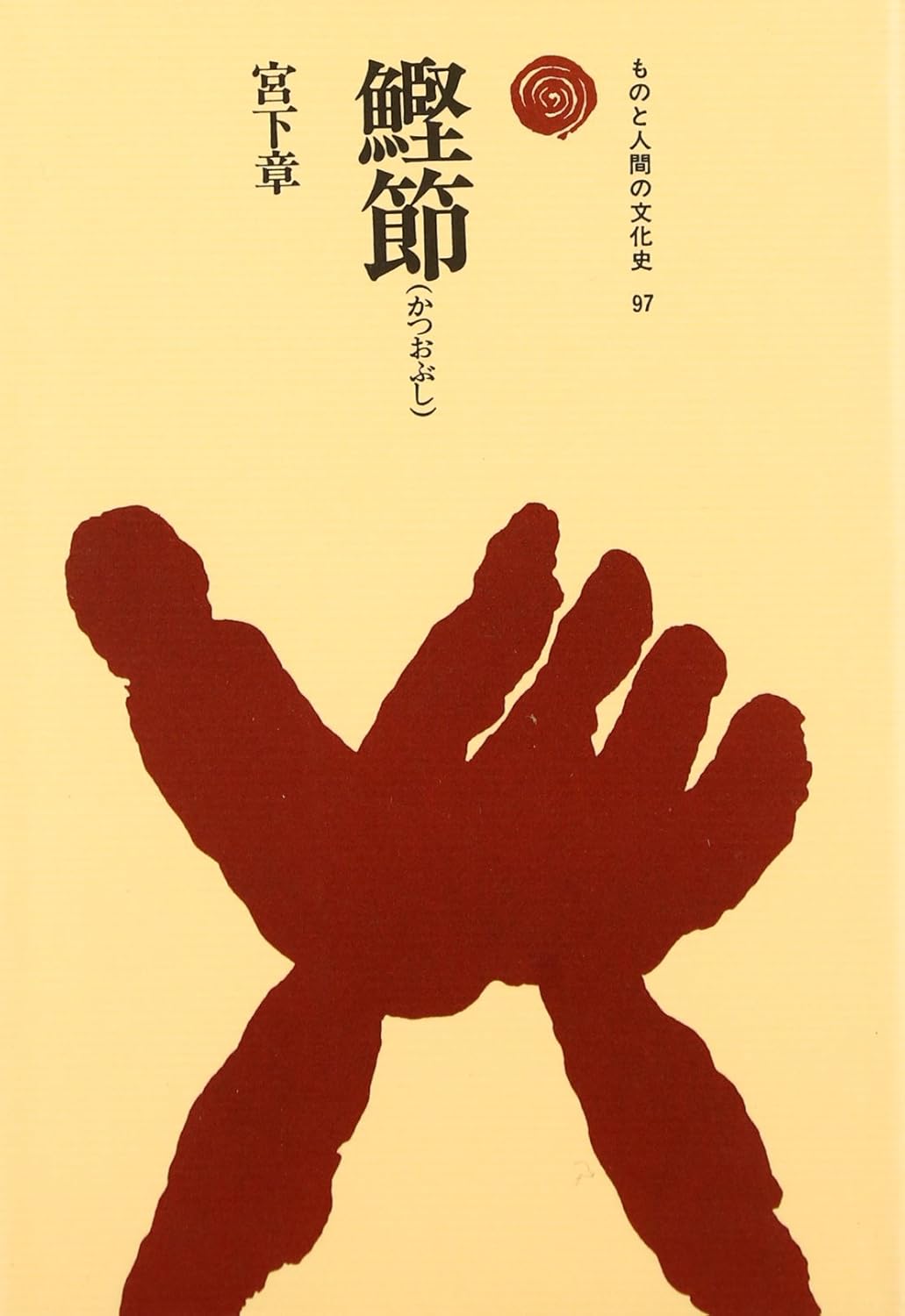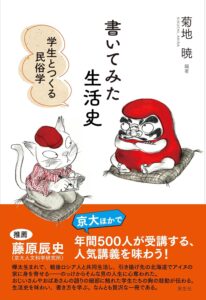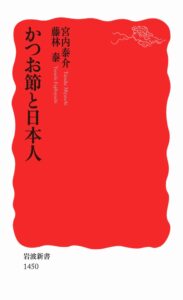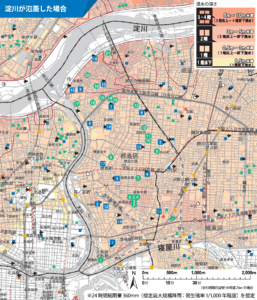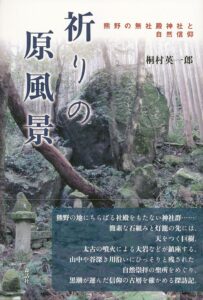■法政大学出版局250826
鰹節のすべてがわかる本。映画監督の大重潤一郞はおそらくこの本を読んだのだろう。
縄文時代からカツオを食べ、奈良・平安以前には「堅魚(かつお)」と書かれる製品が、伊豆、土佐、紀伊などから朝廷へ貢納されていた。これらは単なるカツオの素干しだった。本来の「鰹節」の最古の記録は、室町末期の「種ケ島家譜」の1513年の1項に書かれた「かつほぶし」だった。
堅魚と鰹節はなにがちがうのか。
鰹節の製造は、①生切り ②煮熟 ③焙(燻)乾④削り ⑤カビ付け、という段階を踏む。
古代の堅魚(かつお)は、生切り後、天日で乾かしたもの。「煮堅魚」は、生切りして煮たあとに乾したものだ。
室町末期に登場する鰹節は③の工程を経たものだ。
①生切りと②煮熟のあと、2回程度焙乾・燻乾し、水分が多くやわらかい食べる鰹節を「若節」という。8回程度焙乾をくり返し、削って花鰹としても使われるものが「荒節」。荒節の表皮を削ると「裸節」となり、西日本ではこのまま食用とすることが多い。
さらに焙乾したうえで青カビをつけ、悪カビ付着を防いだものが「上枯節」「一番枯節」。これに4,5番カビまでつけて堅固に仕上げたものを「本枯節」「仕上節」と呼ぶ。カビをつけるのは、カビが節内の脂肪、水分を吸い出し、かたくて香味豊かな製品にできるからだ。
本枯節が完成品と位置づけられているが、西日本の産地は明治までは裸節をつくっていた。削り節が主流になった今でも、東日本ではカビ付けした鰹節・雑節が好まれ、西日本では裸節や荒節段階の鰹節・雑節が好まれている。東西で鰹節の定義が異なるのだ。
③の段階を踏んだ鰹節が広範に普及している国は、日本以外にはインド洋のモルジブしかない。モルジブでは総漁獲高の7割をカツオが占め、カツオの存在感は日本を凌駕する。鰹節の歴史も、日本では16世紀初頭が最初の記録だが、モルジブではその150年以上前にインドや中国へ輸出していた。
カツオをとる漁法も、煮沸して煙でいぶし日干しにする……という「荒節」までの工程も日本とモルジブで共通している。ただ、モルジブの鰹節はこれで完成だが、日本では表面のざらついた部分を削って一次製品(黒節、裸節)とし、その上でカビ付けをして2次製品(本枯節)とする。
温帯の日本ではとれすぎた魚は塩干魚にして保存する。サケや川魚を焙乾する例はアイヌなどにあった。だが、燻乾法はなかった。
熱帯では、じかに天日乾燥をすると虫に食われウジが発生してしまう。東南アジアでは虫の駆除方法として、魚類の焙乾・燻乾が発展した。燻乾小屋は、蝿や蚊が近づかず、食物の保存所にもなった。
日本では、南西諸島のエラブウナギは燻乾法で加工される。また南西諸島には、イロリの真上にセイロウを釣るし、魚類を入れ、燻乾を目的とする保存法があった。イロリの上の燻乾用のセイロウは、フィリピンにも見られる。燻乾法は南方から学んだ可能性が高い。日本最古の「かつほぶし」の文字が南西諸島の文書であることからも、鰹節は南方から伝来したと考えられる。
ただ、鰹節は東南アジアには存在せず、日本とインド洋のモルジブにしかない。つながりがあったのだろうか?
モルジブは1153年、仏教からイスラム教に転換した。200年後の14世紀にはマラッカ王国、15世紀にはインドネシアがイスラム教に改宗し、モルジブ王国と関係が深まり、モルジブ、マラッカを中継してアラブと中国がつながる「海のシルクロード」貿易が盛んになった。
一方、琉球王国は14,5世紀から、明国に供与された200人乗りの大船約30艘を駆使して、安南、シャム、マラッカ、インドネシアなどと交易をした。モルジブからマラッカに鰹節が輸出され、その地で琉球王国人が鰹節を知った可能性は否定できない。事実、モルジブの鰹節は「溜魚」の名で中国に輸出されていた。そして燻・焙乾食品に無縁だった日本に「大航海時代」後の15世紀ごろから鰹節が忽然と出現したのだった。
琉球王国の交易を支えたのは久髙海人だった。久高島には、風葬や略奪婚などの風習があり、南方系海洋民であった可能性が高い。
奄美方面では、沖縄から来て海上交通や漁業に従事する船を「クダカー」と呼んだ。
江戸中期と後期、琉球へきた清の冊封使2人が、報告記で鰹節について「久高島の産」と書いた。その背後には、薩摩藩が清国を刺激しないよう、独立国の琉球王国を前面におしだす意図があった。大坂や富山で仕入れた昆布も冊封使の記録には「久髙島で採れる」と記された。
久高島のエラブウナギ(イラブー)を加工する技術は、鰹節づくりと酷似している。しかもその上質なものは、切り口から鰹節と同じ芳香が漂う。
エラブウナギは、口永良部島などに多数生息するから久髙漁民が出漁した。この島の周辺はカツオの大漁場でもあった。久髙海人がカツオの燻乾技術を指導し、販売に寄与したと考えられるという。
熊野の漁師が全国の最先端の技術をもち、出稼ぎによって、鰹節だけでなあく様々な漁法を青森から九州にまで伝えた、という話もおもしろい。全国どこでも「熊野の漁師が伝えた」という言い伝えがあるという。