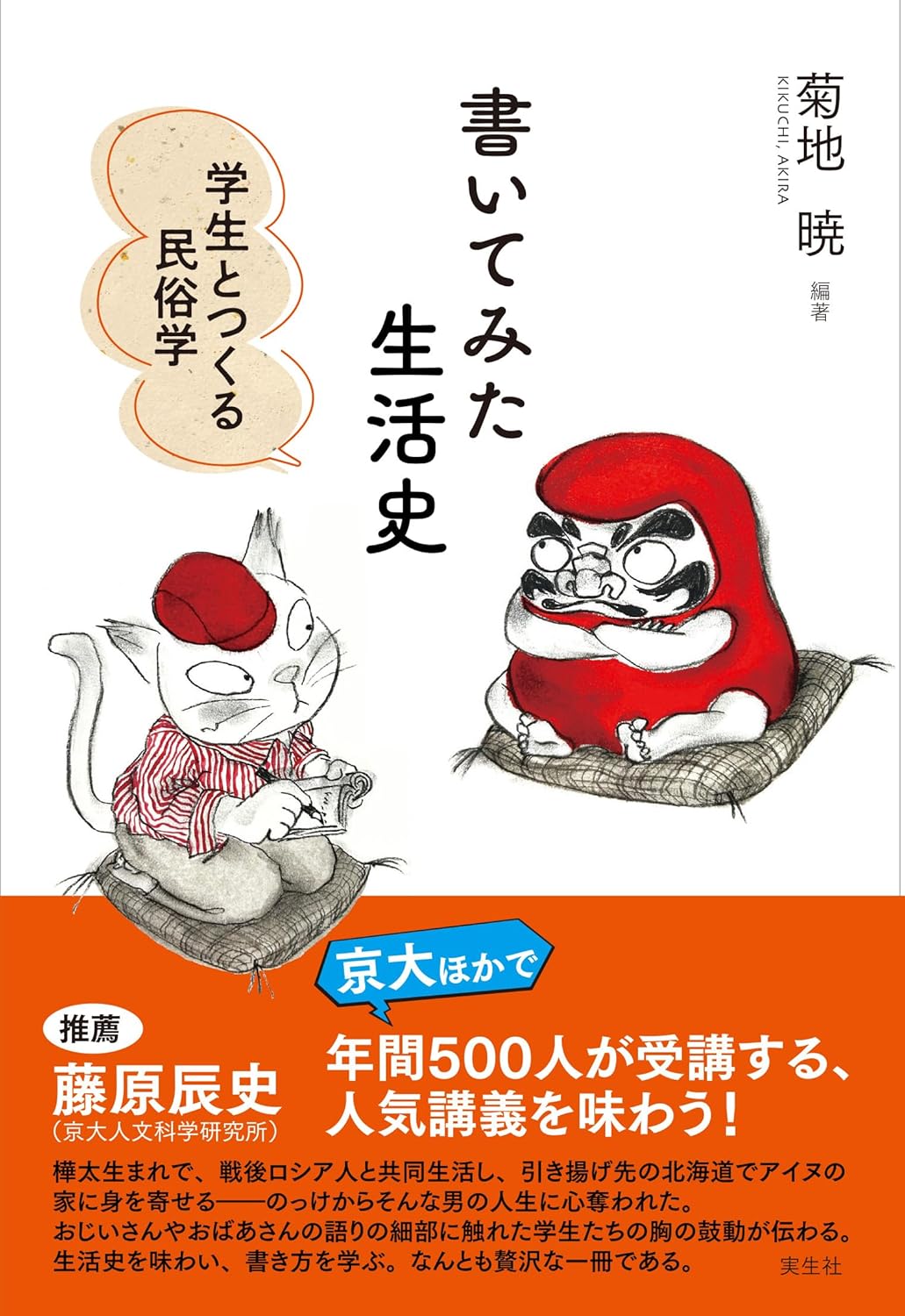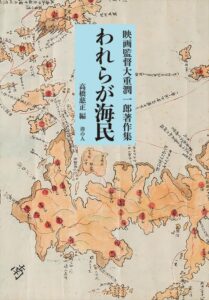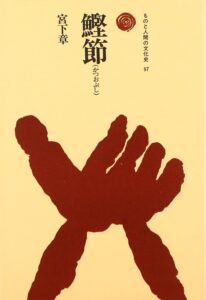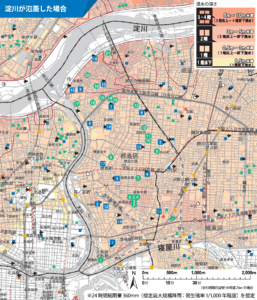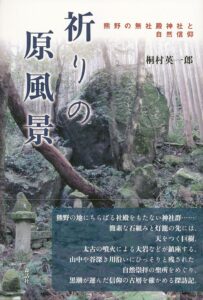■実生社250801
大阪市立大と京大と龍谷大の「民俗学」の講義で、「受講生の祖父母を話者として生活史を聞き書きする」という課題を学生に課してきた。計5000本のレポートから12本を選んだ。
学生の文章が想像以上におもしろいことに驚いた。編者が添削したのだろうが、そもそも一定以上の観察に基づく素材がなければ、添削してもおもしろくなりようがない。
あと、聞き書きは素のままが一番おもしろくて、聞き手が解釈して抽象化すると陳腐になりがちだが、優秀作品だけあって、いきすぎた「解釈」「抽象化」がなかった。
聞き書きの真骨頂は、文書化されていない経験の豊かさにある。たとえば……
樺太で裕福な暮らしをしていた男性話者は、敗戦直後、ロシア人と共同生活をした。ソ連兵といえば、シベリア抑留などの悪辣なイメージが強いが、ともに暮らした人たちは人なつこくて、ソ連兵の兵舎に子どもが遊びに行くと喜んでくれた。「この共同生活が人生85年で一番楽しい時代」と話者は言う。北海道に引揚げ後は家が見つからず、アイヌの伝統家屋チセにも暮らした。その後、国鉄でSLを運転し、1969年には最初の電車運転士となった。
東大卒業後すぐに寺院に嫁いだ女性は、檀家とのつきあいで忙殺され、長男が成人するまで、買い物以外で寺から出たのは父母が亡くなった時だけだった。寺は死と直面する場だ。遺族の悲しみによりそうことで自分を成長させてきたという。
「運命に抗おうとがんばってもしょうがない。それでも、自分がやるべきと思うことを自分なりに考えて誠実にしていったら、死ぬときになって、『あなたはちゃとしてきたでしょ。だからこれでいい』と思えるのです。そう思えたら、今までの悪いことは全部帳消しになって、心穏やかに死んでいけるんですよ」
幸せになる必要はない。つらいことだらけの人生でも「生きる意味」を見いだせる。フランクルの思想のような高みに達している。
太地町の漁師の男性は中学を卒業して、ゴンドウクジラの追い込み漁に携わり、次はミンククジラ漁、さらには大型捕鯨船で極地の海にでかけた。その後、捕鯨船をおりて自分の漁船をつくった。木製の船ばかりの時代にFRPの船をいちはやく導入した。その速度にみんなが驚き、太地の漁船は一気にFRP化した。先取の気性と行動力にあふれた漁師だった。レポートを書いた学生は祖父が亡くなる2日前にレポートを届けた。母が読み聞かせると顔をクシャクシャにして喜んだという。記録することで、自分や家族の人生の価値を認識できる。「生活綴り方」と共通する生活史(記録や表現)の可能性を示している。
女遊びが大好きなじいさんの娘だった話者は、ばあちゃんにつれられて遊郭に祖父をつれもどしに行った。「あるときなんか、じいさんとキラキラべっぴんが七輪はさんでお肉食べよってな、小春ばあさんがその七輪蹴り飛ばしたのはよう覚えとらぁ」
やがて結婚し、夫は木材会社を成功させて裕福な暮らしになったが没落する。あるとき話者は「子どもに恵まれて、家に帰っても息子夫婦や孫がおって、仕事の時も娘と孫がおって、ホンマに幸せじゃなあ」と言われた。するとぼろぼろ泣いて、「私もほんまにそう思うんじゃって、ずっと気づかずにおったけど最近わかってきたんじゃって……毎日起きたときと寝る前に神さまに感謝しょうるいうて……」
この話もまた「幸せ」のあり方を考えさせてくれる。
高知県・宿毛には、平家の落人が土着の人に密告されてほとんどが殺されたという伝承がある。その経緯から宿毛では平家を下(しも)、土着の人を上(かみ)と呼んでお互いを区別し、下の子孫は密告されたことを恨んで上の子孫と結婚させなかった。現在でも、ふだんのつきあいはあるものの、婚姻関係は結ばない。家のすぐ近くの丘の上には、密告されて殺された平家の落人が祭られたオクボサンという石碑がある。伝承と現代生活が混ざり合っている様子がおもしろい。
この話をした女性は、「戦時中も自給自足がなりたっていたから、配給はもらう必要はなかった。もらったのは自分たちでつくれない砂糖ぐらい」と語った。ただ、雑穀も食べなさいというお触れがでていて学校に白米の弁当を持っていったら先生に没収された。話者は麦が嫌いだったから薄く切った芋を白米の上にのせて白米を隠しながら食べていた。こういう話も聞き書きをしなければ採集できない。
台湾の医師の息子で産婦人科医の男性は、大陸から移ってきた蒋介石ら外省人と台湾生まれの本省人の関係について語った。
戦後、授業は中国語にになり、外省人の先生ばかりになり、1、2年後には日本語が禁止された。1947年に2.28事件が起きて、国民党政権は戒厳令をしいた。日本統治時代にはなかった差別を外省人からうけ、本省人の子が級長になるのを先生はいやがった。話者は日本に脱出した。
能登半島の珠洲の女性は、浄土真宗の寺の、市役所職員の男性と結婚した。その家では農耕儀礼の「あえのこと」をやっていた。原発計画がもちあがって、夫は市役所職員だから推進側。実家は原発計画地の近くだから反対派が多かった。
伏見稲荷前の神具店に生まれた女性によると、観光客は2015年ごろから、千本鳥居がSNSで話題になることで爆発的に増加し、毎日が正月のようなにぎわいになった。食べ歩きをしながら店に入ってくる人も増え、「ここで食べんといて」と注意するのが日常になった。こうした街の変化も住民の話を聴かなければ埋もれてしまう。
本の後半に掲載された「生活史」と柳田民俗学のかかわりについての編者の文章は、私が感じる民俗学の「しんきくささ」の原因を解明してくれた。逆にどうすれば現代に生かせるかのヒントも示していて刺激的だった。
柳田「遠野物語」(1910)は日本的私小説である田山花袋の「布団」への批判をこめて書かれた。
序文の「願はくは之を語りて平地人を戦慄せしめよ」というのは、外国文学にかぶれ、日本の現実を顧みず、内面描写にばかり明け暮れる自然主義文学者たちを挑発したものだった。
自らの「内面」を赤裸々に描いた花袋が私小説の創始者だとしたら、異類異形をも含みこんだ重層的な「風景」こそが課題だと考えた柳田は、遠野という共同体の共同幻想を描き出そうとした点において「公小説」の創始者だった。
民俗学とは「普通の人々」の「普通の暮らし」の変遷を研究する学問だ。そのためには、識字層という「特別な人々」が残した文字資料だけでなく、「普通の暮らし」を研究する。
その対象は「有形文化」、「言語芸術」(言葉を解するものが最採集できる)、「心意現象」(見えも聞こえもしない内面の出来事なので当事者本人が採集するしかない)であり、とりわけ「心意現象」を観察するため当事者自身を研究に動員した。
ところが、その集まりは、「対話」の場ではなく、話者が柳田の「師説」を拝聴して自らの情報を提供する、一方通行の場になってしまった。柳田に資料提供する全国の民俗学徒は「無名戦士」と化し、柳田ただ一人が膨大な著作を残すことになった。
宮本常一の「忘れられた日本人」以降、無味乾燥な項目羅列へのアンチテーゼ、生活世界への回帰の旗印として、生活史アプローチが実践されるようになるが、柳田民俗学が生活史に直線的につながったのではなく、生活綴り方などの戦後文化運動などとの接点が必要だったという。
現在の大学生は観察力、記述力、歴史意識がいちじるしく劣化している。
自らの生活体験を客観化し、他者と比較する視座を獲得する。祖父母の生活史を媒介に、大文字の「歴史」が自己と無縁でないと確認する……。生活レポートは、生活世界に根ざした観察力、記述力、総合力を涵養することになり、「広義のリテラシー教育」となりうるという。
柳田民俗学は、「伝承(のようなもの)」と「それ以外」とを峻別し、前者だけを研究対象とした。だが、伝承もモダンの影響をうけている。「伝承という本質」だけを対象としては現実と向き合うことができない。
「北海道に民俗はないので民俗学は無理」という主流派学者の発言の背景には「民俗がある/ない」を単純に峻別できるとする本質主義的な「民俗」観がある。そのような「民俗」観は、純粋な「民俗」を求めて「近代」や「外部」を排除してしまう。その結果、民俗学は人々のリアリティから切り離され、しんきくさくなり、現実と切り結べなくなってきた。
ではどうするか。両者をわけるのではなく、「大きな網」によって、生活者の身体に刻み込まれ、暮らしの中で実践される言い伝えやしきたりの総体をとらえる。そのために生活史というアプローチにたどりついたという。
生活史は、個々バラバラな人々の人生の断片だが、その断片が、私たちが対峙する世界の解像度を高めてくれる。理解しているつもりだけど本当は理解できていないことが膨大にあることを教えてくれる。それは、この世界に必要なはずの多様性への寛容や忍耐といったものを、少しずつ育んでくれるはず……と、編者は期待している。