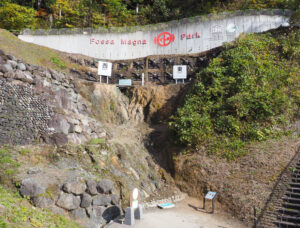芭蕉布を復活させたムラと岡本太郎が紹介し、長寿村としても知られる大宜味村・喜如嘉(きじょか)集落を2022年3月に訪ねた。名護市から30分ほど海沿いに北上した「道の駅おおぎみ」は「やんばるの森」のビジターセンターを併設している。地元の野菜や果物が豊富で楽しい。中南米原産のアマランサスの葉を売っているのには驚いた。
妖怪は平和のシンボル

大宜味村役場の隣には1925(大正14)年に竣工した旧庁舎が残っている。沖縄最古の鉄筋コンクリート建造物だという。台風の風圧を軽減するため八角形の平面にしたらしい。
「ぶながやの里宣言」という碑がおもしろい。
……「ぶながや」は、平和と自然を愛し、森や川の恵みを巧に利用し、時折私たちにその姿を見せてくれる不思議な生き物である。
第2次世界大戦以前は、沖縄のほとんどの村々で暮らしていた「ぶながや」たちは、激しい戦禍と基地被害、戦後復興の近代化に耐えきれず、かつてのふるさとを離れ、20世紀最後の安住の地を求めて、豊かな自然と人々の肝清らさにひかれ、大宜見村に命を永らえるようになったという、希少種族である……(1998年)
「ぶながや」は精霊あるいは妖怪だ。妖怪は平和でなければ活躍できない。精霊と妖怪が消えたあとに戦争や拝金主義が蔓延するともいえる。
近くには「日本国憲法第9条の碑」や、戦争で亡くなった村民の名が刻まれた「霊魂の塔」がある。生と死の境を超えて飛びまわる「ぶながや」は、憲法9条とともに平和のシンボルなのだ。
昔は田んぼがあった
芭蕉布の原料となる糸芭蕉の畑が、戦後、マラリア対策として米軍に伐採されつくされ、芭蕉布は消滅の危機に瀕した。喜如嘉出身の平敏子さんが糸芭蕉を育て、糸をつくり、染め、織りまで再興させた。平さんは人間国宝となった。後継者も育て、私が喜如嘉を訪ねた半年後の2022年9月に101歳で亡くなった。
そんな歴史を展示しているはずの芭蕉布会館は残念ながら休館だった。

会館の駐車場の目の前に古民家があり、「展示館」と書いてある。おばあさんがひとり、芭蕉の繊維で帽子をつくっている。もとは夫婦で登り窯と穴窯で焼き物をつくっていたが、夫が21年末に急逝した。「女ひとりでは焼き物は無理だから、芭蕉でいろいろつくっているんです」

集落を散策した。
共同店があるが日曜は休み。店のわきの鳥居をくぐり石段をのぼると、芝生の小さな広場があり、祠がもうけられている。集落と海を一望できる。
山に囲まれて水が豊富だということがわかる。昔は稲作をしていたのだろう。古い民家があちこちに残っている。戦争でも破壊されなかったようだ。

「オクラレルカ」(送られるか)という冗談のような名前の花が咲いていると聞いていた。
「どこに咲いてますか」とおばさんに尋ねると、
「むこうの田んぼですよ」
「田んぼ」があるんだ。

紫の花びらに黄色い彩りのあるアヤメのような花がチラホラ咲いている。
「県内できわめて少なくなった水田(ターブク)のひとつ……昔は米やイグサをつくっていたが、今は,オクラレルカを生け花用に出荷している」と案内板に記されている。
戦後しばらくはサツマイモと水稲が主体だった。その後、熊本県の八代から風や病害に強いイグサの苗を導入した。イグサは、特定の人たちがつくり、一般の人は養豚・養鶏・薪炭で現金を稼いだ。大宜見村は1956(昭和31)年、換金作物のパイナップルを導入する。パインブームにつづいてサトウキビブームが到来した。大宜味村のサトウキビのピークは1965(昭和40)年で、78年には半減したが、喜如嘉はこの年、面積・生産量ともに最高を記録した。国の減反政策によって水稲がイグサとサトウキビに転換されたためだった。サトウキビとイグサが衰退すると、オクラレルカなどの花卉や水芋、野菜(インゲン、キャベツなど)が主流になったという。

女性の運動で火葬場を整備
1996年に「喜如嘉誌」という本を刊行している。分厚い「集落誌」の存在は文化レベルの高さや住民の団結力をしめしている。
戦前、喜如嘉は教育熱心で民衆運動が盛んだったが弾圧によって皇民化した。「県下一の翼賛部落」と評され、県内で最初の国防婦人会が結成された。
共同風呂、共同救急箱、共同学習所、家畜の共同購入。共同結婚式……を実践した。共同結婚式によって、4〜500円かかった結婚式の費用が30円ですむようになり、節約運動の手本とされた。戦後は、革新政党の組織が喜如嘉で誕生して全県に広がった。
沖縄や奄美では、土葬した遺骨を数年後に洗い清めて甕におさめて埋葬する「洗骨(せんこつ)」という風習がつづいてきた。その作業は故人の肉親の女性、とくに長男の嫁が担うことが多く、女性にとって過酷な儀式だった。
喜如嘉の女性たちは戦前から火葬場設置をもとめる運動を展開し、1951年に実現した。葬儀にともなう費用は、埋葬(洗骨)は6940円だったが、火葬は440円ですむようになった(1954年)。
婦人会長だった大山幸さんは1964年の公民館発表会で次のように語った。
「愛する肉親がひとたび他界したあとは、あのいとしいなつかしい面影をいつまでも心に描き、胸に浮かべてひたすらその冥福を祈っておりますのに、1カ年後に来るあの洗骨といういやな行事、亡き肉親の蝕まれた見苦しい姿を思い起こしますとき、むしろぞっと致します。この非人間的非衛生的な洗骨を、しかも婦人が行わなければならない理由がいったいどこにあるのでしょうか。私たちは婦人としての立場からまた、子々孫々のためにもひいては文化生活のためにも洗骨を徹底的に排除しなければならない責任と義務をひしひしと感じたのでございます」
洗骨をはじめ、伝統的行事を最近まで堅持してきた久高島とはある意味で正反対だが、どちらも沖縄の魅力を体現していると私には思える。
小学校跡に新名所

友人のビデオ・ジャーナリストの中井信介さんが大宜味村に移住した。2025年7月、喜如嘉翔学校(旧喜如嘉小学校)にある彼の事務所を訪ねた。
鉄筋コンクリートの立派な校舎には、サウナや書店、ハンモック工房、陶芸・木工工房、芭蕉布工房などが入居している。中井さんの「てわたしプレス」もその一室にある。大きな扇風機と簡易ベッドと、映像編集用のパソコンをそなえ、月に一度はここで、彼が制作してきた映像作品の上映会を開いている。

目の前の畑では、オクラやナス、キュウリなどを無農薬で栽培して直売している。
校舎の上の図書館だった建物にある「山原工藝店」は、地元アーティストの作品がならび、カフェも併設している。7月中には宿泊施設BUNAGAYAもオープンするという。

元気で魅力あるムラには魅力ある人々が吸い寄せられる。喜如嘉の人々は今後も新たな魅力を生みだしていくのだろう。