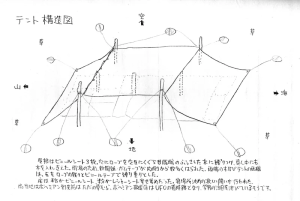実践ゼロの恋愛至上主義
中学1年で畑正憲の「ムツゴロウの青春記」をよんでから、恋愛小説をかたっぱしから手にした。愛する人といっしょなら、家出をしてどこか遠い町でくらしてもよい。愛さえあれば、どんな苦労ものりこえられる--。アルバイトの経験もないのにそうおもいこんでいた。
高校2年の秋、女子校の文化祭のフォークダンスでであった子にひとめぼれして、長い手紙をおくって撃沈した。
それ以来、「彼女がほしい」とおもいながらも、具体的な対象はいなかった。大学2回生に進級する春休み、中国の南の端の雲南省シーサンパンナで羅遠芳ちゃんと遭遇して久々にドキドキ感をあじわった。
1986年4月。新入生歓迎の大文字キャンプにはじまり、新入生獲得だけでなく自分たちのであいをもとめて、「バーベキュー・ハイキング」や合コンを企画する。参加者をつのるため京都女子大や仏教大前でチラシを配布して声をかける。
そんなこんなで実現した合コンで、オクダさんという子に目をうばわれた。
すらっとしていて、上品で、おっとりした声がやさしい。彼女たちのグループとは複数回「ひらパー」(ひらかたパーク)であそんだり、合コンをしたりした。
6月末、百万遍を自転車でとおりがかると、女の子の笑い声がした。ふりむいたら京女(キョウジョ=京都女子大)の女子寮の3人だった。
「なんでこんなところに?」
「バイトをさがしにきたんです」
ひとことふたことかわすあいだに206系統の市バスがきて、あっさりサヨナラ。オクダさんのかわいさにまいってしまって、ぜったいこの子しかいない! と決意した。

魅力にクラクラ、会話つづかず失速
1週間後の7月6日、3回目の合コンにでかけた。幹事役をしたタケダがさりげなくオクダさんの隣の席をあけてくれた。タケダは腎臓病になってから、人の気持ちをこわいぐらいにくみとってくれる。サバイバルを脱走してひらきなおった図々しいヤツと同一人物とはおもえない。つらいおもいをすると、人間ってやさしくなるのかなあ、なんて感謝したのは数分で、すぐにオクダさんとの会話に夢中になる。
彼女もジャーナリスト志望だったとか、中国文学や漢詩が好きで中国へいきたいとか、文学では中島敦や太宰治が好きとか……
「毎晩のように悪いヤツをやっつける夢をみるんです」
「酔っぱらってなぜか腹がたってトイレでペーパーをなげつづけちゃいました。アハハ」
上品でおとなしい語り口と、その正義感のつよさと行動のはげしさとのギャップ。ぼくも水俣病などの社会問題に興味をもっていたからなおさらひかれた。
舞いあがってフィリピン旅行の話などをペラペラしゃべった。とりあえずちゃんと会話になっている。「話題カード」だのみだった1年前のオレとはちがう!
だが1時間もすると話題がつきた。不自然な間ができるようになると、彼女はななめをむき、シオモトの話に耳をかたむけ、セージの話にわらい……。こちらをむいてほしくて新しい話をひねりだすと、応答はするものの、すぐに視線をはずしてしまう……。
場をもりあげられるセージやシオモトがうらやましい。
前半の高揚がうそのように自信を喪失していった。
コンパがおわり、彼女らがタクシーにのったとき手をふったが、ふりむいてはくれなかった。
「中身がないから会話ができないんや」と指摘されて1年、それなりに「中身」をつくったつもりだけど、やっぱりダメだった。
大学のノートに大量の手紙の下書き

翌々日の早朝、2日間ほとんど一睡もしないまま比叡山にのぼった。
人のいない、眺望のよい広場で横たわり、ウグイスのすんだ声をききながら昼寝をすると心がおちついて気力がわいてきた。
「ダメでもともと。今日こそは電話する!」
ひらきなおったせいか、うまくいくような気がしてきた。
山をおりて古書店で「会話術」という本をかってシオモトの下宿でよんで準備した。
その夜はボヘミアンの例会だった。
「いまから電話するわ」
例会がはじまる直前に宣言して、シオモトにつきあってもらって公衆電話にでかけた。
京女の寮のダイヤルをまわす。「217号室のオクダさんおねがいします」
とりつぎの時間がやけにながい、ということは留守ではないということだ。3分ほどして彼女が電話口にでた。
「話がしたいんだけど、今度の土日にあえませんか? こっちはシオモトといっしょにいくので、オガワさんもいっしょにどうですか」
単刀直入にきりだした。
「私はダメだけど、オガワ先輩はわからないからきいてみましょうか」
ガックリきた。
勇をふるって電話したのに事務的にさらりとながされた。せめてドギマギしてくれたらよかったのに。
話の穂をつがなきゃ、とあせっていたら、「それじゃあ」と電話をきられた。「会話術」のテクニックをいかすすきもなかった。
全身の力がぬけた状態で例会場にいくと、みんなが報告をまっていた。
「予想どおりやったわ」
「それじゃわからん。ちゃんとはなせ」
「週末はひまがないんやて」
泣きそうな思いで報告すると
「これがもしフジーじゃなくてほかのヤツがかけたら『ずーっとひまなんですぅ』なんていうんちゃうか」
シモザキとセージはちゃかす。たしかにそうかも……。
京女の寮の子とデートをしたヤツがまじめな声色でつけたした。
「オクダさんは週末はいつもいそいそとでかけているそうや。彼氏がいるんちゃうかなぁ」
目の前がまっくらになった。
あとは手紙で思いをぶつけるしかないのか。でもそれを拒絶されたらとかんがえると足がすくむ。
8日後の15日には祇園祭りの宵宮にみんなででかけることになっていた。
自分の気持ちを手紙にしてとどけよう。
祇園祭り、再会ははたせたが

7月15日の昼間は、滋賀県にすむ水俣病の患者さんの話をききにいくことになっていた。友人の自動車ででかけ、夕方にはもどるつもりだったが大渋滞にまきこまれた。
京女の子たちは学生寮だから門限がはやい。気ばかりあせって19時半にもどったが、もみくちゃの群衆のどこにいるのかわからない(携帯電話は存在していなかった)。汗だくになって碁盤の目状の街を右に左にさまよいあるき、八坂神社ちかくでようやく一団をみつけた。
浴衣姿の彼女はきれいでかわいい。心臓がたかなってはなしかけることもできない。用意していた手紙は、彼女らが市バス206系統にのってしまう直前にねじこむようにわたした。
しばらくして速達で返事がとどいた。
「ひとりで読んでください」と書いてある。みんなに相談して勝手にもりあがったことへの不快感の表明だ。
手紙の内容はもちろん「お断り」だ。でもその理由が想像をこえていた。
中学時代から男に生まれたかった。男のくせにやりたいこともやらずウジウジとしているヤツをみると罵倒していた。自由に生きているボヘミアンの人たちにあえてうれしかった。
なのに「女」としかみてもらえなかったことが残念だった。
男になれなかった女のことをおもいだして、たちあがってほしい。
私は女であることをうけいれて、静かな日を満足して、本を読んだり美術館へいったり編み物したり、お花をしたりしていきます……
たしかそんな内容だった。
頭がカーッとして、焼酎の「純」をあおりながら、今の自分の思いを大学ノートにしるしてみた。純がからになって、気づいたら大学ノートも1冊おわっていた。外をみたら空がしらみはじめている。いてもたってもいられなくなって、またもや比叡山にかけのぼった。
こうして、傷心のまま夏のサバイバルへ……というながれだと記憶していた。
だが今回、昔の日記をひっぱりだしたら、手紙の下書きが大量にでてきた。
当時はワープロもパソコンもないから、日記帳にしていた大学ノートに下書きをかいて推敲し、便箋に清書していたのだ。
下書きは5、6通ぶんあり、大学ノートで20ページにはなるだろう。
「ぼくがふられるのはいいけど、自分の人生をあきらめないで!」
「もうつきあえることはないとあきらめました。でも友だちとして関係はつづけたい」
「個人の幸福はまわりの人の不幸の上に安住してはいけない。真の幸福はまわりの人をも幸福にするものだ。そういう幸福をいっしょにめざしたい」
……などと、恋愛論や幸福論をふりかざし、「友だちとして」なんて常套句をつかいながら、自分はじつはすごい人間なんだぜ! というPRをわすれていない。
あつくるしくて、イタイ。30年たってもみるにたえない文章だった。
それらの手紙を清書したかどうかは記憶にない。郵送していないことをねがうばかりだ。
「自分の中身」をつくることで、「山は好き?」「趣味はなんですか」といった「お見合い会話」からは脱することができた。でも「自分の中身」だけでは、根本的になにかがたりない。そう自覚できただけ、ボヘミアンと京都女子大の子たちをまきこんで爆発し、すべてをぶちこわした大騒動にも意味があったのかもしれない。
われながら、とんでもなく迷惑なやっちゃな。
千枚のラブレターをかいた有名人がいた
ぼくが書いた手紙の下書きや一連の日記の量は原稿用紙にしたら200枚ほどだ。自分が心をこめれば愛がつたわるはずだと心のどこかで信じていたからそれだけの量をかきつづけたのだろう。何カ月かして、その数倍のラブレターをかいたという作家の文章をよんで「負けた」とおもったが、作家の名前は失念していた。
今回、それは立花隆だとSNSでおしえてもらった。「田中角栄の研究」の「まえがき」に「千枚のラブレター」の体験を立花自身がつづった文章があった。
30歳になったばかりの立花は、片思いの女性に「これから千枚のラブレターをかく。かならずあなたを説きふせてみせる」と宣言して2年間手紙をおくりつづけたが、あと数枚で千枚という時点になっても女性の心はうごかなかった……。
「私は自分のものを書く能力に対して、完全に自信を喪失した。読者を一人にしぼり、たった一つのテーマについて千枚も語り続け、それでもなおその読者をいささかも説得することができなかったのだから」
若かりし立花の、自分の文章と愛への強烈な自負と挫折感がつたわってくる。
ひとりよがりもここまでつきぬけると後光がさす。
200枚と1000枚の差が、単にイタイ学生と天才ジャーナリストの巨大な落差をしめしていた。(つづく)