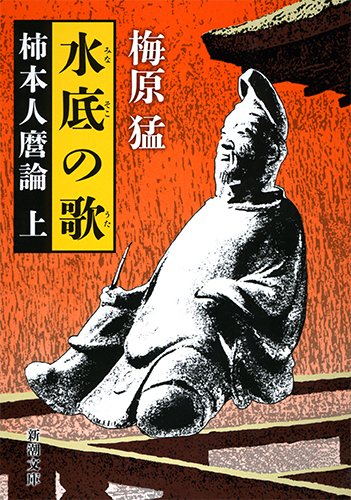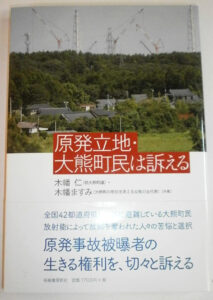■新潮文庫20230727
松尾芭蕉とならぶ日本最大の詩人である柿本人麿は長らく、島根県益田市の高津川河口の鴨島で死んだとされてきた。だが、そんな辺鄙な島で国府の役人が死ぬわけがない、と、斎藤茂吉は、海辺ではなく江の川上流の湯抱で人麿は死んだと結論づける。たたら製鉄の仕事の監督にきて、伝染病に罹患してしまった、と。辞世の歌をのこしているから、じりじり悪くなる病ではない。事故でもない。だとしたら流行病だ、と茂吉は考えた。
学界と歌壇は、斎藤茂吉の人麿終焉地の説をほぼ信じた。
梅原は茂吉の説にまず反旗を翻す。 人麿が「自らの死を傷む歌」をつくったのは、自らの死が確実であることを意識しながら、その死がのぞましくないからだ。
人麿は死後、「神」としてまつられた。神になる人は、藤原広嗣、菅原道真、平将門、崇徳上皇など、恨みをのんで死んでいった人間ばかりだ。
5つの歌を丹念によみこむと、島にながされ、そこで水死という形で処刑されたと読める。その場所は、従来の伝承どおり、高津川河口の鴨島だった……。
斎藤茂吉の説への反証をするうちに、茂吉に影響をあたえた江戸時代の国学者・賀茂真淵らが最大の敵として浮かび上がる。彼以降のほとんどの学者は、茂吉もふくめて彼らの影響下にあった。
賀茂真淵や契沖は、五位以上の貴族の死は「薨」「卒」と表記されるのに人麿は「死」と表記されていることや、五位以上なら正史にしるされるが、人麿は正史にでてこないことから、人麿は六位以下だったと判断する。石見の僻地につかわされた下級役人が、偶然の病で死んだ、という筋書きだ。
だが、 紀貫之が編纂した「古今集」の真名序・仮名序には人麿は三位、すくなくとも五位以上であるとしるされている。真淵は「それは後世の人がまちがって書き加えた」と断じた。
梅原は、真淵の判断に疑問を抱く。紀貫之が、人麿の運命や地位を誤記するわけがない、真淵の認識のどこかに誤りがあるはずだ、と。
実は、柿本人麿とほぼ同時期に、天武10年に従五位下に位置づけられている柿本猴(佐留=さる)が死んだ。
猨は人麿の父、という説もあるが、2人は同一人物ではないか、と梅原は思いつく。人麿の生年が猨とほぼ同じである可能性があることを証明していく。
「猨(サル)」という名は蔑称である可能性が高い。時の権力者の不興を買って蔑称を押しつけられる例は少なくないからだ。
人麿は、皇族の挽歌をいくつもつくってきたが、もっとも人麿を重用した持統天皇への挽歌はつくらなかった。それは「ヒトマロ」が「サル」と女帝に改名されて近江か四国の岑島に追放中だったからではないか。
さらに「猿丸大夫」の伝説に梅原は目をむける。猿丸は「有名な歌人」とされながら、古今集にも万葉集にもその名がでてこない。実は「サルマル」は「ヒトマル」ではないか……。
人麿=猨なら、身分上の説明はつく。罪人として流されていれば「死」と表記されるのもおかしくない。
人麿の死んだ(和銅元年)わずか1カ月前、藤原不比等が権力の掌握をはたしている。
藤原氏をトップとした律令制の秩序と、古くからの勢力とつながっていた詩人とは相容れなかった。当代一の詩人の死は「律令体制(藤原)に逆らうとこうなるぞ」という脅しとして機能したのではないか。
地方へ赴任して伝染病で死んだかわいそうな下級官僚ではなく、中央の権力争いにやぶれ、世にも悲しげな辞世の歌を残して入水自殺した流刑の貴族だったのだ。
人麿の立場を明確にするために、梅原は、古事記・日本書紀・万葉集の「意味」を考察する。
人麿の歌と古事記、日本書紀では天孫降臨の描き方が少しずつ異なる。
八百万の神の合議によって「皇子」が降臨していたのが、「皇孫」が降臨することになり、次に、天照大神と高木神の命令で皇孫が降臨することになる。最後の日本書紀では、高皇産霊尊(高木神)の命令で皇孫が降臨する。
神の衆議は、天武帝死後の不安な政治情勢を示し、天照大神とは持統であり、その後、外祖父である高木の神=不比等=が権力をにぎる……という経緯が神話のなかに表現されていると梅原は見る。
柿本神社は全国に70あり、大和新庄の柿本神社などの人麿像の首は、すぽっとはずれる。後世の像も、首がすっぽり抜けるものが多い。しかも天平年間には人麿は水難の神になっている。
そもそも、万葉集の相聞歌の多くは引き裂かれる男女の歌であり、挽歌の多くは強いられた死の歌だ。万葉集の巻一と巻二、すなわち「原万葉集」の中心テーマは人麿の死であり、「原万葉集」のねらいは、人麿を死に追いやった藤原権力の告発だったと梅原は説く。
そう考えれば、橘諸兄が、藤原との対決を覚悟しはじめた天平勝宝5年に原万葉集がつくられたという伝承に符号する。諸兄や家持の時代に、人麿が復権されたのだ。
その後、藤原がふたたび権力を独占する。大伴家持は左遷させられ、死の直後、大伴継人の反乱に関与した容疑で官位を剥奪される。
ところが、桓武天皇の死の間際に復位される。桓武の弟で、桓武が息子に天皇をつがせるために無念の死を遂げた早良皇太子(崇道天皇)の怨霊鎮魂のためだった。家持は崇道天皇の近臣としてつかえていた。
橘諸兄と家持による万葉集A(原万葉集)は、藤原仲麻呂らによって勅撰集の地位を奪われ、仲麻呂体制の成立とともに大伴家持も左遷された。左遷中に家持は20巻におよぶ歌集をつくった。
しばらく眠っていたその万葉集が、桓武天皇が没し、早良皇太子(崇道天皇)の怨霊がおそれられた大同元年に、家持と彼の主君の早良皇太子の怨霊鎮魂のためにふたたび勅撰化された……と、万葉集の制作過程を梅原はえがく。
徳川時代の国学者たちは浪人や町人で、身分秩序のきびしい封建時代を暗い社会とし、それを否定する明るい社会として日本古代を理想化し、古事記や万葉集を「聖典」と考えた。素朴で明るい神話=古事記、健康でますらおぶりな歌集=万葉集、という見方が国学者たちによってつくられ、明治以後もうけつがれた。
古い日本の魂は、そんなに、浄く、明るく、直きものではない。浄く、明るく、直き魂は、律令支配者がつくった「上からの道徳」にすぎない。不気味で、暗いものが、日本人の魂の底にある。この本で梅原はそう主張している。