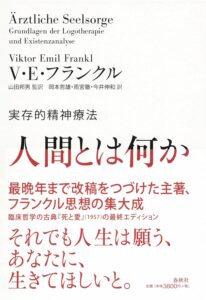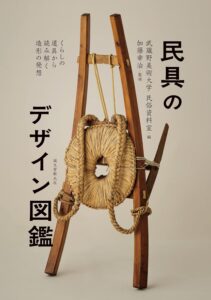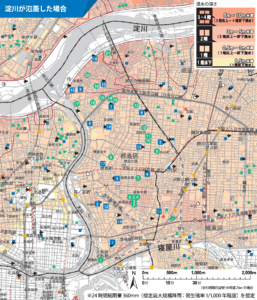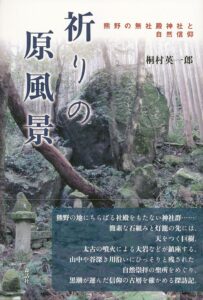久髙オデッセイの最終作である「久髙オデッセイ第3部 風章」をウェブで鑑賞し、助監督をつとめた高橋慈正さんの解説をきいた。
12年に一度の午年の年にもよおしていたイザイホーは、島で生まれ、島の男性と結婚した30歳から41歳の女性の女性が神人になる儀式だったが、1978年を最後にとだえた。
大重潤一郞監督は、2002年から「久髙オデッセイ」を撮りはじめ、最終作である「第3部 風章」は2012年から撮影し2015年に完成した。完成後まもない7月22日に監督は亡くなった。
映画は「イザイホーは1978年でとだえたけど、地下水脈は流れつづけている」という言葉からはじまる。
東海岸のサンゴ礁にかこまれたイノー(浅海)では初夏、中学生が追い込み漁を体験する。東南アジアから南太平洋にみられる漁法だ。とれた魚は自分たちでさばいてみんなで食べる。
2000年には久高島留学センターがオープンし、子どもたちが、落ち葉と生ゴミで手作りした堆肥で野菜をつくる。野菜ぎらいの子も多いはずだけど、自分でつくった野菜は不思議とおいしい。そんな記憶は私にもある。
海でとったモズクからサンゴ石をとりのぞく作業も子どもにとっては「遊び」だ。1月のスク漁では、大人をまねて子どもも海にとびこむ。資本主義以前は、生業と遊びはごちゃまぜだったのだ。
祭りではカチャーシーをおどる。ラテンアメリカではサルサやメレンゲは身体をつかった男女の会話だった。踊れないのがくやしかった。カチャーシーもまた、人と人、神と人との交歓だ。自然にリズムをきざめる身体がうらやましい。
私は岡本太郎の影響で久高島を訪ねたから、スピリチュアルにひかれる多くの旅行者と同様、独特の信仰や祭りなど「特異なもの」に注目してきた。でもあたりまえなのだけど、スピリチュアリティは生業や生活という基盤の上に形成されるものだ。島に通いつづける大重監督には、生業や遊びと信仰や神事がひとつながりに見えている。暮らしと神をすんなりつなげる世界観が心地よい。
双胴船のヨットに乗った一家が島に立ちよる。主人公である内間豊さんの妻も東京から移住してきた。古来、海のかなたから「まれびと」をうけいれてきたことは、沖縄の祖神アマミキヨが上陸したという伝説が示している。内間さんの娘のナオコちゃんの成長は、永遠の命の象徴のようにみえる。たぶん島人たちは「まれびと」の力をかりながら、島の暮らしを守ってきたのだろう。
大重監督は撮影しはじめたばかりの2003年に「12年後には新たな祭りが再生する」と予言していた。
若いカミンチュのアキさんは、祖父が神人で、2008年ごろから神事に参加していた。
2014年旧暦11月15日のイザイホーの日、アキさんら4人が祈る場面に撮影クルーは偶然遭遇した。その日がクランクアップで、がんで入院していた監督は病院を抜けだしてきていた。
遠くからカメラをまわしていると、手をあわせるアキさんの目からは突然涙がふきだし、神にとりつかれたようにイザイホーの祈りの歌をうたいつづけた。
「地下水脈からでてくるような歌声だった。生きているあかしが祭りである。やがてちがったかたちで復活するだろう」と大重監督は映画で語った。
その日のできごとは、ほとんど住民も知らなかった。映画を見た人びとは「あのシーンを見られてよかった」とのべたという。
超越(神仏)なしには、人は生きる意味を失ってしまう。祈りなしには人は生きられない。逆に祈りがあるかぎりムラはつづく。能登半島の人々の粘り強さは「祈り」の力でもあった。久高島のイザイホーの地下水脈もまた祈りとともに生きつづけるのだろう。
大重監督の作品は7つほど見てきたが、遺作となった「風章」は最高傑作だと思う。