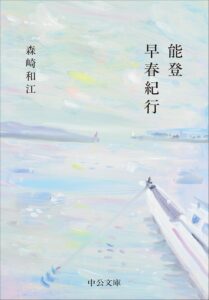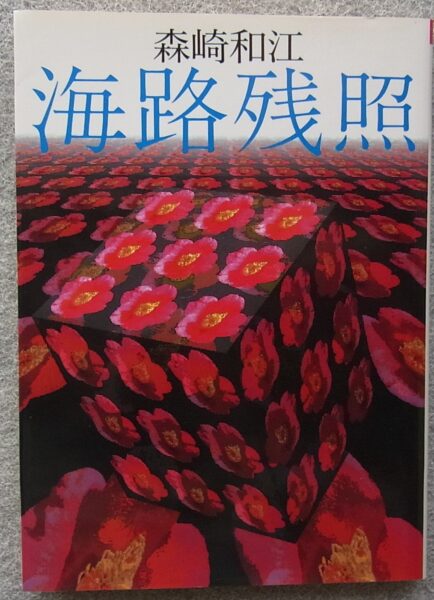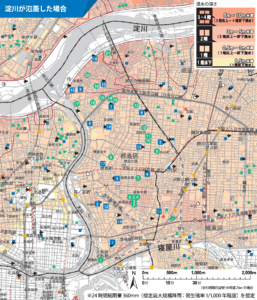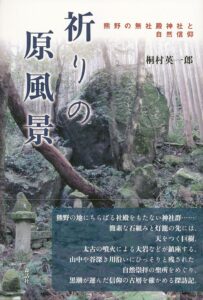■朝日新聞出版 20250328
玄界灘につたわる、ほら貝を食べて不老長寿になった海女が津軽に流れていくという伝説からはじまり、若狭や隠岐、越後の寺泊、佐渡の小木…の八百比丘尼の跡をたどる。
人魚の肉を食べて幾百年も生きつづけた八百比丘尼の伝説は、熊野権現の信仰を広めた比丘尼の語り口が一人称であったところから生まれたらしい。
八百比丘尼の生誕地の小浜は、筑紫平定に向かった神功皇后の船出の地であり、筑紫の海女が小舟に乗ってアワビをとりにいった地方でもあった。
鐘崎周辺では朝鮮半島を「川向こう」と呼び、「筑紫は朝鮮と親戚みたようなもんじゃから」という感覚だった。済州島に行った漁師が島の海女と結婚して郷里につれかえり、海女漁をひろめたという伝承もある。
鐘崎からは、海女の家族が対馬や能登、五島列島や天草、瀬戸内海づたいに四国沿岸まででかけた。
八百比丘尼などの伝説と、海女の暮らしとの関連をさぐっていく。
海をなりわいとする海女たちには海神(女神)信仰があったはずだが、宗像族の海の女神が律令国家の時代にアマテラスの体系下にはいり、独立した信仰体系としては残らなかった。でも、若狭小浜には「宗像の神さま」をまつる神社があり、小浜には戦前まで潜水漁をする沖縄の糸満漁民がきていた。輪島の重蔵神社では、「舳倉島の女神さまが蛇神となって海を渡られ、その先の川尻…河井の浜でお産をなさった」と伝えられている。
敦賀の常宮神社の祭神は神功皇后で、新羅から伝わった鐘は国宝だった。神功皇后の母親の母系の祖はアメノヒボコであり、父系はスガマユラトミでいずれも渡来者だった。
八百比丘尼の伝承は、若狭以東では越後の寺泊や佐渡の小木近くなど、航路に近い地に残っている。一方、内陸の会津駒形村の金川寺にも伝わる伝説では、比丘尼の父を勝道上人としている。龍神が上人をもてなし、そのご馳走のなかに9つの穴のある貝があった。それを上人の娘が食べて八百比丘尼になった、という。これは海路ではなく修験とつうじて伝わったのだろうか。
津軽では荒吐族(あらばきぞく)が独自の文化をもち、中央権力に対抗していた。荒吐族の中心勢力である安倍貞任の一党とその子孫の安東氏は、鎌倉幕府とも一線をおいて独自性をつらぬいてきた。「邪馬台国の王の安日彦命と長髄彦」が祖先とされた。津軽では、明治時代に祭神変更を強要されるまで、ほとんどの社は荒吐神をまつっていたという。
九州の宗像神とちがって、津軽には、強固な共同体的氏神はない。人々が心をよせているのは地蔵と岩木山だという。「ごみそ」や賽の河原のちいさな地蔵たちに祈る人々の愛が信仰の核になっているという。
青森の十三湊は、中世期に活躍した安東水軍が拠点として幕府と拮抗していた。安東氏と幕府のあいだに年3回北国船が往来し、その船の幕府側の湊が小浜だった。安東氏は、焼失した小浜の羽賀寺の再建にもかかわった。
中世は、小浜や敦賀、十三湊などが栄えたが、船が大型になると、浅い港は沖積みしなければならなくなる。沿岸伝いの航行から沖乗りの大型船の時代になって、能登半島の福浦、佐渡の小木、越後の酒田、津軽の深浦などが活気をみせるようになる。
深浦の船着き場近くには、船方衆が澗口観音とよんだ円覚寺と、問屋と遊女屋がならんでいた。寺の本堂脇の観音堂にはおびただしい船の絵馬があった。深浦のにぎわいは明治15,6年ごろまでつづいていた。
十三湊も「料理屋もわたしが記憶しているだけでも十数軒ありましたから、明治のころはもった多かったでしょう。夜になると三味線がにぎやかでした。近くの村では十三をまちと呼んでいました」という。
十三湊が米や木材の積み出し港として北前船に応じきれなくなった江戸期に、深浦についで鰺ヶ沢および青森が開港した。西廻り航路の主要港となった鰺ヶ沢に対して、青森は、東廻り航路で江戸廻米を運んだという。