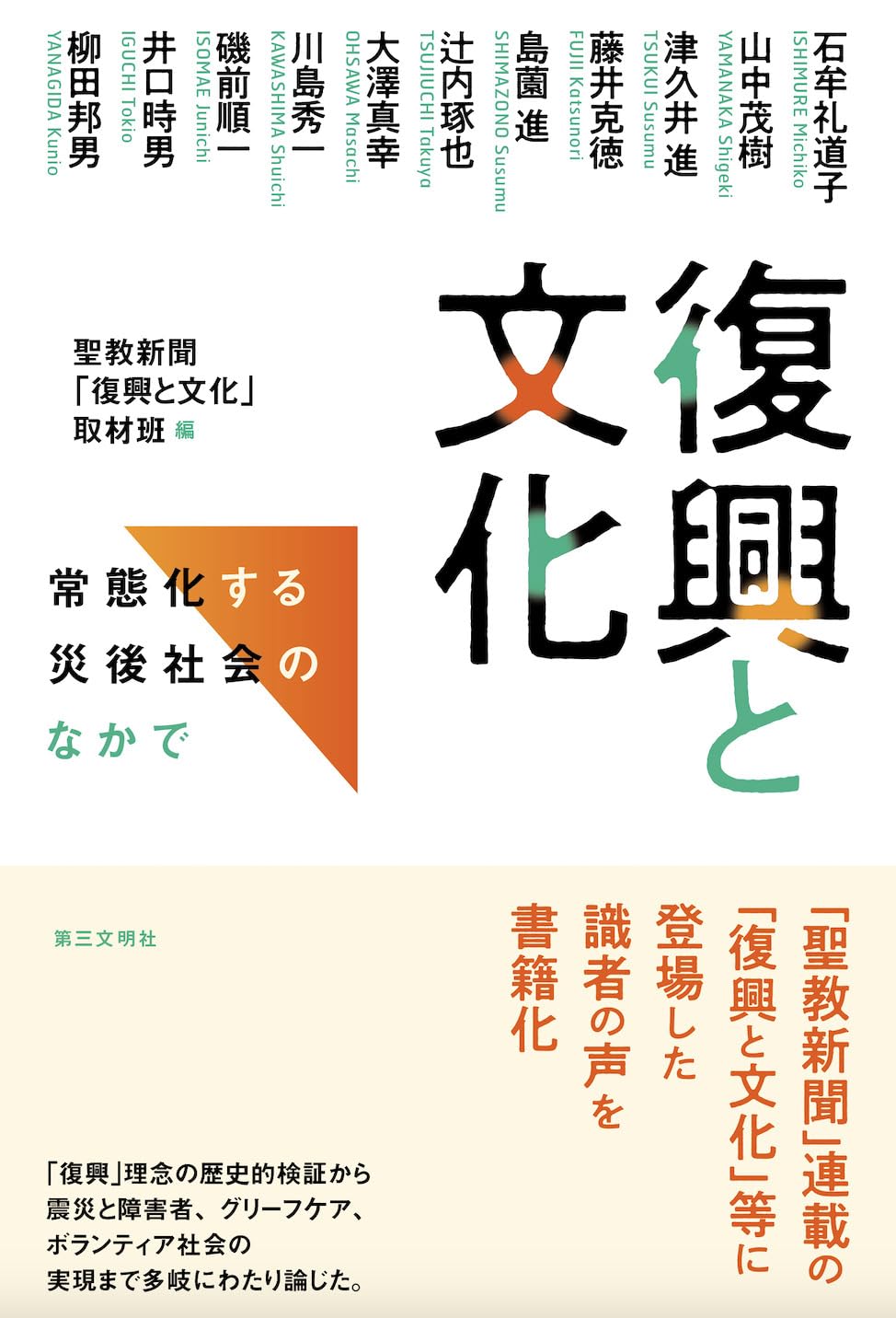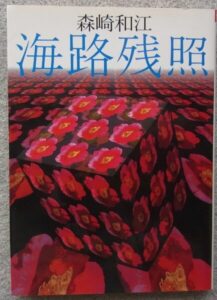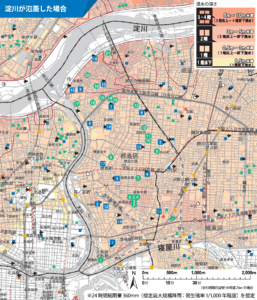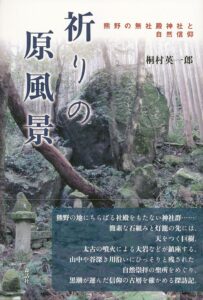■第三文明社250303
能登の民俗文化が消えてしまうのではないか、どうしたら防げるのかヒントを得られるかと思い、「復興と文化」という名にひかれて購入した。勉強になる内容もあったけど、私の知りたいこととははずれていた。
以下、興味深いところを抜粋。
▽山中茂樹さん
阪神淡路大震災で提唱された「創造的復興」で、被災者生活再建支援法の原型となる制度の提唱や、幹部職員を有識者らとチームを組ませて被災者の声を聞いてまわる被災者復興支援会議の設置などの成果をあげたと評価する。
一方、東日本大震災や熊本地震では、「創造的復興」を唱えながら、国に財政出動を求める中央依存型の災害復興に矮小化され、空港民営化や農地集約化といった新自由主義的経済復興に変質したという。能登半島地震でも知事は「創造的復興」をかかげるが、どうやら後者に近いようだ。
村山富市首相は「一般的に自然災害等によって生じた被害に対して個人補償をしない、自助努力によって回復してもらうということが原則になっている」(1995年5月)と答弁したが、小田実らの市民・議員立法運動によって98年、被災者生活再建支援法が成立し、「私財形成に公的資金を投じることは許せない」とする新自由主義派の壁に「蟻の一穴」をあけた。2007年には支給最高300万円という改正支援法が成立した。
▽津久井進弁護士
制度を前提に生活を切っていく残酷さ。そうではなく、憲法の生存権と生活の実態から制度の運用を組み直す必要性を説く。
被災者の苦しみを生みだす原因は「法制度」の側にある。個々に異なる困難は、法制度という画一的・類型的な救済措置ではカバーしきれない。一人ひとりの被災者に「人」が寄り添って個別の支援をする災害ケースマネジメントが必要だと説く。以下の指摘はいずれも重い。
「能登半島地震直後の1月4日び石川県庁は、危機管理関連の部署以外は平時モードだった。生命維持の限界水準となる72時間が過ぎる瞬間にも庁内で緊張を感じられなかった」
「災害弔慰金の申請をして認められなければ災害関連死と認定されないことが災害関連死の実態が見えない一因になっている」
「能登半島地震の復興が遅れている最大の原因は、ボランティアの不足にある。あるいは、ボランティアの本質である「自由」「自立」「利他」が忘れられ、行政のお手伝いをする下請的存在に成り下がっているところにある」
▽藤井克徳(日本障害者協議会)
障がい者や精神障害や認知症、それに準じる人たちが人口の2割超を占めており「マイノリティー」ではない。
災害時、それらの人が犠牲となるリスクが際立っている。阪神大震災を契機に「福祉避難所」がつくられたが、能登半島地震2週間の時点で、被害の大きい7市町で福祉避難所が開設されたのは想定の2割だった。
▽島薗進
かつてお盆のとときに人はよく泣いたが、文明社会に進むことによって泣くのが下手になったーーと戦時中に柳田国男は述べた。
他者が自分の悲嘆に共鳴すると期待できない状況では心を開いて泣くこともできない。
▽辻内琢也 医療人類学
2021年から、ゼミの学生による、同世代の原発事故被災当事者へのインタビューをはじめた。当時小学生だった被災当事者たちが、この10年間、どのように暮らしてきたか。避難先学校でのいじめ、福島育ちを秘匿しながら生きてきた孤独感、親の顔色をうかがいつづけてきた日々……。当事者の悲痛な語りは、学生たちに大きな衝撃を与え、しだいに尊敬の念が芽ばえていった。当事者にとっても、誰にも話せなかった思いを同世代の学生たちに傾聴してもらうことで、安心と癒やしが得られる場となった。
困難を抱えた個人同士が連帯することで、変革への風を起こすことができる。
□井口時男 大震災と俳句
東日本大震災でも文学は変わらなかったが、俳句だけは大きくかわった。
関東大震災には震災詠はほとんどなかった。「ホトトギス」によって俳壇を支配していた高浜虚子の俳句観によるものだった。虚子は、俳句というものは春夏秋冬を滞りなく循環する穏やかな自然を詠むものだと考えた。
「写生」を唱えたのは彼らの師の子規だったが、子規にとっての写生は、類想によってマンネリ化していた「月並俳句」を打破する手段だった。
子規においては「手段」だった写生を弟子たちは目的化してしまった。写生は自然の模倣再現をめざすから、想像力による虚構は排除された。
1931年、水原秋桜子がホトトギスを離脱し、社会的な主題を詠みはじめる。子規の改革の初志を継承したのは、彼ら昭和の「新興俳句」だった。だが戦時体制でつぶされた。虚子の「花鳥諷詠」にしたがった俳人たちは俳句会をあげて戦争に翼賛した。
1950年代に金子兜太らが「社会性俳句」運動を展開したが1960年の安保闘争敗北を機に俳句界も保守化する。
そんななか、現代俳句協会の呼びかけに俳人協会や日本伝統俳句協会が応じて編まれた「東日本大震災を詠む」は画期的だった。
□柳田邦男
日本の政治・行政において、危機管理の基本的な思想が形成されてないことが問題。
2002年に文科省の地震調査研究推進本部地震調査委員会が、三陸沖から房総沖にかけてマグニチュード8級の津波地震が30年以内に20%の確率で発生するおそれがあるとの報告書をまとめた。ところが、発表直前に内閣府の官僚から「上と相談したところ、非常に問題が大きく、今回の発表は見送り、取扱について政策委員会で検討したあとに、それに沿って行われるべき」と、発表を控えるようにという横やりが入った。さらにやむを得ず発表する場合においては、発表文書の冒頭に、「この予測は信頼性が低いものなので、防災対策の見直しが迫られているものではない」と言うに等しい文章を加えるよう要請してきた。
「歴史的な地震は震源や規模などを科学的に確定する資料が不十分であり、そうした科学的根拠に乏しいデータはこれから起こる地震を予知する対象から除外すべきだ」という悪質なロジックだった。
たとえば平安時代には、大規模な津波をともなった貞観地震が起きたが、、これも官僚のロジックでは、参照されないデータにされてしまった。
事故前、福島第一原発を襲う想定津波最高水位は5.7メートルとされ、原子炉建屋の敷地は、海面から10メートルの高さだから津波対策は十分だとされた。ところが実際は高さ15メートル前後の津波が襲った。
国や東電の責任者は異口同音に「想定外」と言ったが、専門家の警鐘に耳を貸さなかっただけ。非常用ディーゼル発電機は、地下階にならべていたために水没した。原発事故は想定外などではなく、国や東電の安全性確保への思考停止が招いたものだった。
パンデミック対応も同様だ。
ドイツでは2013年にコッホ研究所が提出した「リスク分析報告書」をもとに、ドイツ全土でいざという時に速やかにPCR検査ができる態勢が整えらた。コロナの感染拡大に早い段階で対応できた。平時において最悪の事態をリアルに想定して、具体的対策を準備していた。日本はコロナ初期、多くの国民がPCR検査さえ受けられない状態だった。初動があまりに遅かった。
福島原発事故では、政府事故調査・検証委員会の委員長代理をつとめた。
政府の調査は、が周辺地域の汚染状態や、震災関連死の数、農業生産の被害額といった、マクロな数字で捉えられる被害ばかり。広域避難による家族の離散・崩壊、ふるさとの喪失、PTSDなど、ミクロな視点でも被害者に多大なダメージを与えた。これらすべてを調査することを強調してきた。
全容調査の大切さは水俣病の歴史から学んだ。公式発見は1956年で、59年には厚生省の食品衛生調査会が、主因をは、魚介類に蓄積されたある種の有機水銀化合物であると答申した。熊大の調査によって、原因物資が工場排水にあるのではないかと指摘されていた。
これにたいしてのちに首相になる池田勇人・通商大臣は、有機水銀が工場から流失したとの結論は早計であると反論し、国による排水規制や、漁獲規制がなされなかった。政府が、チッソ水俣工場による公害と断定するのは1968年だった。9年間でさらに多くの患者を生んでしまった。
水俣病が公害の原点と呼ばれるのは、公害発生時に国が原因究明に乗り出さず、対応を遅らせ被害を拡大させたという、日本の危機管理や災害対策の思想の欠如を象徴しているからであり、本質的に同じことが東日本大震災・福島原発事故でも繰り返された。能登半島でも今世紀に入り、地震が何度も起きていたのに事前に対策が立てられていなかった。
日本に安全・安心の柱となる危機管理の思想を築くことが急務だ。
ボランティア活動は、社会は隙間だらけだということを浮き彫りにした。とくに行政や司法がつくる隙間によって、支援の手が届かず切り捨てられる被災者は多い。そうした観点からも、日本の安全文化を考えた時に、ボランティアは大きな柱となるだろう。