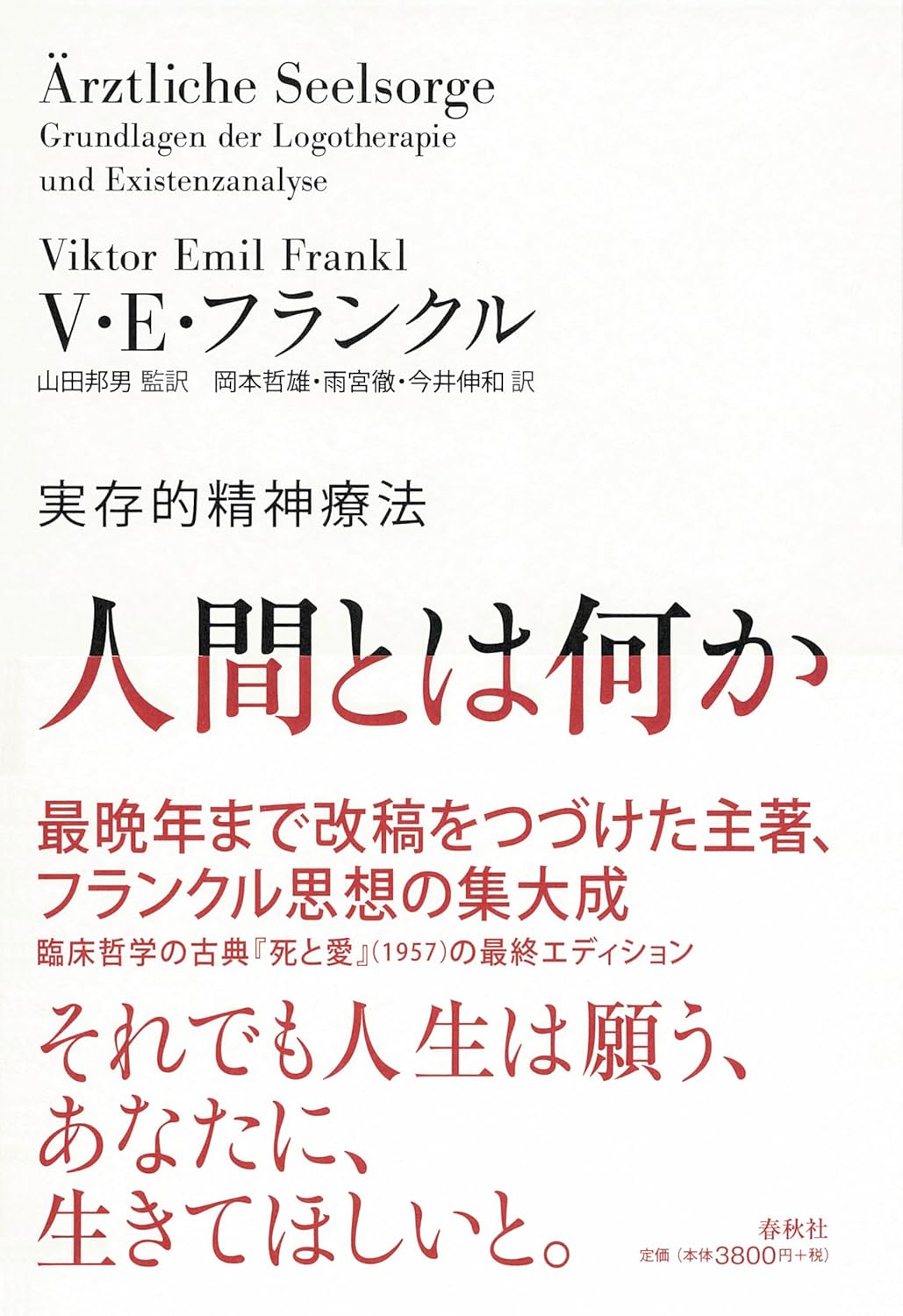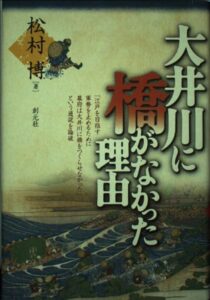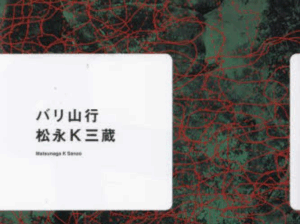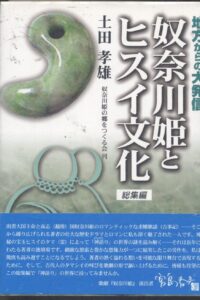■春秋社250628
強制収容所を生きぬき、妻も親も失っても「生きる意味」をおいつづけたフランクルに魅せられてきた。この本では、フランクルの思想や精神医学者としての「ロゴセラピー」の実践が詳細につづられている。
フロイトの精神分析は、人間は性的欲動(リビドー)に駆りたてられ、快楽への意志によって支配されているものとみなす。そこでは、「無意識」と現実との間に妥協をもたらすことをめざす。
アドラーの個人心理学は、そうした精神分析の「適応」を超えて勇気をもって現実を「形成」することを目標とし、他人から認められようとする努力に注目する。人間の現存在は「力への意志」によって規定されているとみる。
だが心理学主義は単純な名誉欲にこだわり、根源的に自己を永遠化しようという努力には目がとどかない。芸術は人生や愛からの逃避にすぎず、宗教は、宇宙の圧倒的な威力にたいする原始人の恐怖に「すぎない」とされる。
「人間」の全体像を理解するには、精神分析による「適応」と個人心理学の「形成」にくわえて、「充足」というカテゴリーが不可欠だとフランクルは説く。人生の「充足」は、その人にのみ課されている価値可能性へと方向づけられている。実存分析は、人間の現存性の中枢は意味への意志にあるとみなす。
動物は環境に順応する知恵(本能)しかないから、自分自身を超えて立つこと(超越的なものを考慮すること)、自分自身と向きあうことができない。動物は「世界」をもたず、ただ環界(環境世界)をもっているにすぎない。
「動物ー人間」「境界ー世界」の関係から推定すれば「超世界」に行き着く。動物の境界からはそれに優越する人間の「世界」を理解できないのと同様、人間は「超世界」を把握できない。できるとしたら、信仰によってのみである。家畜が、人間が自分をどのような目的で使役しているか知らないのと同様、人間は、世界にどのような超意味があるか知ることはできない。
人間は、生物学的・心理学的・社会学的に支配されているが、こうした制約に対して態度を選択する「自由」をもっている。実存哲学は、人間の存在を、単に「ある」のではなく、そのつど新たに決断する存在であると位置づけた。ロゴセラピーはそうした実存主義を基盤にしている。
ロゴセラピーの実存分析では、人間的実存の本質的根拠である責任性を意識にもたらそうとする。責任とは、意味に対する責任だから、人生の意味への問いが中心となる。
人生の意味は快楽や幸福にあるのではない。快楽や幸福は目標ではなく、努力が実現されたことの結果でしかない。
人間は幸福であることではなく、幸福であるための根拠をもつことを欲している。だから、人間が快楽や幸福を直接求めようとすればするほど、快楽や幸福は逃げ水のように遠ざかることになる。
人間のするべきことは、常に、「いま・ここ」で「なすべきこと」という具体的な形で提示される。それぞれの人はそれぞれの瞬間において、ただひとつの使命をもっている。こうした個人の唯一性と状況の一回性は「死」という期限によって強いられたものであり、人生の意味にとって本質的なものだ。
人生は今まさに撮影中の映画であり、あとから「編集」されてはならず、一度「撮影」されたものは後戻りできない。人生は死ぬまでなにかの「途中」なのだ。
「創造価値」を生み出せず、美術鑑賞のような「体験価値」を得る機会がない強制収容所でも、「いま・ここ」でどんな対応をするか決断するという「態度価値」は残る。人間は意識があるかぎり態度価値にたいして責任を負っている。
実存哲学は、人間の現存在を本質的に具体的なもの、「各人ごとのもの」として際立たせた。「人はいかにして自分自身を知ることができるか。それは決して考えることによってではなく、行為することによってである。汝の義務を果たそうと努めよ、そのとき汝はただちに、汝が何であるかを知るであろう。では、汝の義務とは何か。日々の要求がそれである」というゲーテの言葉は実存哲学の本質を示している。
自分の責任を意識しない人は、人生を「与えられたもの」と考えるのに対して、実存分析は、人生を超越的な審級から使命として与えられたものとして見ることを教える。
だから、人生の意味は、人間が問うものではなく、人間は人生から問われる存在であり、人間は責任をもって人生に答えねばならない。その答えは、人間が責任を負っている具体的空間における具体的な行動を伴ったものでなければならない。
モザイクの石の独自性が価値を得るのは、モザイクの全体に関係づけられることによってのみである。それと同様、人間の個人的な独自性が意味をもつのは、その上位にある全体(共同体)との関係においてである。
共同体の意味は個性によって構成され、個性の意味は共同体によって成立する。一方、「大衆」の意味は、構成する個々人の個性によって妨げられ、個性の意味は大衆のなかで消失する。
大衆のなかへ逃避した人間は責任性を失う。真の共同体は責任ある人格の共同体である。それに対して大衆は非人格化された存在の集まりにすぎない。人間の自由は、あらゆる制約の只中における自由であり、制約こそが人間の自由の出発点といえる。人間は自由存在であるがゆえに責任存在なのだ。
個性が共同体と結びつく生業のある共同体(ムラ)は、たとえば災害時にひとりひとりが責任を自覚して行動するから強い。都市の大衆は顔のないアノニマスな存在の集まりだから無力におちいりがちだ。
強制収容所などで「未来」を失ったとき、ただ現在だけを漫然とすごすことになる。そんな場での精神療法は、生きなければならないということを「未来の相のもとに」見る時のみ可能になる。「もはや人生からなにも期待できない」と自殺しようとしていた男性は、地理学の本を書くという具体的な使命をもつことで意欲をとりもどした。
収容所からの解放された人々は、もはやこの世で怖れるべきものは神だけだと実感した。多くの人々が、神をふたたび信じることをまなんだ。収容所だけではない。身近な人の死に直面した人間は、超越的なものを実感するようになる。
ロゴセラピーでは、意志の自由、意味への意志に加えて「苦悩の意味」を柱とする。「死の運命と苦悩が人生からはぎとられるならば、人生はその形と姿を失ってしまう」「人生は本来、それが困難になるほど、それだけ意味に充ちたものになる」「輝くべきものは、燃えることに耐えなければならない」
愛については以下のように論じる。
性的欲動の満足は快感を与え、恋愛は喜びを与え、愛は幸福を与える。恋情は人を盲目にするが、真の愛は「永遠の愛」として体験され、人間の目を鋭くする。愛は他者をひとつの独自世界としてわれわれに体験させ、それによってわれわれ自身の世界をいっそう広くさせる。愛は、相手の死を超えて持続する。死によって人格そのものが存在しなくなるのではなく、その人格が自分を表現できなくなるにすぎない。
死をへてむしろ愛は深まり、愛によって、理性を超越する存在の目から人生をとらえられるようになる。これは実感としてよくわかる。
愛が永遠であるのと同様、「過ぎ去った」ということは、失われたということではなく、すべてが失われることなく救い出されたことを意味する。一度生じたものは世界から取り除かれることはない。だからこそ私たちは、世界のなかでなにかを創りだしつづけなければならない。
人間存在は責任存在である以上、人間には意味を充足する(使命にこたえる)責任がある。実存分析が望むのは、自分が責任存在であるという意識へと患者を導くことだ。だが「何について」の責任か「何に対して」の責任かという問いは、精神療法においては未決定のままにしておかねばならない。それらの問いは宗教の領域だからだ。