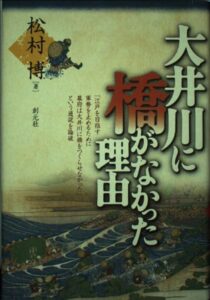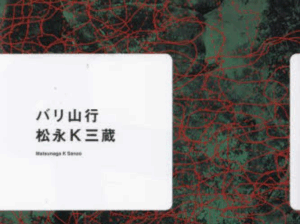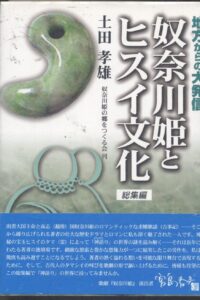■ちくま学芸文庫241103
岡本太郎が縄文を再発見するのと軌を一にして、筆者が伊藤若冲らを再発見したときいて、両者にどんな関係があるのか知りたくて購入した。縄文との直接のつながりには言及していないけど、野卑とか頽廃とかさげすまれていたものの美的価値を発見する感性は、岡本太郎と似ている。
1968年に「美術手帖」に連載したものをもとにしている。
登場する6人は当時は無名の存在だった。主流から逸脱した「傍流」「異端」とされ、国内では評価されず多くが海外のコレクターに買われていた。
異端の少数派ではなく近世絵画史における主流の前衛であると筆者が再評価した。これらの主流を背後から動かしていたのが民衆の貪欲な美的食欲だったという。
岩佐又兵衛は、妖気をはらんだ毒々しい卑俗だけど官能を直接ゆさぶる作風だ。
狩野山雪は、狩野永徳の死後、画壇全体が整った優美な装飾形式にながれるなか、永徳の晩年の「怪々奇々」な表現の流れをうけついだ桃山巨匠の生き残りだ。1世紀以上おくれて登場する若冲、蕭白、蘆雪ら「京都奇想派」の先駆けだった。
伊藤若冲は、古画の模写ばかりの風潮を批判し、鶏を庭で飼い、「物」からの直接の描写に意義を見出した。写生主義を唱えた17歳下の円山応挙は徹底した正確さをめざしたが、若冲は、執拗に観察するにもかかわらず、その外形は不正確で幻想的でさえあった。中国画の素養をもつ彼が、「物」の対話をすることで、独特の特異の世界がつくられた。
曾我蕭白は、妖怪のような寒山拾得図など、グロテスクな人物画で知られる。
長沢蘆雪は応挙の門下で、若冲、蕭白につづいて、京画壇で活躍した。
串本の無量寺の僧が、南紀の東福寺系の寺に襖絵を揮毫するように応挙に依頼。蘆雪がその代役をつとめた。蕭白の怪奇な仙人たちが、超現実の国にすむのに対し、蘆雪の山姥図には、市井の卑俗な現実に根ざす実感がある。若冲・蕭白・蘆雪があらわれた背景には、天明寛政期の京市民の、沈滞に反発する鋭敏な美意識があった。それは、伝統主義のアカを落とした身軽な形で、幕末の江戸市民に受けつがれていく。
清長、歌麿、写楽らの活躍した天明・寛政年間(1781〜1801)を浮世絵の黄金時代と呼び、以後の末期浮世絵を、北斎、広重の風景画をのぞいては、頽廃、衰退の過程として低く評価するのが正統的浮世絵史観だったが、歌川国芳はその考えをくつがえす存在だ。
「荷宝蔵壁のむだ書」という、蔵の壁に釘で描いた落書きに見たてた役者似顔絵は、近代マンガのはじまりともいえる。
水野忠邦は徹底して言論・風俗を取り締まり、忠邦失脚後も、国芳は当局の要注意人物としてマークされた。幕府の隠密が、町奉行の命をうけて国芳の行状を探査した報告書が残っているという。