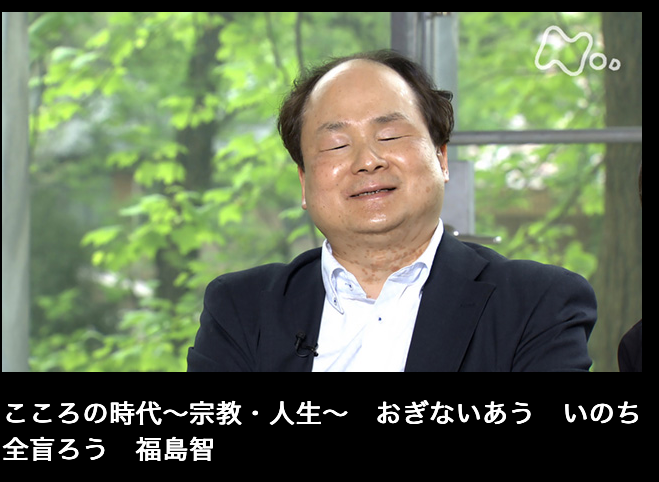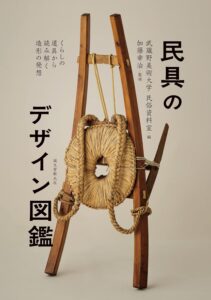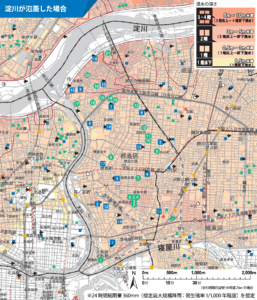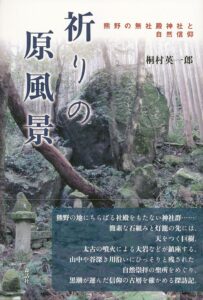■<亀川芳樹ディレクター>
福島智さんは東大で特任教授をつとめる障害学の第一人者だ。盲ろう者としてはじめて大学(都立大)に入学し、点字のタイプライターの通訳で講義をうけ、金沢大助教授から東大の助教授になった。
1962年生まれ。9歳で視力を失って、18歳で聴力を失った。音も光もない世界を中途で強いられた人が、どうやってなにを支えに生きているのだろう? ナチスの強制収容所を生きぬいたフランクルと共通するものがあるような気がして番組を見た。
福島さんは通訳者が点字の位置を指で押す「指点字」によって会話する。
正面にすわったディレクターが、その場の風景を説明し、「こういう説明をしたとき、先生の頭では場所の風景はイメージされますか?」と問うと、
「小説を読むとき風景を思いうかべるのといっしょで、私なりにイメージをうかべている。ただし、直接話ができるから、小説を読むよりはリアルに創造的なやりとりができます」
「(あなたと)会話をしているとき、(あなたの)見た目は思い浮かばない。その人の存在が空中に浮かんでるようなかんじです」
……そんなインタビューによって、全盲ろうの人がとらえる世界をまず再現する。
福島さんは1962年、明石海峡と淡路島を目の前にした神戸市の朝霧に生まれた。子どものころ遊んだ瀬戸内海が原風景だ。
1歳で目に炎症ができたが、「家のなかで静かにするように」と言われても、目が痛いわけでも、体が不自由ではないから退屈でつまらないだけだった。3歳で右目、9歳で左目も失明した。
全盲でも弁護士になった人の本などの啓発書は「あなたはがんばったんでしょうね」「あなたとぼくはちがう」と思って、元気をもらえなかった。
心のよりどころは落語やSFだった。落語の登場人物は長屋暮らしで、貧乏のどん底なのに明るさとバイタリティーがある。人間がぎりぎりのところで、ユーモアや勇気を発揮して生きる姿に心を打たれた。
10歳で盲学校にはいりバンド活動をしていたが、5年目の中学2年のとき、右耳が聞こえなくなり、左耳の聴力も落ちはじめる。「おれはどないなってまうんや!」という思いをカセットテープに録音した。
民間療法にすがり、玄米と野菜と豆だけを食べ、母が自転車で伴走して毎日10キロ走った。だが18歳の春、聴力も失う。
「宇宙空間にほうりだされたようなかんじ。上も下もわからず、真空だから音もしない。絶望的な孤立感でした。……宇宙空間では、恒星は明るくても、ちょっと目をそらせば真っ暗。反射するものがないと無限に暗い。デカルトは、我思う故に我あり、と言ったけど、『我』がわかるのは我でない存在がいるから。その人とのコミュニケーションがあって、 私じゃない人間からの反応(反射)があって、はじめて自分が存在してるんだと感じられるんです」
母とは点字タイプでやりとりをしていた。あるとき手元に点字タイプがないとき、母が機転を利かして、指から指へ点字をまねてみた。それが「指点字」のはじまりだった。
盲学校では。授業の内容は点字で打ってくれるが、休み時間は話しかけてくれない。指点字を打つ人がいなくなると、とたんに周囲の様子がわからなくなる。大きな壺にいれられて、ときどき上からだれかがのぞいて話しかけるけど、5分ぐらい話すと、じゃーね、と、どこかに行ってしまうというくり返しだった。
ラジオ体操? ではみんなの前に立って、号令をする役だった。だがあるとき、みんなの前で体操していたつもりが、ほかの生徒は別の作業をしていて、ひとりで体操をしていた。「はずかしい」と思った。自分が予測している世界と現実が決定的にずれていたことが恥ずかしかった。私とみんなは別の世界におるんだと思い知らされた。集団のなかでひとりぼっち、というのが一番つらいのだ。
1981年7月、盲学校の女性の先輩Aさんと、クラスメートの全盲の男性Bさんと喫茶店に行った。その際私に話しかける内容だけでなく、BさんとAさんの会話も直接話法で打ってくれた。周囲で交わされる会話まで伝えてくれて、周囲の様子を知ることができた。そのときはじめて、もとの世界に復帰できると直観し目の前がパッと明るくなった。
コミュニケーションの本質は、一方的な伝達ではなく、情報をわかちあったり、いっしょに何かするという広がりまであること。そんな広がりの有無で、コミュニケーションの豊かさと貧しさがわかる。
たとえば「寒いですね」というあいさつは伝達が目的ではなく、答えを求めているわけではない。相手と感覚を共有するコトバだ。
逆にメールは、情報の「伝達」「答えを求める」もので、いっしょに感じあおう、いっしょになにかしよう、というものではない。狭いコミュニケーションになってしまう。
そういう意味で、最近はやりの「論破」の貧しさがよくわかる。「伝達」「主張」しかない言語は決定的に貧しいのだ。
孤独、苦悩、さびしさはすべての人がもっている。福島さんは二重の障害による極限の苦悩をとおして、障害の有無にかかわらない実存的レベルの苦悩をこんなコトバで示した。
「他者とのコミュニケーションの不在が精神の死である」
障害は、心や体の制約だけでなく、コミュニケーションの欠如による苦悩が大きいのではないか。つらさや悲しみや苦悩を、自分だけで抱えこむのではなく、お互いが共有しわかちあい、苦悩を他の人とともにのりこえていける社会をめざさなければならない。
最後に吉野弘の「生命は」という詩をとりあげる。
生命は
自分自身だけでは完結できないように
つくられているらしい。……
生命はそのなかに欠如を抱き
それを他者から満たしてもらうのだ……
生命はことごとく欠如を抱いている。欠如の部分を、自分ではない他者から満たしてもらう。それがあらゆる生命にとっての根本的な関係性だという。
「欠如」が生命の本質なのだから、「能力」によって生命(人間)の価値をはかるのは根本的に誤っているのだ。