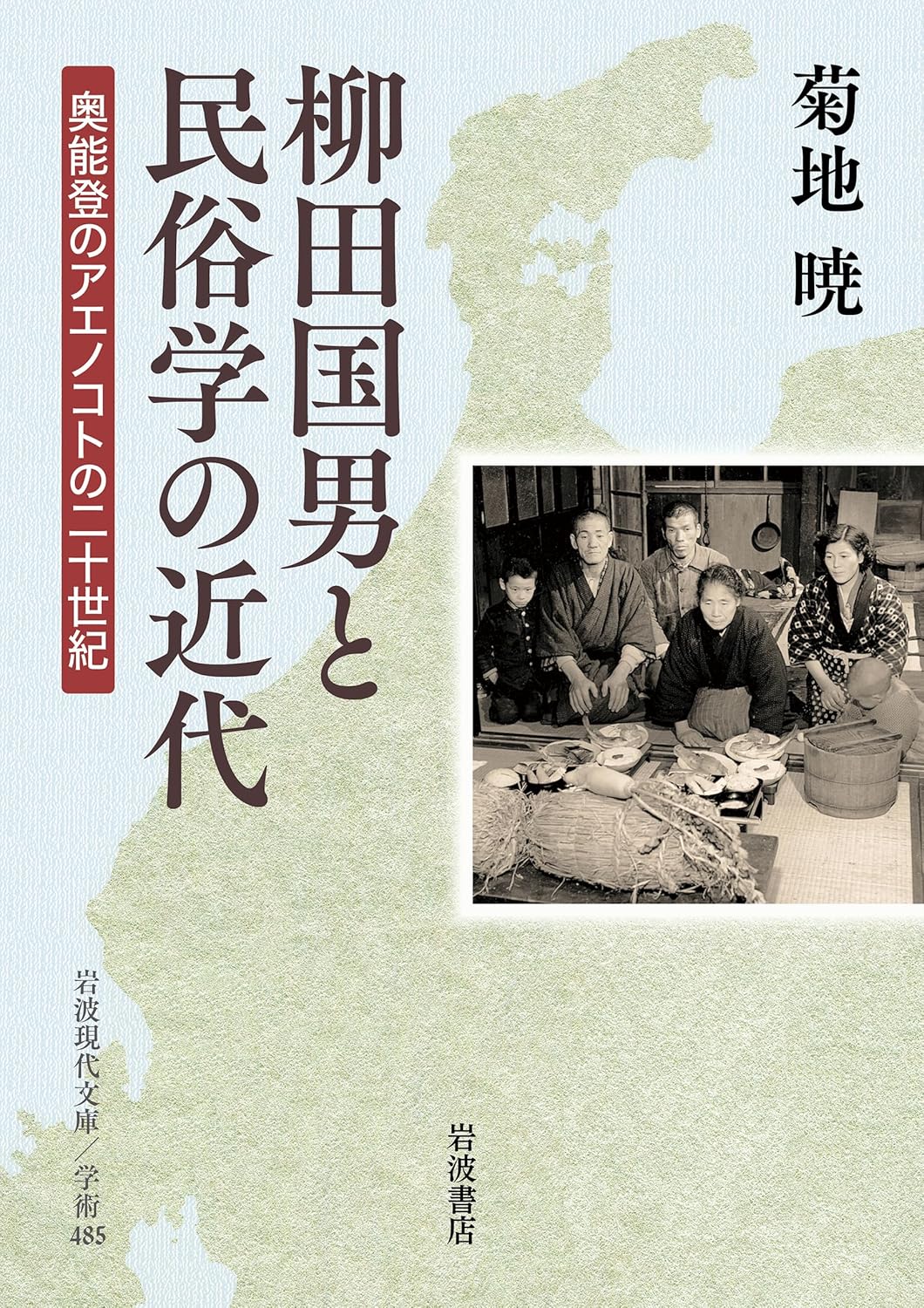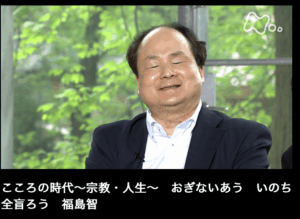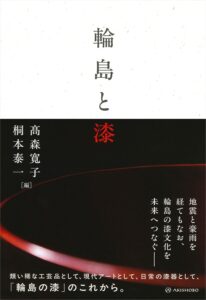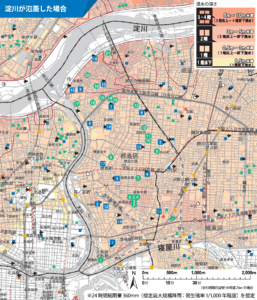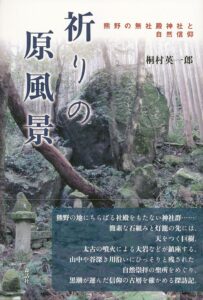■岩波現代文庫
柳田国男がつくりあげた民俗学の実践は、農山漁村の民俗そのものの再発見以上に、ローカルな民俗をいかにしてナショナルなるものに接続させかが課題だった。柳田は、全国各地の民俗学徒を総動員して「日本」を語る共同体をつくりあげた。
そうした「日本の本質という物語」を追うのは刺激的だが、それによって失われたものがあるのではないか。アエノコトはその典型ではないか、ということを筆者は出発点とする。
アエノコトは、毎年12月に田の神様を家に迎えて御馳走や風呂でもてなし、2月にまた田んぼに見送る農耕儀礼だ。
アエノコトが最初に登場する文書は「七浦村志」(1920)で「田祭」「田の神さま」と表記された。「鳳至郡誌」「珠洲郡誌」では「田の神様」という表記が5例、「田の神の祝」「田神の祭礼」「あえのこと」「よいのこと」「あいのこと」が各1例だった。
柳田が当初アエノコトを論じるためにつかった基礎資料は上記と小寺廉吉の報告だけだ。小寺は「田の神の行事」「アイノコト」と呼んだ。
柳田は1934(昭和9)年にはじめてアエノコトに言及した。「あいのこと」は「秋祭と正月の中間」という意味だという説が有力だが、柳田は「私の想像ではアエが正しく、神を饗するアエでは無いかと思ふ」と説いた。たった1例しかない「アエノコト」の表記で、この行事の名称を代表させ、「アエ=饗」「コト=祭」という儀礼像を創出してしまった。
さらに柳田は「田の神は本来的には山と田を往復したものであり、その神格は祖霊である」と論じた。上記の資料にはそんな記述はない。これもまた、日本人の神は祖霊だとする柳田の「固有信仰論」にもとづく「想像」だった。
柳田は「分類語彙」と総称される資料集を刊行する。そこに、「アエノコト」の名を載せて「饗応の祭典」と説明した。全国の資料を集積した柳田が編成した「分類語彙」は、民俗学徒が全国の民俗を比較検討することを可能としたが、一方で、固有信仰論にもとづく柳田の想像物にからめとられることになった。民俗学ではいつしか「アエノコト」が一般名となり、「アエ=饗応」とされた。
戦後、三笠宮と柳田らが主導した「にひなめ研究会」は、民間の農耕行事と宮中の「新嘗祭」の間の稲作民族としての共通性を追求した。アエノコトは両者をつなぐ「民間の新嘗祭」と位置づけられた。そのイメージは奥能登にも環流する。
「とーともかーかも……田んぼで働くだけの人やった。生きているときに、天皇さまのまつりに似ていると知ったら、もったいないと、ありがたがったろうに」
柳田の「至って漠然たる私の仮定説」がいつのまにかアエノコト像となり、それに導かれて調査がすすむことで柳田の言葉を追認した。儀礼像を修正するのではなく、その像を再生産することになった。「日本の本質」という物語を志向することで、地域を見る目を大きくゆがませてしまったのだ。
アエノコトの最初の写真は昭和26年、輪島高校の社会科教諭・四柳嘉孝によってもたらされた。野本吉太郎が祝詞を読みあげる姿だった。この写真は、撮影年も村名も記されないまま多くの雑誌に掲載された。
吉太郎は、柳田の神社の氏子総代だった。神主が戦争に行ったため、小さな神事では吉太郎が神主を代行した。その影響で、神主につくってもらった祝詞をアエノコトで読むようになった。戦争による神主不在という状況が野本家のアエノコトを神道化させた。さらに有名になった写真は、陸軍演習場の落成式にやってきた軍人のために昭和18年に演じた際に撮影されたものだった。
あえのことは昭和51年に「国指定重要無形民俗文化財」になり、61年に「植物公園」の移築古民家で実施されるようになる。本来は夕方の行事だが、テレビ局に合わせるため午前中から催した。
各家の行事は、ブリ1匹は高いから切り身になり、豆腐や油揚、甘酒、里芋などもスーパーで購入する。翌年用の種籾をつめた俵が重要な役割を果たしてきたが、農協が苗の販売をはじめたため、種籾から苗を育てる農家が激減してしまった。
昭和26年の調査時は日取りがまちまちだったが、昭和53年には、12月5日に田の神迎え、2月9日を田の神送りとする日程に収斂した。両日に集中するマスコミ報道や研究者の記述の影響だった。
最近では、棚田ブームやユネスコ無形文化遺産(2009年)指定、「能登の里山里海」の世界農業遺産登録(2011)でアエノコトを集落レベルで復活させる例もでてきている。
戦後、民俗文化財保護制度が整備され、昭和50年に無形民俗文化財の指定制度が確立された際、宮本常一はそれに異を唱えた。「日本民衆の自律的な領域であった民俗への国家的保護」を否定したのだ。「国」の物語づくりを求めた柳田とは正反対だった。だから今も宮本に惹かれるのだろう。