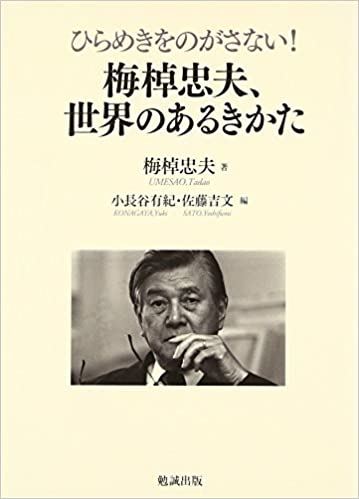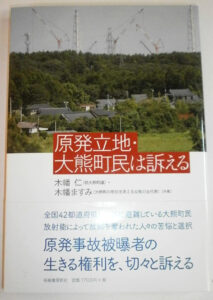■勉誠出版20230501
私が学生時代、梅棹先生は雲の上の人で、2度か3度、講演会などで目にしただけだが、圧倒的な語りに魅了された。
梅棹は「あるきながら、かんがえる」という。彼が世界をどう見て、どのような調査をしていたのか。彼ののこした文章と写真からその断片をつたえる本だというから購入した。
若いころからスケッチが抜群にうまい。探検した先の情景をわかりやすく生き生きとえがく。
移動しつつ調査する旅では、記録はとてつもない手間がかかる。パキスタンからサイゴンまで陸路で走ったり、サハラ砂漠を横断したり…といった苛酷な旅をしながらいとも簡単に写真を見るかのように記録してしまう…ように見える。
でも「いとも簡単」ではないことは、こんな記述からわかる。
--車でタイプライターで記録する。「ノートと鉛筆という方法では、こんな道のわるいところでは字は書けない。タイプライターなら、なんとかかける。暗闇でもうてる。すぐその場でかきつけるのだから、くわしくてまちがいのすくない旅行記録をつくることができる--
工夫と努力によってさりげなく見える記録を必死でのこしていたのだ。
旅をするなかであたらしいなにかを発見するには、観察眼が必要だ。
パキスタンから国境を越えてインドにはいると、数カ月ぶりに豚を「発見」する。イスラム世界ですごしてブタを忘れかけていたことの「発見」だった。イスラム世界とヒンドゥー世界を旅して東洋でも西洋でもない中洋だとかんじる。「文明の生態史観」の序説となる発見だった。
ベトナムのカオダイ教は、各種の宗教統一する真の宗教だと自称していた。植民地時代にはフランス支配に抵抗する軍をもって闘争をしていたにもかかわらず、アメリカが支援する時代になると、封建的な勢力として討伐の対象になり、みずから武装解除して転向する。ラジカルにして、それゆえに抑圧され、屈折しながらも生き延びる新興宗教に梅棹は関心をよせた。
ビルマでは男も女も巻きスカートのロンジーを身につけていた。ロンジーは戦後になってむしろ増えたことや、憲法に固有の服装の愛用という項目があることを梅棹は知る。伝統が近代化をはばんでいるわけではない。ナショナリズムが、植民地体制を脱して近代化するための原理として作用していた。ロンジー美学の確立と浸透こそが、ビルマの近代化の成功のしるしだと観察する。
「その人たちのかたることに、じっと耳をかたむけ、その人たちの人生体験を自分の体験とする。そして、自分のなかでその体験を整理し、くみたてなおすことによって、その人を自分なりに理解し、自分はいちだんと成長をとげる。それが人類学なのである。人類学は、おとなの学問であるとともに、おとなになるための学問である」
この言葉はどこか宮本常一につながる。
「一度モノにした外国語を一生保持してゆこうとかんがえると、たいへんなことになる」から「さびつかせておけばよいのである」という開き直りと、 1日300語の単語をおぼえて1カ月で語学をなんとか実用できるようにする、という実践にも舌を巻いた。