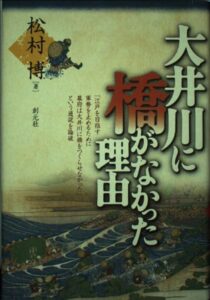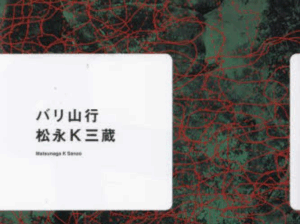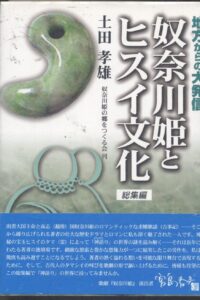■講談社文庫20230924
高群逸枝の自叙伝。途中で亡くなったため、48歳から亡くなる70歳までは夫の橋本憲三が逸枝の日記などをもとにまとめている。「最後の人」の橋本は妻につくした聖人のようだが、この本でははじめ清らかな逸枝を翻弄するエゴイストとしてあらわれる。水と油のように異なるふたりが、紆余曲折のすえに一体化していく過程にひきこまれる。
山の学校の教師の父、母も教養のある人で、同志的で民主的な夫婦だった。
逸枝は父母から「観音の子」とよばれ、毎月の誕生日には、母の料理でお祭りがなされた。逸枝自身も小学校入学までは自分を観音の子と信じ、いじめる子に「あたい観音さまの子よ」と叫んでいた。
川原などにすまい、農具や竹細工、桶修繕などをする山窩もいる時代で、「自由で不屈な人々」と思っていた。
妻問婚が、若い衆の男女関係とし、のこっており、女の家では、顔も知らない忍び男のことを「うちの婿どん」などと黙認していた。そして子どもが生まれそうになるのを機会に嫁入婚となって結ばれた。これは古代の招婿婚のなごりだった。
師範学校は体をこわして退学し、熊本女学校へ。卒業後、女工哀史のような工場に就職したが校長の娘だとばれて4カ月で退社した。
父にならって、一生をへき地教育にささげようと教師になってまもない23歳のとき、当時20歳のK(橋本憲三)とであい恋に落ち、「私はあなたへの永遠の愛を誓います。私に不正な行為があったら、あなたの処分にまかせます。あなたのお手紙はたいせつにしまっています。恋しいあなたよ」という手紙を書いた。Kからは茶化した返事がとどいた。
「この世には永遠というものはありえない。瞬間のみがある。まあ行けるところまで行きましょう。あなたがぼくの手紙をたいせつにしてくれるのはありがたいが、手紙というものは時の拍子で書くものだから、あとで恥をかくから焼いてくれ」
エゴイストのKの言葉に傷つきながら、そんな彼の思いを受容しようと努力する。
感受性の強い逸枝は、釈迦や日蓮、親鸞のような清い尼になることをねがった。そして貧しい人をすくう新聞記者をめざして1917年に教師をやめて熊本にでるが、野暮ったい服装や鈍い物腰や口の重さをみただけで、ていよく断られてしまう。絶望した逸枝は、過去の自分も憲三への鯉も断ちきろうと、1918年6月、四国巡礼にでる。
熊本にもどるとKと同棲をはじめるが、Kは、妻との関係は子育てなどの負担だらけで、そこには恋愛はない。真の恋愛にちかいのは娼婦との関係だけだ……とうそぶく。逸枝は、父母のような永遠恋愛、一体化恋愛をもとめるからKと歯車が合わない。
Kはかんしゃく玉を破裂させて暴力に訴えることも。逸枝は「…さよなら。あなたの小鳥が飛んでいきます。さよなら。私をおゆるしください。私ののこしたものはみんな捨ててください。私は悲しいのです。恋しい人よ」と書き置きして3カ月で実家にもどる。
「Kをして毒舌を吐かせ、わがままを募らせ、暴力をさえふるわせて、救いがたい堕落的人間と化させ、私をしてはこれまたあらゆる悪徳、醜態を露呈させた……」と、Kを堕落させた自分自身を責めた。
そのとき逸枝の心に「感情革命」が起き、従来天上的なものとして描いていた恋愛を地獄図としてとらえた。のどかでうつくしい歌ではなく、破調の短歌をつくるようになった。
吹く風の白、白、白の大揺れに 水は底ひく草木の揺れに
男がひとりじいとみるその目 千仞の闇うしろに積もる
「山の乙女の女体は成熟し、その精神は悲鳴をあげて生き悶え……人生のむざんな露骨な現実への苦悩…山の乙女の私は、あるときはか弱く抵抗し、あるときは進んで対応し、…あるときは打ちたおされて死骸となった。常識も、自己防衛も断絶した」
つまりあらたな恋愛に苦しんだ。
逸枝は東京にでることを決意すると、Kが旅費100円をもってきた。
母は「出世しなはりえ」と言い、「出世します」とこたえて出立した。それが父母との永遠の別れになった。
東京ではどこかに就職しようかと思ったが、偶然、持参していた原稿の出版が決まった。郊外の世田谷の大百姓、軽部仙太郎宅で勉強生活をおくることになった。そこにKがたずねてきて「故郷の南の海岸で1年くらい2人だけでのんびりくらしてみよう」と誘われ、その言葉にほだされて熊本の海辺に8カ月暮らす。妊娠して世田谷にもどったが赤ん坊は死産した。
Kは1923(大正12)年6月、逸枝の友人の夫の紹介で平凡社に入った。創業者の下中弥三郎が会社組織にあらためた時だった。それから3カ月後の9月1日、関東大震災が襲う。
逸枝夫婦のすむ郊外の村にも、「横浜を焼け出された数万の朝鮮人が暴徒化し、こちらへも約200名のものが襲撃しつつある」という噂がながれ、「三軒茶屋では3人の朝鮮人が斬られた」「そこの辻、ここの角で,不逞朝鮮人、不逞日本人が発見され、突き殺された」とつたわってくる。隣人からは「朝鮮人があぶないから、いっしょに集まって、戸外に蚊帳を釣って寝(やす)め」といわれる。
「村の取りしまりたちの狭小な排他主義者であることには驚く。長槍などをかついだり騒ぎまわったりしないで、万一のときは代表者となって先方の人たちと話し合いでもするというぐらいの態度ならたのもしいが、頭から「戦争」腰になっているのだからあいそがつきる。…いわゆる「朝鮮人」をこうまで差別視しているようでは、「独立運動」はむしろ大いに進めてもいい。その煽動者に私がなってもいい……私はもうつくづく日本人がいやになる」と逸枝は日記につづる。
震災被害がおちつくと、あたらしい家を入手する。2人の生活がはじまると逸枝は期待したが、Kは友人を1人2人と無料で寄宿させた。当時のアナキストの若者たちのあいだでは、だれかが家をもてば宿無しの友人が居候してたかのがあたりまえだった。Kの友人が家にのさばり、逸枝は台所の板の間においだされた。
炊事や友人たちのよごれものの洗濯、タバコ屋や酒屋へのつかい、小遣い銭の工面……膨大な家事が逸枝に集中した。路地裏的、梁山泊的な生活に不満げにすると、Kは「家を出てゆけ」といってなぐった。
そして、平凡社が軌道にのり、Kの地位が安定したのをみはからって書きおきをおいて1925年9月19日、居候の青年をつれて家出した。
「恋の駆け落ち」と報じられ、Kが半狂乱でさがしていると新聞で知ると、逸枝はみずから警察に届け出てつれもどされることになった
以来、Kは豹変する。夫にとことんまでついてこようとする逸枝の愛の深さを知ることで、逸枝の希望を優先しようと思うようになり、路地裏生活で体をこわした逸枝のために田園に移住しようと提案する。
1929年に荻窪へ。荻窪の都市化がすすむと東京府荏原郡世田谷町満中在家の軽部家の森にのちに「森の家」とよばれる家をたてた。
「そこは細長い樹木地帯の南端に位置し、南はまるで人通りのない並木道をへだてて畑地、北は森、この森の先は植木園をはさんで稲荷の森につづく。東も森、西は軽部家の1枚にあまる広い畑。その遠近にも森や雑木林が点在し、その間から富士がちょっぴり頭をのぞかせている。
敷地は間口10間、奥行き20間の200坪。……敷地の北寄りにクリーム色をした方形の建物。2階建て上下各3室、延べ約30坪……」
新聞雑誌社をはじめ知友には来訪をことわり、過去のいっさいのグループから離れた。
男女の差が不均等で、婦人が圧迫されるまでの歴史を調べたいと考えて「女性史」にとりくむ。家族制度は国の基だとされ、ごく初歩の民主主義婦人論が、家族制度破壊の名のもとに発売禁止になる状態だった。通説を批判することは国家的反逆とみなされた。
戦争が近づくと、特高に目をつけられ、出版社を通じて警告される。「高天原は高天原以外の何処でもない」とか「皇室の恋愛に触れてはならない」と指摘された。文部省が「国体の本義」をだして、神話を歴史のように解釈することを強要するようになった。1940年には「部落常会」という隣組が発足した。森の家は、警察署や駐在所にマークされた。
そんななかでも、逸枝は最低1日10時間の研究というノルマをみずからに課した。玄関には「面会お断り」の標札をかかげ、執筆依頼にも金がほしいときだけしか応じなかった。
逸枝の研究は家族形態の変化をあきらかにする。 「源氏」のころまでは、男が女の家に結婚後数年通い、その後妻の家に同居していた。その前は、一生男も女も自族にいて、男が通っているだけだった。南北朝(14世紀)ごろまでがそうした招婿婚で、それ以後嫁取式になる。平安時代には嫁姑の同居がないから、嫁姑の民話などは室町以後にしかない。皇室にも江戸末まで「御簾入」婚がのこり、山漁村には今でも招婿婚の遺制がある。
室町から嫁取り婚になると、嫁姑の悲劇や公娼制がおこり、有夫姦は罪悪とされる。離婚は一方敵な追いだし式となった。
「上代は母を氏族の中心とし……私有財産制の発展にともなって、氏族が崩壊し、国家が成立すると、女性の地位は後退し、男性中心の家父長家族制度になる。女性は家婦か娼婦かのいずれかであるほかないが、どちらにしても「性器」以上のものではなくなる。……家父長的な伝統は、実は室町以後の600年の伝統に過ぎない。その前にはのびやかな母性の時代があった。」
フルシチョフの新綱領に共感し、「理想社会の到来を確信したもので、巨大な計画規模を示し、人類を鼓舞している」などと社会主義に希望をいだいた。
逸枝は進歩的でリベラルな人のように思われるが、実はさびしがりで愛情ふかい、よく泣く「女」でもあった。幼いころからの「観音さま」をもちつづけ、60歳をすぎても周囲をやわらかな空気にする「しら玉乙女」のおもかげをのこしていた。
1943年、49歳のころ、憲三が水俣にいって10日間留守にしたときは、1日に何度も「いまどこだろう」「今ごろ下関だろうか」「今夜は夫が車中だから、私も着のままでやすむことにする」と日記にしるす。夫のぬぎすてたどてらでつくった夫の人形に、お茶をつぎ、陰膳をおいて話しかけ、「ではあなた」と声をかけて電気を消して寝る。
鶏を飼い、トンコ、ブーコ、タロコ、ジロコ……と名づける。鶏が死ぬと、「ジロコが死んだ。……庭の花という花をとりつくしてなきがらをうずめ、泣きながら埋葬した」。
純農部落はしだいに住宅が増え、農家もが消え、屋敷に雑木や雑草があるのは森の家だけだ。廃屋同然の森の家は子どもたちから「4丁目の化け物屋敷」とよばれるようになる。
逸枝は病院ぎらいだったが、1964年5月10日、ついに入院する。
おしゃれで、身だしなみよく、発病まで毎日の化粧をかかしたことがなかったから、丁寧に髪をくしけずり、クリームをぬり、足にはソックスをはかせた……。
主治医は病名についてKがたずねても説明してくれないが、百科事典の「腹水」の項からあれこれしらべて、重大な覚悟を要することを察知した。
完全看護の病院で夜は付き添えないことがKのなによりの後悔だった。
「こんな完全看護制の病院でなくて私がいつでもいっしょにそばについていられるところだとよかったけど……」とわびると、「ここではそれができないのね」と自他をいたわるように逸枝はこたえた。
6月7日午前8時に入室すると、逸枝の寝顔の美しさに「彼女は神だ」とKはうたれる。
ヘアトニックを髪にふりかけてブラシですいてやると目をつぶってよろこんだ。また頭部から手や足をさすると、とても気もちがよいという。それから手を握ってくださいとも……
「私がいかにあなたを好きだったか、いつでもあなたが出てくると、私は何もかもすべてを打っちゃって、すっ飛んでいった。私とあなたの愛が『火の国』でこそよくわかるでしょう。『火の国』はもうあなたにあとを委せてよいと思う。もう筋道はできているのだし、あなたは私の何もかもをよく知っているのだから、しまいまで書いて置いてください。本当に私たちは一体になりました」
私……
「私はあなたによって救われてここまできました。無にひとしい私をよく愛してくれました。感謝します」
彼女……
「われわれはほんとうにしあわせでしたね」
私……
「われわれはほんとうにしあわせでした」
そう4時30分しるした。夜9時、帰りのあいさつのとき、逸枝はかたく手をにぎり、「あしたはきっときてください」とつよいことばでいった。
家にもどってまもなく、病院からの連絡をうけ、11時に駆けつけると、「もう彼女の偉大な魂は一生の尊い使命を終え、永遠のねむりにはいっていた」。
逸枝のとくに最後の姿はぼくにとってはRそのものだった。