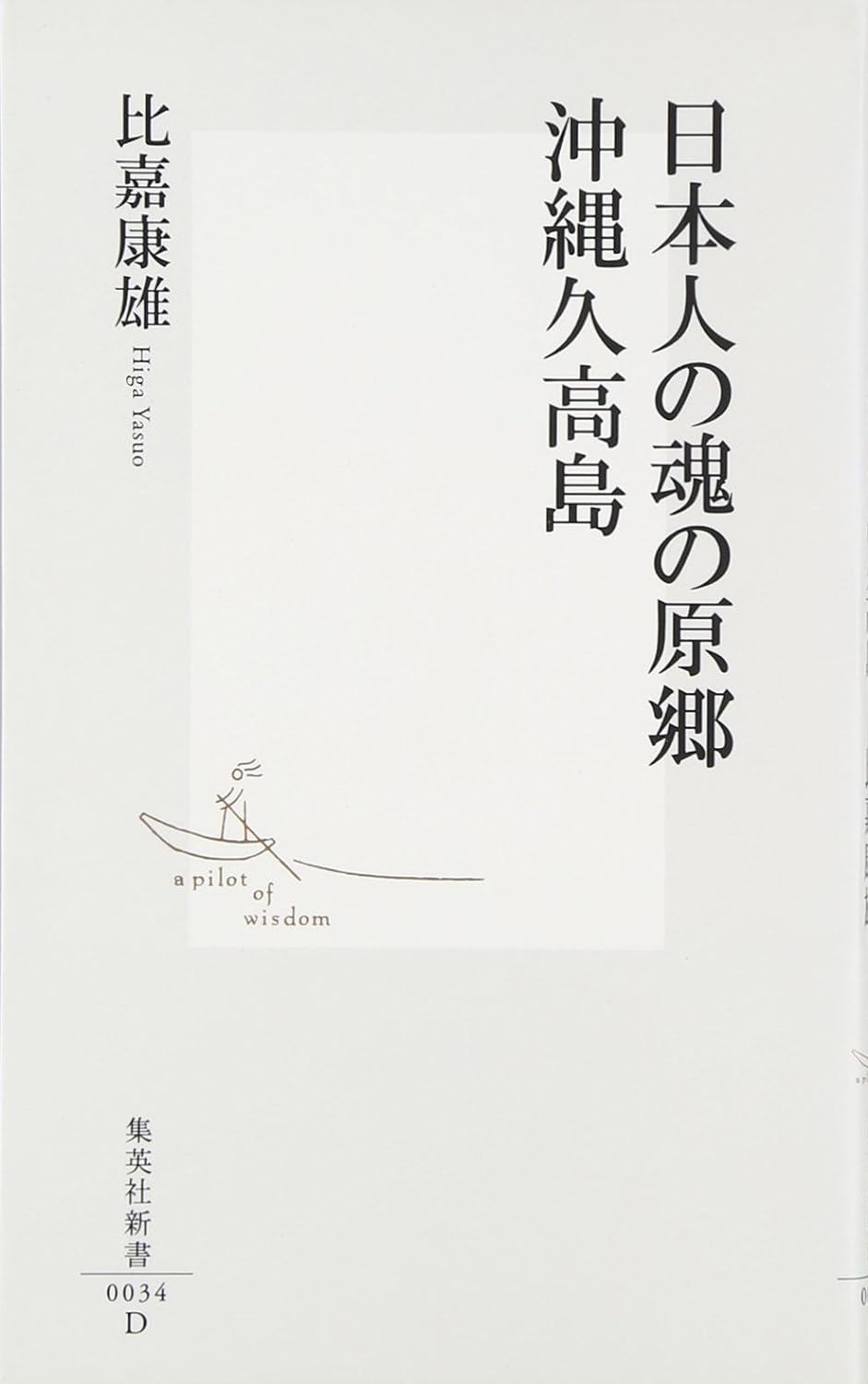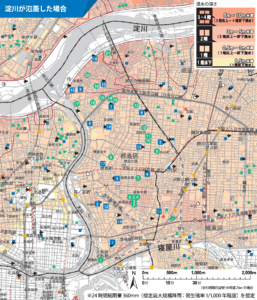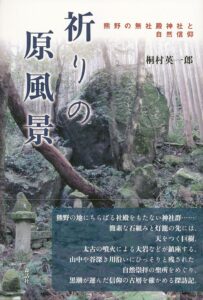■集英社新書 202310
久高島は、隆起珊瑚礁の小島で最高標高は17.1メートルしかない。畑地には石灰岩が露出し、農耕に適していない。水は、雨水をサンゴ石灰岩が吸収し、岩のあいだからしみでる水をためた井泉(西海岸沿いに9カ所、ほかに2カ所)をつかった。
そんな島でなぜ古くからの祭祀が濃厚にのこったのか。不思議な魅力の意味を知りたいと思った。
筆者は100回以上かよいつめ、縄文以来の歴史のなかで、どうやって女性主体の祭祀体型ができたのか、島の宇宙観や世界観はどうなっているのか……をあきらかにしている。
島には2000年前から人がすんでいた。
礁湖イノーで魚介類をとった。力も技術もいらないから、男女差はなかった。だから、子どもを産む母を中心とする社会ができた。母を中心とするグループはクバの森のなかで生活していた。クバの森の聖地は男性は入れないという考えは、この魚介類採取時代の社会のあり方を示している。
祖先の生活の場、魂の鎮まっている場所が御嶽としてのこされた。島の祖母霊がしずまる9つの御嶽のうち水場と対になっているアグルラキとフボー御嶽はあきらかに居住跡だった。
集落は北側から南側にひろがってきた。集落の北側の8家は「古ムトゥ」とよばれ、その下方の18家は「中ムトゥ」とよばれた。
血族レベルの祭祀がおこなわれていたが、第2尚氏王統第3代・尚真王の時代に祭政一致政策としてノロ制度が施行されることで、ムトゥ神中心の信仰から、ノロを中心とするシマ全体を束ねる祭祀に移行した。島々のノロの上位に「三十三君」と称する高級神女を配し、さらに最上位に王妹がなる「聞得大君」が君臨する形だった。
久高島は、東の外間根家(フカマニーヤー)と西のタルガナーの2大ムトゥを中心に家々が集まっていた。ノロ制度施行にあたり、王府任命のノロ職は外間根家からでて外間ノロとなり、タルガナー家からのノロ職はシマノロとし、久髙ノロとなった。それぞれのシマレベルの祭祀場が現在の外間殿と久髙殿だ。ノロの財産として、ノロ地という畑とイラブーの採取権をあたえられていた。
12年に一度のイザイホーは、ノロ制度を受け入れて以後、祭祀団員を組織するためにはじまったが、イザイホーの核心である、祖母霊を孫娘が継承するのは古代からの世界観だった。
かつては岩塊がつらなる西海岸沿いに4カ所の葬場で風葬がなされたが。1966年に岡本太郎らが報道して途絶えた。
死者の魂は、太陽の没する軌道に沿って、地底をくぐりぬけて東方のニラーハラーに行き、また生まれかわってくる。骨は魂の抜け殻であり、近年まで祀られることはなく、葬所は礼拝の対象ではなかった。
寅年の旧暦10月20日に村中いっせいに洗骨をするという風習は、魂が去った後の処理のようなもので、骨を拝むことはなかった。洗骨じたいも近世のことで、昔は放置したままだったらしい。
近世以降中国などから首里王府が導入して庶民まで普及させた亀甲墓や「トートーメー」という位牌は、儒教思想の父系をたどる祖先観にもとづいている。久高島でこの位牌を導入したのは1923年ごろと遅かったため、家庭祭祀は本来の母系の守護神が中心だった。
一方、死体があがらない海難者の魂は、あの世へいけず祟りをおこすと考えられ、毎年、魂鎮めの儀式をしなければならない。マヤの秘密墓地発掘をささえる世界観とおなじだ。魂の存在を肯定する死生観は、古代人からうけつがれてきたものだ。
沖縄は性に開放的なイメージがあるが、島では、婚前婚後をとわず、配偶者以外と性交渉をもつことが浮気とされ、神女になれなかった。イザイホー資格者で浮気をした者はノロに告白し、許しの御願がおこなわれた。浮気を隠してイザイホーに参加した者は、七ツ橋渡りのときに橋から落ちるといわれ、浮気を知っている同僚神女がひじで突き落とす例もあった。
久高島には若い男女の共同野遊びの習俗はない。戦前までは年頃の男女は口をきかず、結婚相手は親がきめた。好きになれない場合、男は出漁先で旅妻をさがし、女は実家に帰った。だから離婚は頻繁だった。
琉球弧の祭祀は、首里王府やヤマト世になったときくずされ、戦争で集落も祭場もこわされ、戦後は生産体系が農業から軍作業などにかわったため消えていった。久高島は古琉球の祭祀を今に伝えているが、イザイホーは1978年でとぎれ、年間27回のシマレベルの祭りのありかたも不確かになってきているという。