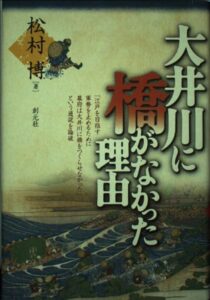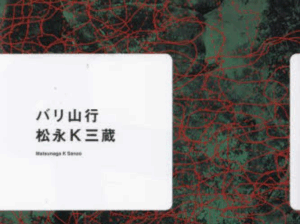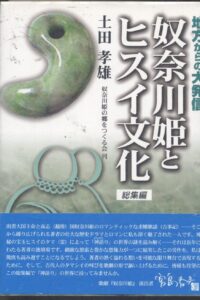ヒンドゥー教は「カースト」と直結して、厳格な身分制度をささえた宗教というイメージだ。
大学時代にインドをおとずれたときは、その「異界」ぶりに圧倒され、興奮と緊張の旅だった。でも短期間の滞在ではヒンドゥーの「差別」のイメージはぬぐえなかった。
日本の「神道」は戦前の独裁的な天皇制をささえたけど、だからといって、神社を詣でる信仰がすべてダメなわけではない。それと同様、ヒンドゥーだって何億もの人が信じているということはなにか「プラス」があるはずだーー。
学生時代からそう思いつつも、その謎を解こうとはしてこなかった。
ヒンドゥーのプラス面を知りたくて特別展にでかけることにした。

ヒンドゥーには多くの神が登場する。もっとも高い地位にあるのが、ヴィシュヌ神とシヴァ神だ。ヴィシュヌ神は10の化身をもち、7番目のラーマと、8番目のクリシュナがよく知られている。
インドの山奥で修行した「レインボーマン」は「火の化身」「水の化身」といった7つの化身に変身する。ヴィシュヌ神から着想を得ていたんだ、とはじめて知った。
シヴァは男性器の形で造形される。その上に牛乳をたらしたりするらしい。なかなか淫靡だ。象の形をしたガネーシャや猨顔の神など、ヒンドゥーにはさまざまな神像がある。
ヒンドゥーの教えでは、バクディー(信愛)という形で、神に熱烈な愛をささげることで、神と一体化して解脱の境地に達せられる。人間の「愛」の対象として、おなじ地平に神々がいるのだ。だから、神像をあざやかな衣装でかざりたて、にぎやかな楽器や歌をともなうのだ。
19世紀にはドイツの印刷業者が神像を印刷してインドでもうけようとした。20世紀前半には日本製のタイルや陶器の神像も流通した。ステッカーやカレンダー、タバコ、マッチ……神像はさまざまな商品になっている。
ヒンドゥーの神々は、高い壇の上にまつられるのではなく、身近にまじわる存在だ。「わたし」の右にも左にもうごめいていて、こちらから愛をささげればそれにこたえてくれる。特別展の企画者はそれを「交感する神と人」と表現する。日々、神々をかんじていきられるとしたら、それはとても幸せなことなのかもしれない。
ただ、ぼくが以前から抱いていた疑問はさらに深まった。それほど身近な神々が、なぜ厳格な身分制をささえたのか? そこにはどんな意味があるのか? 今回の特別展では答えは見つけられなかった。