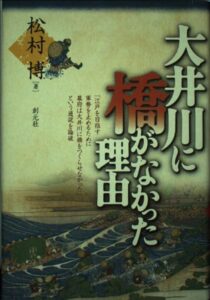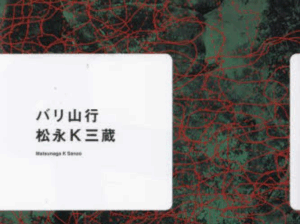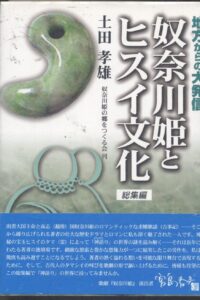■春秋社 20231119
民俗学には興味があるけど、それが今に生きる知恵としてどういう形で生かせるのか、と疑問に思ってきた。この題名を見たら、買うしかなかった。つい最近亡くなった石牟礼道子から、日本の民俗学の原点である柳田国男まで、さかのぼって紹介している。
私は1990年に新聞社の地方支局に配属されて、「ムラ歩き」をするようになった。まだ当時は、保守政治の基盤としての農協が力をもち、米輸入自由化にたいして、トラクターでデモをしていた。
母の実家での祖父母の葬式では、集落の人たちが「ゆい」の形でごちそうをつくり、「野辺送り」の行列で墓におくった。
ところが2000年代のいとこの葬儀は葬儀場でいとなまれた。
2002年から平成の合併の取材で愛媛の農山村を歩くと、農協はかつての組織力を失っていた。でも、生業とともにあった農家の豊かな知恵にはまだふれることができた。
2012年から能登半島にすむと、農村共同体がくずれ、棚田が荒れ、祭りは縮小し……「ムラ」のしばりがゆるむことで空白のキャンバスができて、Iターンの若者が生き生きと活動していた。
こうした流れはまさに「ムラの終焉」を意味していたのだ。そのことがこの本でよくわかった。
14世紀以来つづいたムラ(惣村)が消える、文明の大転換機に直面している。 「民俗学という学知は、成熟への階梯をたどることなく、若くして老いてしまったのではないか……」と筆者はつづる。ムラが伝授してきた「民俗知」はこの時代にどう生きるのか? はっきりした答えはない。でも筆者がムラを歩きつづけるという行動のなかに、考える端緒のようなものがあるような気がする。歩くことからしか現実は見えないし、現実をかえる力も見だせないのだろう。
□石牟礼道子
島原の乱がテーマの「春の城」の前半は、島原・天草地方の民俗誌の繊細な記録だ。「苦界浄土」でも、水俣病の不幸以前の地域共同体の日常を丹念にえがいた。
「西南役伝説」で、百姓は「西郷戦争は嬉しかった」という。「上が弱うなって貰わにゃ、百姓ん世はあけん」と。そして、第2次大戦がもたらした大地主からの土地解放を喜んだ。
民俗学は、日常の暮らしだけに関心を集約するが。石牟礼文学は、「日常」と、水俣病のような「非日常」も同時にえがく。著者は石牟礼に「民俗学」の限界をこえるありかたをみている。
石牟礼は、人間の言葉が言霊をもっているのではなく、言霊自身が宿るところを人間に借りている、と考える。理性ではなく「霊的なもの」が言葉をうみだすのだ。
「渚」の評価もなるほどと思った。近代は、人と自然との境界にある渚や浜辺、潟などを犠牲にして、経済的に発展してきた。有機水銀が垂れ流された水俣の海と、汚染された東京湾や福島の海も「渚」の喪失が前提となっていた。
□岡本太郎
小学校で、派手な縄文土器よりもシンプルな弥生土器のほうが「上」と教えられたが、縄文土器のほうが楽しかった。
予定調和をたっとぶ弥生以降の日本人の美意識を太郎は批判し、縄文土器のような破調の美学を評価した。彼が縄文の美を「発見」した。私の子どものころの感性はただしかったのだと、太郎によって知らされた。
太郎にとっては、縄文と沖縄が根源的な発見だったという。
中尊寺の守り刀の柄の飾りに縄文の気配をかんじとり、縄文やアイヌの「北の文化」と、弥生やヤマトの「西の文化」とのあいだにひき裂かれた東北に「奇妙にズレた二つの異質の舌ざわり」を見だす。
太郎は、啄木や宮沢賢治を評価しなかった。
「啄木なんて発想は単純だし、詩とはいえない。通俗的な感傷を区切りをつけて説明しているにすぎない。だから……できのわるい中学生あたりにもわかりやすく、奇妙に感激したりするけれども、あのいやったらしさ。まさに現代歌謡曲調の草分けだ」
啄木や賢治の詩に感動していた私はまさに「できのわるい中学生」だった。
イタコは「コジキとおんなじ」と忌み嫌われているが、ハレの場では神や死霊の声をとりつぐ存在となる。不浄なるものは、ときに逆転して神聖へとなりあがる。欧州の人類学の素養があったからそれを感知することができたという。
パリ万博には、ピカソの「ゲルニカ」と、民族学の博物館の「ミュゼ・ド・ロンム」があった。これをもとに、大阪万博では太陽の塔と民族学博物館を太郎が中心になって構想した。太郎にとって万博は祭りであり、「ベラボーなもの」として神々しく鎮座する存在として太陽の塔が位置づけられた。大阪でふたたび万博をひらくというけれど、太郎のような哲学や思想のかけらもない。あるのはカネと利権だけ。1970年とくらべるとよくわかる。
□網野善彦
網野は始原の場所に,<無縁><公界><楽>という私有も隷属もない平等の原理に浸された至福の平等社会を想定する。
無縁という言葉は貧しいという意味だが、中世社会では一時期にせよ、無権利で貧しいがゆえに自由であるという積極的な価値をもっていた。
共同体の秩序原理としての<有主・有縁・所有>にたいして、共同体の外部に生きる者をささえる<無主・無縁・無所有>の原理を対置した。
その原理がいきる「原始の野性」に満ちた時代として、網野は中世前期の世界をえがいた。
殺生を悪とする世界は農業を基盤とし、「悪」に親近感をもち「猛悪」をほめたたえる世界は、農業以外の生業に基礎をおいている。ふたつの見方が併存していたのは、この時期の社会が、まだ農業的社会として成熟しきっていなかったからだと考える。
南北朝以前には、異類異形の者らがある意味で聖なる存在だった。聖から穢・賤へと転換をとげる結節点に出現したのが、異形の王権としての後醍醐だった。後醍醐が敗れた以降は農業的社会が圧倒するようになる。
自然に圧倒されきっている原始の人類には、「無縁」「無主」も「有縁」「有主」も未分化だった。「無縁」の原理はそこから自らを区別する形であらわれる。同時に「無縁」の対立物である「有縁」「有主」も登場する。人類史のはじまりに、都市的な場/ムラ的な場が、すでに対をなして一気に登場したのではないか、という。
柳田国男は「はじめに祖霊ありき」「はじめにイエやムラありき」と考えた。それは有主・有縁の世界へとつながる。折口信夫は、「はじめにマレビトありき」「はじめにイエやムラの外ありき」が原風景だ。それは無主・無縁の世界につらなる。(「祖霊・マレビト論争」)
網野の「無縁・公界・楽」は折口にちかい。
ムラの内なる「方言」で語られる昔話にたいして、説経師や盲僧ら芸能をたずさえてわたりあるく人々は「共通語」による語りを必要とした。遍歴する芸能民たちは、文字社会の均質化に大きな寄与をした……という指摘も新鮮だった。
□宮本常一
宮本常一の本を読むと、故郷の周防大島での百姓の経験が彼の基盤になっていることがよくわかる。生活の場に生業が存在しない都市でそだった私には宮本のような百姓としての基盤がない。そのことにある種の劣等感をかんじてきた。
筆者は宮本を、故郷の延長線上において、あらゆる事物を観察していた民民俗学者と位置づける。そして「故郷の延長線上において、……」という知の作法が不可能と化していく時代のなかで、その予感を受け止めながら、あくまで「故郷を失っていない」という幸福を演じつづけてきたという。
数百年つづいてきたムラ社会が崩壊する時代だからこそ、宮本の百姓としての知が光芒をはなったのだ。
柳田や宮本が最近も再評価される背景には、高度経済成長以前の日本社会にたいするノスタルジーがあるという。
宮本は1950年代半ばから、民俗的事象を整理してならべる民俗学に懐疑をいだき、「民俗誌」より「生活誌」を重視するようになる。
実は明治・大正期の柳田は、平民はいかに生活してきたかを記述する「生活誌」の大切さを説いていたが、昭和10年以降の柳田の「民俗学」は、生活誌の記述といった側面は切り捨ててしまっていた。
宮本は「風景のよいといわれるところに住む人はどこでも貧しかった」と指摘する。人間は、生活のために二次的な自然をつくりだしたが、その風景を楽しむことはなかった。それが変貌するのは、観光という第3のテーマが浮上してきたからだ。宮本によれば、昔の上流階級の人々の自然鑑賞的な態度が、一般人のあいだにひろがって観光開発へと展開した。
地域の風景はそこに暮らす人たちがつくるものであり、よそ者だけを楽しませるのではなく、地域の人々の生活を豊かにするような風景をつくることが大切ではないか……。自然を鑑賞の対象とする態度をこばみ、地域の生活を豊かにするための風景をつくることを志向していた。
□柳田国男
「村の協同の一番古い形」としてユイがあり、それは農耕以上に、漁労と狩猟にのこされてきた。漁獲物は浜で分配が終わるまでは「まだ何人の私有とも認められなかった」。由比や手結という地名は、いずれも協同作業としての地引網漁に適した広い浦辺だった。
山野は入会地で、困窮した人々が食いつなぐために働く場所となり、「焼畑・切替畠の一作ずつの利用」が貧しき人々に許されていた。「無主・無縁」であった「共有林野」が分割・譲渡されることで「固有の共産制度」が失われ、福祉という「慈善と救助」が導入されねばならなくなったという。
柳田は、文献のみを担保とした歴史学への痛烈な批判者だった。一方で彼は、信仰や魂といった心意の伝承を重視し、モノにたいして冷淡だった。それが、柳宗悦の民芸運動や、渋沢敬三や日本常民文化研究所などの民具研究にたいする批判となった。今でも柳田の系譜をひく民俗学者たちのなかには、モノに冷淡で、心の伝承に関心を寄せる傾きが強いという。
明治・大正期の柳田は、ヤマビトとよんだ、先住異族の末裔の消息をもとめ、多元的な列島の民族史を構想していた。毛坊主や巫女などの漂泊する人々や被差別の民にも関心をよせた。
しかし、巫女や毛坊主のいる農村生活史の探究は、大正10年前後、差別や天皇制とのからみのなかで姿を消す。昭和3,4年を境として山人への関心が姿を消し、昭和10年前後、民俗学の体系化が本格的に進められ、民史学としての民俗学となっていった。
南方熊楠は「郷土研究」とはフォークロア=民俗学のことだと考えた。それにたいして柳田は「民俗学は余分の道楽」であり、「郷土研究」はルーラル・エコノミー=農村生活史のための雑誌であると応じた。それによって2人の関係は一気に破綻したという。欧米のフォークロアを範型とした南方の「民俗学」をしりぞけたが、その後、その民俗学をとりこみながら、民間伝承=民俗学へと着地することになった。
稲作中心史観にとらわれた柳田の民俗学にたいして、マージナルな色合いの濃い、漁村のフォークロアに光を当てたのが渋沢や宮本、網野だった。
□柳田と折口
柳田は、列島の社会の文化的基層をつくったのは、稲とイエにまつわる固有信仰をもって渡来した種族であり、米をもって祖神を祀る種族が統治民族つまり「日本人」だと考えた。「はじめにイエありき、個々のイエが祀る神=祖霊ありき」というのが柳田の信仰論の核だった。
折口は、障がいの多い時代から多くの人々が旅をしたのは、神の教えを伝播するためであり、マレビトが、村から村へ遍歴してあるき神の教えを伝えたと考えた。「はじめにムラありき、ムラを訪れる神=マレビトありき」がそれが折口の思考の核だった。折口こそが、民俗学の名のもとに結晶した柳田の後期思想にたいする根底からの批判者だった。
□記憶という問題系
記憶とは、体験/証言/記憶の三位一体の様相をしめすとともに、時系列的である。たとえば戦争の記憶は、最初は「体験者」、次に「証言」、そして証言者がへっていくと「記憶」が中心をになうように鳴る。
筆者は1990年代、東北のムラを聞き書きして歩きながら、ムラが終焉をむかえ「記憶の時代」がはじまりつつあることを実感した。
1960年代後半、宮本常一は「もはや古老からの聞き書きの時代は終わった」としるしたが、そうした予感は、高度経済成長期から1980年代のバブル経済をへて、1990年代のはじめに現実と化した。
ムラはいま終焉の時代を迎えつつある。
いまは山そのものを生業の基盤とする人はほとんどおらず、木挽きも狩猟も焼畑も、断片的なものとして残存するだけ。村人の大半はサラリーマンだから、隣家と「何カ月も会ってないな」ということがおきる。ムラは、居住の場/生業の場だったが、生業の場としての要素を失ってしまった。
生業から切断されたムラは、都市のニュータウンと変わりがない。
また、ある季節や週末だけムラにすむ……というのも増えている。ムラ=定住中心主義という形態がくずれ、漂流をはじめているのだ。
ムラは生業から切断され、定住の場としての意味をも失いかけている。そこではユイは稀薄になり、ムラは相互扶助の場でなくなっている。村八分などの異端排除のシステムの大半も壊れてしまった。
「血の通った伝統のなかに、物言わぬ習慣のなかに、古来の反復のなかに、生きられてあった過去が失われようとしている。1990年代のムラ歩きでは、太古の昔からある(かのような幻想に包まれながら、時代ごとに紡がれてあった)アイデンティティの絆が、そこかしこで断ち切られる現場に立ち会うことになった」