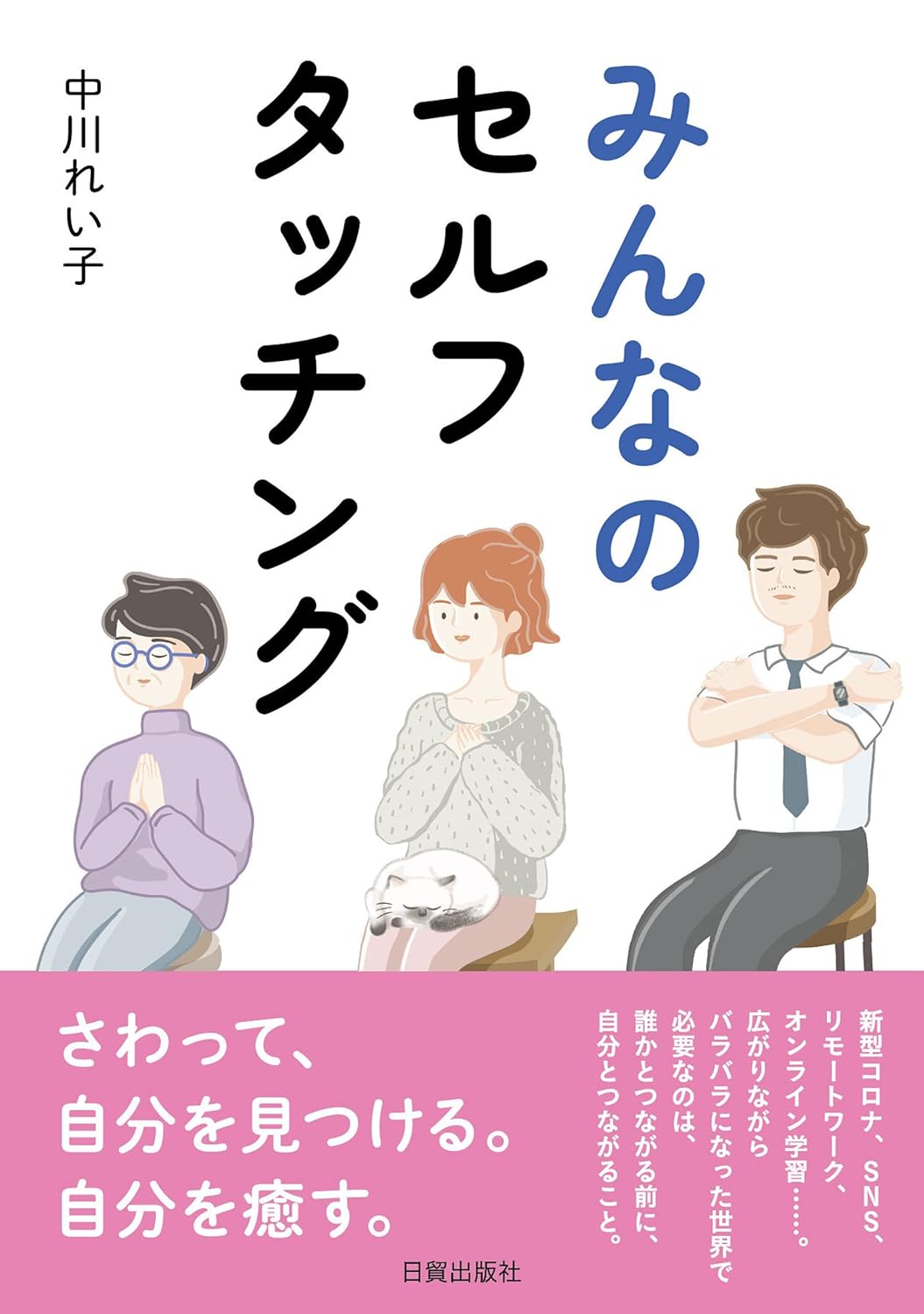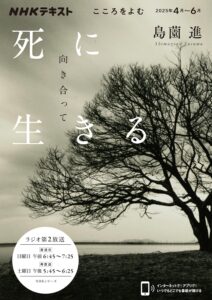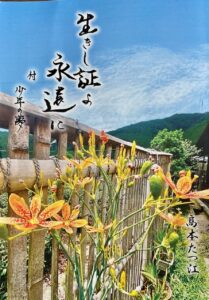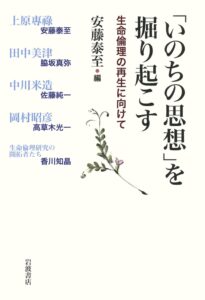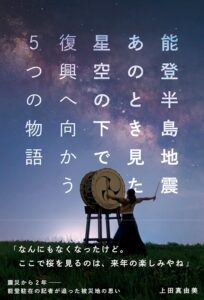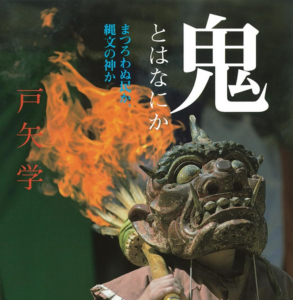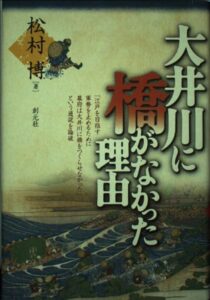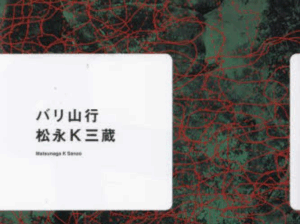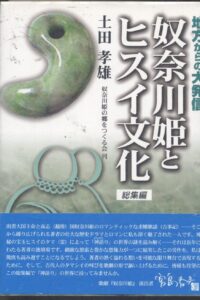■日貿出版社250410
阪神淡路大震災で「人と人が寄り添うことが力になる」と実感し、「タッチケア」の活動をはじめ、東日本大震災では、タッチケアの手法をまとめた小冊子被災地へ届けた。
たが、新型コロナのパンデミックで「タッチ」が不可能になった。そこで自分をタッチすることでケアする活動をはじめた。
手のひら全体でやさしく肘を包む。あごを手のひらで軽く包むようにふれる。首は手のひらの温度を伝えるイメージでやさしくさわる。
赤ちゃんをあやすようにゆっくりしたテンポで、両手で軽くからだをタッピングすると心地よく眠くなる。逆に速度をあげて、バン・バン・バンとタッピングすると目がさめる……。
大地とつながる「グラウンディング」は、自分のからだの重みを大地にゆだね、最小限の力でたてるポジションを見つける。うまくいくと「重力=地球の力」と親しむことで「軽さ」を実感できる。
心臓の上に両手をあてて、呼吸や鼓動をとおして「ゆらぎ」を感じることで、自分自身が「今・ここ」で生きて在ることに思いを馳せる。自分の肩を抱く「セルフハグ」も心を落ち着かせる効果がある。
本を読みながらやってみると、気のせいかもしれないけど、心地よいような気がする。
欧米ではがん患者を対象に、タッチケアで不安や痛みを緩和しているという。
人間の意識のベクトルは「外側」へと向かいやすい。「からだにふれて感じる」をくりかえすことで、ベクトルを内に向けて、「自分自身がまるごとひとつである」と意識する。その身体感覚を通じて、「今・ここ」に在ることに気づく……という。
宗教儀式で手を組んで祈ったり自分の胸に手を当てたりするのも、からだの内部に意識がむかわせて、心の状態をクリアにして、自分自身を再発見するという意味があるという。
瞑想やヨガ、マインドフルネスと効果は似ているのだろうけど、精神力で集中するよりも、実際に「さわる」ほうがわかりやすい。
心の疲れを心や頭の働きで対処するのではなく「身体」からケアするというのは大切だなと思えた。