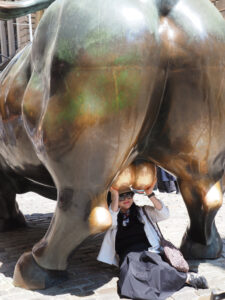ふたたびMETへ。今回は丸一日みるつもりで10時すぎに入館した。前回はローマ帝国がキリスト教をする公認前で終わったから、まずは中世のコーナーからみはじめた。 ゴシックとルネサンス、後期バロック、フランスデコラティブアート、産業革命などの不安の時代を背景としたパリやイタリアでの復古調……。それぞれどんな特徴とちがいがあるのかはっきり理解できなかった
「ヨーロッパの絵画1300~1800」というコーナーにうつってがぜんおもしろくなった。
15世紀より前は聖人や宗教が題材で、個人の肖像は1450年ごろから広まりはじめる。肖像画の誕生がルネサンスのはじまり、という。
初期オランダの絵画は、1400年代に経済が発展して、画家をやしなうパトロンがふえたことによる。
神聖ローマはドイツ王のオットー1世の即位(962年)からはじまり、16世紀にハプスブルク家が皇帝位を独占して全盛時代をむかえる。1500年代、生首をもつ美女などえぐい絵がえがかれた。

イタリアでは1500年ごろラファエロらが活躍する。

オランダでは17世紀、ルーベンス(1577〜1640)が高度な技術で聖書や神話の世界を描いた。「フランダースの犬」のネロがあこがれたのは、聖母マリアやイエスの絵だった。

80年戦争でスペインからオランダが独立(1648年)すると、その繁栄がアートを刺激する。フェルメール(1632〜75)は写実的だが、たんなる写生ではなく、信仰や神話のさまざまな意味をこめている。近代的な技術と、古くからの物語を絶妙なバランスであわせもつのが彼の絵の魅力なのかもしれない。
風景画は16世紀に誕生し、当初は風景をとおして、聖書や神話、死後の世界を表現していた。オランダの画家たちは独立闘争を通してナショナリズムが高まり、自国の美しい風景を描いた。

レンブラントは「夜警」が有名だが、肖像で有名とは知らなかった。
17世紀の肖像画は、王族だけでなく、経済人や官僚らの権力者の肖像も描かれるようになる。

スペインの肖像画(ベラスケス)は、外交や政治同盟の際の贈りものにもつかわれた。

スペインのエルグレコ(1541〜1614)の抽象的な絵は、当時はうけなかったが、300年後のピカソやセザンヌといったモダニズムにつながっているという。たしかに彼の絵は、印象派やピカソと通じるものがある。
16世紀の宗教改革によって、北ヨーロッパでは宗教画や教会などの伝統的パトロンが衰退した。北ヨーロッパを中心に1560年ごろから、聖書や神話だけでなく、日常生活も描かれるようになる。

「魚市場」(1568)、「台所」(1620ごろ)などの日常生活を描くことがふえた。
以前に読んだ「教養としてのロンドン・ナショナル・ギャラリー」を思いだした。美術史を勉強するには最高のコーナーだった。
つぎに「19世紀と20世紀」コーナーにうつった。
フランス革命で絵画も大きく変化した。

Degas(ドガ)は(1834〜1917)女性の裸などが抜群にうまい。

イギリスのターナー(1775〜1851)の霧にけむったような風景画も魅力的だ。

宗教や神話から離脱することで風景の描写がどんどん緻密になっていく。 透けた服を着て半裸で歩く女はその頂点のような作品だ(19世紀)。
でもその流れのなかでなにかを失っているようにもみえる。物象化がすすんで、魂とか霊とか心のようなものが抜け落ちて写真とかわらなくなってきているような気がする。

そこに「印象派」が登場する。ルノワールのやわらかな女性の絵は正確な写実というより漫画にもつながるかわいさがかんじられる。
思わず「いいな」と思ったうつろな表情の男の絵「The actor」はピカソだった。


マチスやセザンヌ、ゴッホやゴーギャン……それぞれの作品をならべた部屋がつづく。



ゴッホの色彩はのみこまれるような迫力があるし、ゴーギャンの南の島の絵は、ハイチやニカラグアの素朴画との共通点をかんじる。

モネのスイレンなどの作品は何度みても透明感にすいこまれる。
20世紀の「印象派」やピカソなどの流れは、写実主義によって一度うしなってしまった魂のようなものをとりもどそうとしていたのかなと思えた。
■アジアセクション
ちょっとだけのぞいたが、膨大なコレクションにびっくり。
石仏などで中国の歴史をたどり、絵巻や仏像で日本のアートを代表させる。インドの仏像は彫りが深くてエキゾチックで、ヒンドゥーの神々はエロくて生命のエネルギーがみなぎっている。
ざっと流したのにあっという間に17時前になってしまった。
2日かけたのに全体の半分も見られなかった。