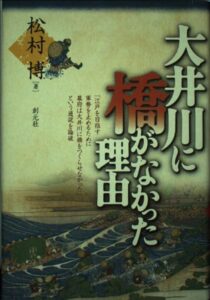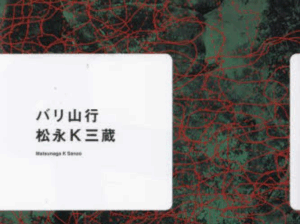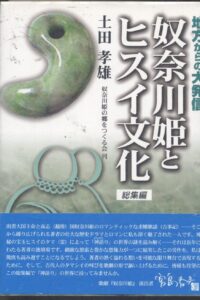■弦書房
かつて江戸時代は封建的な遅れた体制だと評価されていたのにたいし、最近の江戸ブームでは、江戸時代の近代に通じる部分をとりだして「実は意外に近代的だった」と評する。どちらも近代を基準に過去を評価している。
渡辺は、江戸は、もう二度と引き返せない、明治以降の日本人が滅ぼしてしまった世界であるからこそおもしろい、という立場だ。
失ってしまった江戸の姿を「逝きし世の面影」では外国人ののこした文献をもとにえがいたが、この本は江戸時代の人びとがのこした記録によってえがいている。
温泉宿で自分の部屋がきまると、両隣の客にあいさつにでむき、おなじ宿の客はみな友だちになった。人びとは赤児のように純真きわまりない感情をもち、旅先で病人を見かけるときまって声をかけ、知的な障害者にも生きる空間を与えた。江戸人の情愛の深さは、昭和になっても庶民の心情のうちにのこっていた。
たとえば能登のお接待や、人へのやさしさはそのなごりだろう。「精薄」とか「きちがい」とかよばれる人が昭和40年代までは近所を歩いていた。ステテコに腹巻きで歩く人もふつうで「裸」も許容されていた。それらはたぶん「江戸」のなごりだったのだろう。
幕末の外国人は、日本人の宗教心の薄さ、とくに武士階級の「無神論」に注目した。だが迷信・俗信は否定する一方で、よほど知的な人であっても、狐狸などの超自然的現象を疑うことはなかった。近世の科学的探究心は、あの世とこの世が交流するような心性を排除するものではなかった。江戸時代の人びとにとって世俗化とは、不思議と驚異にみちたコスモスの発見でもあった。
江戸時代の人びとには、中世のように死と生を徹底して見すえる態度はなく、死を気軽なものとみなし、とことんはぐらかしていた。「野暮天」がはぐらかしのためのキーワードだった。小西来山(17世紀後半の俳人)の辞世は「来山はうまれた咎で死ぬるなりそれでうらみも何もかもなし」だった。 明日を思い煩うゆとりもなく、その日を無事に過ごして、ただ一合の寝酒があれば満足する。そして最後は、観念したようにさっぱりと死を受け入れた。
仕事は労役ではなく生命活動そのものだった。家業は近代の「職業」とは異なる。運命にあたえられたその人の存在形態であって、家業に精を出すのは生命活動そのものだった。
だから「家」はおのれの生命活動によろこびをあたえる根源だった。家が存続するというのは、生命が継がれるということだった。
鈴木牧之は、生涯6人の妻をめとり、4人を離別した。
江戸期にはあらゆる家は家業をもち、家が経営体である以上、嫁という新加入者は審査され教育される。あわなければ離婚した。当時、離婚歴は再婚の障害にはならなかった。庶民の女の場合、一度の結婚で自分の運命をきめるのではなく、いくつか試みて、自分に合った家に落ち着くというのが賢明で自主的な生き方だった。 結婚を人格的結合とみなし、その核心に情熱的な恋愛を仮定するのは近代の発見であり、それゆえに近代人は愛の幻想にとらわれて苦しむことになった。
村尾嘉陵は50歳すぎに妻をなくしたあと諸国を歩きまわり、72歳のとき、薄明から午後6時までかかって60キロを歩き通した。平均時速5キロだ。「歩く江戸の旅人たち」という本に「多い日は1日60~70キロにも歩いた」「旅人にとって無理のない歩行距離の上限は50キロ程度」と書いてあったのを思いだした。現代ならばアスリートなみの健脚だ。
旅の記録の筆者は地域ごとの風俗のちがいにおどろいている。「娘小児に至るまで裸にて、近郷の一里ばかりある所へ用事ありて行くにも裸身にて……」。京の女が立ち小便することに江戸からの旅人は驚いた。
性のタブーは今よりよほど少なかった。
岩手の胆沢郡小田代にある十一面観音菩薩の祭は、若い男女たちが自由に交わることが許された祭りだった(菅江真澄)で、「出羽の温海では、娘のいる家ではみな娘を遊女に出すのを習いとして」いた。
天草では、男は外にでて、老人と女子ばかりだから、他国の船がよれば、女が家につれていった。男鹿半島の戸賀の浦では、老若を問わず、女たちが暗闇の船宿に入って相手をした。
実はそれに似た世界は昭和50年ごろまで残っていた、と能登半島で聞いたのを思い出した。