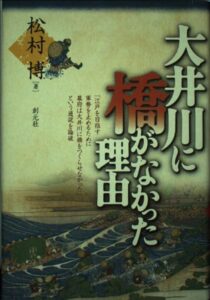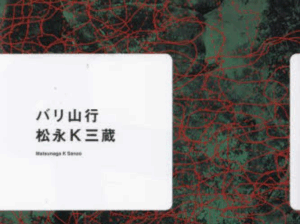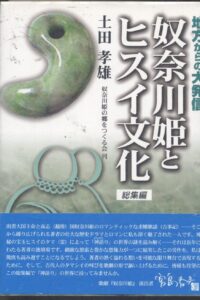■20240518
「芸術は爆発だ」というヘンなおじさん、というのがぼくらの子どものころの岡本太郎のイメージだった。
戦前にマルセル・モースに師事して民族学をまなび、帰納的で具体的な姻族学と、演繹的で抽象な芸術の双方で創的な世界をつくりあげた天才だったということがよくわかる。
太郎は戦前のパリで抽象芸術の運動にかかわる。
人間の思考、とくに芸術は、自分の主観からこうだ、と自己中心的に演繹的に決めていく。一方、ミューゼ・ド・ロンムでであった民族学は、自分を捨てて主観的な判断を排除して、ひたすら帰納的に結論を導きだす。太郎は、世界観を帰納的に見直してつくりあげることに感動した。芸術の演繹と、民族学の帰納という2つの精神的な方向のぶつかりあいのポイントに、自分の本当の生き方を発見すべきではないかと直観する。
岡本は辛気くさい日本の伝統文化に興味をもてなかったが、1951年に東京国立博物館で見た縄文土器に仰天し、「たんに日本、そして民族にたいしてだけでなく、もっと根源的な、人間にたいする感動と信頼感」を感じる。
大阪万博の際、太郎の発案で太陽の塔の地下に人類の原点を示すという狙いから、世界の民族資料約2500点が収集展示された。京大の梅棹忠夫と東大の泉靖一と協力して1968から69年にかけて収集した。そのコレクションはその後、民博に寄贈された。
岡本は、万博の準備段階から「人類は進歩していない」と公言してはばからなかった。
「近代主義的な機械でつくったようなものばかりならべて、得意になって、「進歩と調和」とかいっていた。ぼくは……人間は進歩していない、逆に破滅にむかっているとおもう。調和といってごまかすよりも、むしろ純粋に闘いあわなきゃなあないというのがぼくの主義で、モダンなものに対して反対なものをつきだした」
それが、丹下健三がつくった巨大なモダニズム建築の神殿に穴をあける「太陽の塔」のコンセプトだった。1970年当時、万博の主役のひとりは丹下健三であり、岡本は脇役もしくは道化でしかなかったが、半世紀をへて、丹下の神殿は消え、太陽の塔は2018年に内部をととのえ復活した。両者の役どころは逆転したのだった。