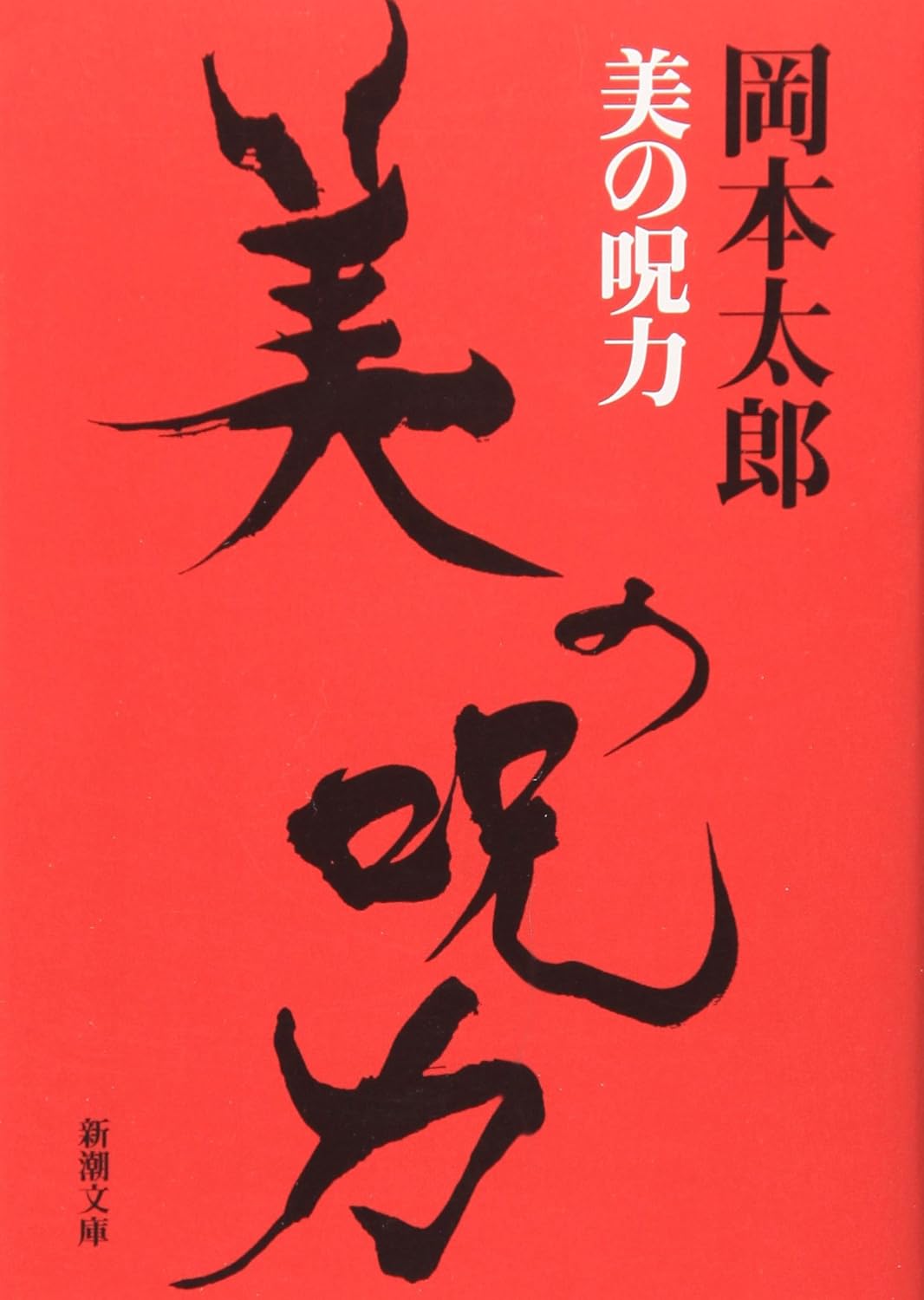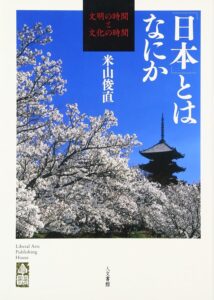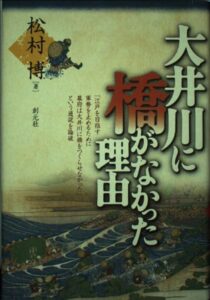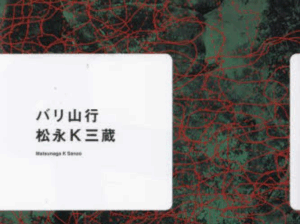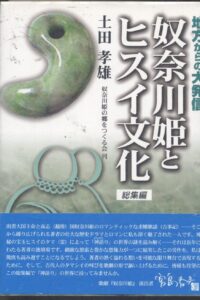■新潮文庫240607
1970年の連載中のタイトルは「わが世界美術史」。
美術史といいながら、印象派とかバロックとか分類して歴史をたどる本ではない。
最初にとりあげるのが、カナダエスキモーの積み石「イヌシュク」や霊山の石積みなどだ。
石積みが世界各地にあるのは、呪術的意味があるからだ。崩れ去るのを知りながら、ただ積む。吹けば飛ぶ、蹴飛ばされれば転がり落ちる「いのち」を表現している。近代人は、人生には目的があると信じるが、目的を見失って空虚になっている。無意識に石を積みつづける人たちの方が時間の流れや歴史の深みを体現していると太郎はみる。
グリューネヴァルトの磔のキリストは、ナマで残酷で、体からは生臭い血が流れている。キリストを「人間」としてとらえる描写は中世からの脱出だった。絶望的な「醜さ」「けがらわしさ」が極限までしめされるときに「神聖」が出現するという。
アステカでは、生け捕った敵を神に献げる人身御供があった。太陽はエネルギーの塊だが、血と生命を捧げないと死んでしまう。古代の血は超越と交流する意味があった。「真っ赤な血の塊が胸から飛び出す。死である。と同時に、いのちが強烈にふきおこる刹那だ」
忌避されたり、排除されたりする特質こそが、無限のエネルギーを創出する。穢れから聖が生じ、死から生が生じる。太郎の文章にはこうした顛倒のビジョンがあふれている。
仏教は「静」の印象が強いが、太郎は「マンダラは憤りである。あの怒りは宇宙全体に透明な波光としてひろがって行く」という。なぜ「静」や「至福」「調和」ではないのか。「存在が満足していたら、己の分量だけに安住してしまい、無限大のかなたまで神秘的な触手をのばしきるということはない」「華やぎつつひらき、宇宙をみたしている」「宇宙に透明にひろがる情熱、エネルギー」が「怒り」とする。
戦国時代の日本の兜も評価する。
人間のノーブレス(高貴さ)は、死に正対するところでしか輝かない。江戸時代の「武士道」は、形式的で、生真面目だが、武士階級が華々しく活躍した戦国時代には、しゃれっ気たっぷりの兜が生まれていた。受けて立つ覚悟のなかで「怒り」が華やぎつつひらき、宇宙をみたすという。
現代人は惰性に流されて生きている。それに「ノー」と言い、常に運命に挑むことでしか、人間の本当の生命力はひらかないと説く。
成人になるための通過儀礼(イニシエーション)は、はじめて「死」と直面し、生きる意味をつかむ意味があった。文化人類学者は、社会の側が若者を「大人」と認めるための儀式ととらえるが、太郎は逆に、若者の側が人生に対して挑む激しさをもっているとみる。
ルネサンス以降の西欧は、古代オリエントがもっていた人間を超えた神秘の存在への情熱を見失ってしまった。ゴヤの芸術は、「俗的」なゆがんだ人間関係への絶望的な怒りであり、西欧近世の矛盾が凝集されているから、ゴヤは近代芸術の源流のように位置づけられたという。
一方、太郎がすごした時代のフランスでは西欧美学が壁にぶつかり、ピカソやシュールレアリストたちが、プリミティブ・アートの表現に影響され、新しい美を生みだそうとしていた。
西欧の伝統に強烈に挑み、乗り越えた代表がピカソであり、「より透明な怒りの相が見え」「……あくまでも激しいと同時に冷たく、微妙な計算の上で炸裂している。そこに同時に遊びがある」と太郎は評価する。
ゴッホは19世紀末ヨーロッパの暗さを一身に背負って、人々に受け入れられず、狂人として死んだ。太郎はゴッホの作品は絵ではなく、「絶望的な呪文。なまなましい傷口」という。アルルでは原色が爆発したような絵を描くが、その底には、暗い世界がとじ込められている。「彼の色は自然の色ではない。強烈に自然の形をゆがめた……身のうちにある混沌を引き入れるために、そのように外界をつかんだのである」