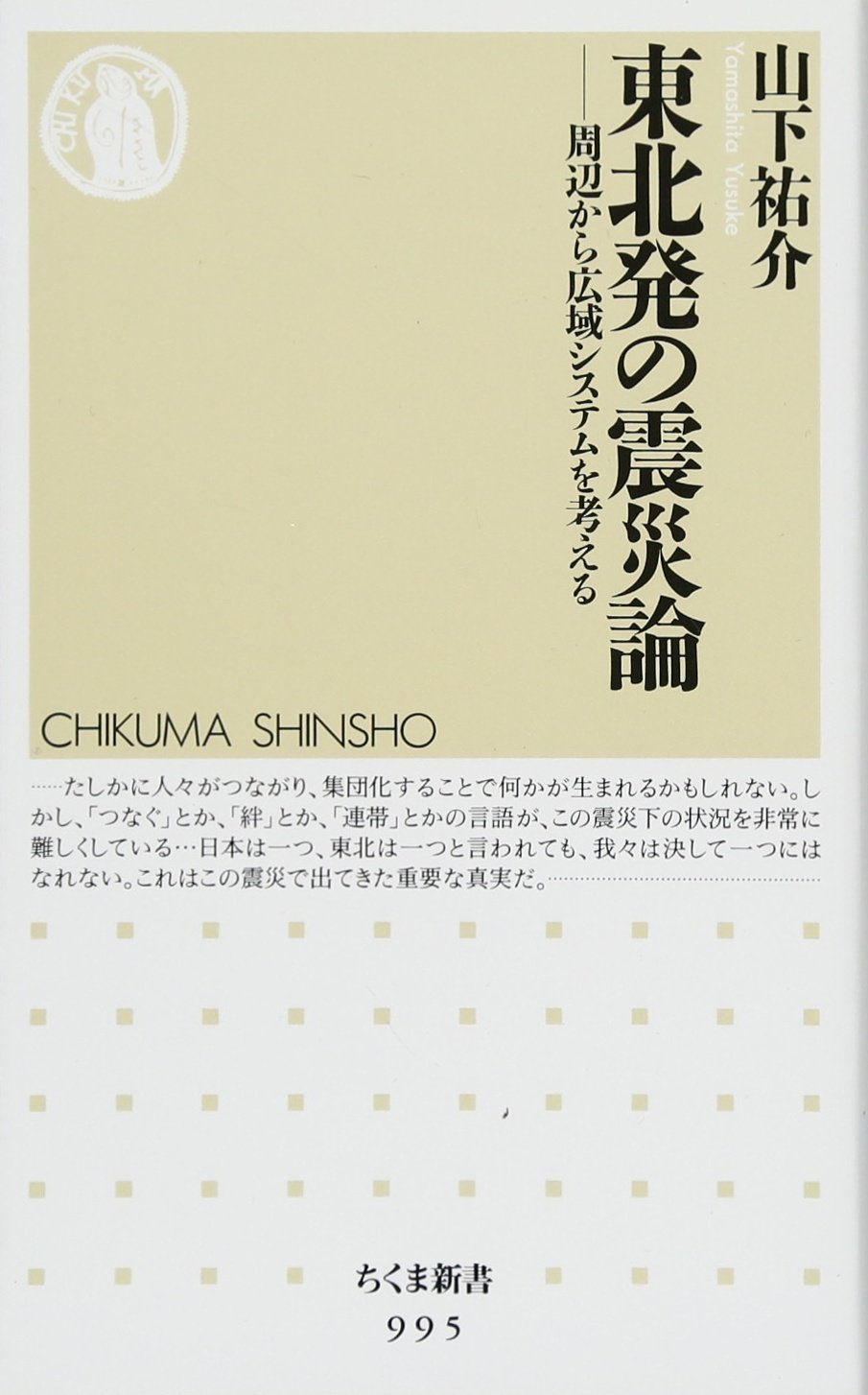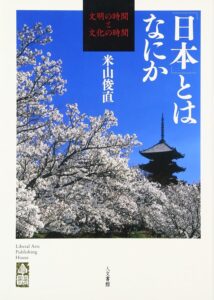■ちくま新書240625
東日本大震災から2年後の本。筆者は2011年4月まで、弘前大におり、その後東京の大学に移って、被災地を歩いてきた。
<広域システム>と<中心ー周辺>の問題こそが震災であらわになったとする。原発事故にそれが典型的にあらわれた。
自然災害では、安全確保の主体は地方自治体であり、情報はまず自治体に通報される。 原子力災害の主体は国と事業者だ。事業者→国→自治体→住民という順になる。だが実際は、最初の避難指示は、各役場にさえとどかず、事故を知ったのはテレビを通じてだった。
SPEEDIの情報が流れなかったのは、情報を吟味し知らせる主体を欠いていたからだ。情報を住民に流す決定をだれがくだすのかもあやふやだった。官邸でも当時、SPEEDIが何なのかさえわからずにいた。システムが巨大で複雑すぎて、壊れてしまうと人間の手には負えなかった。その結果、現場から遠く離れた首相が最終判断をくだすことになった。政府の不手際というより、そもそも対処不能だったのだ。
巨大発電所にたよる電力、大規模な水道網……など、広域システムに頼り切った生活のもろさが浮き彫りになったはずなのに、復興の過程ではシステムをさらに強化する方向にむいている。
各地の復興は、それぞれの事情にあうかたちで進められるべきだ。1000年に一度の津波ならば、これを最大値として、逃げたり避けたりする「減災」も選択肢なのに、「国の復興財源には限りがある。気仙沼だけ住民全員の合意を待ち、取り残されることがあってはならない」と知事があおり、「復興を急げ」という一部の「住民の声」に後押しされ、巨大防潮堤と高台移転、広大な土地のかさ上げという巨大ハード事業だけが強行され、海辺の暮らしは認められないというかたちになってきた。
暮らしの視点や周辺の視点が押しやられ、全体をみわたす射程をもたない「中心」の視点で決定されてきた。しかもその決定は、だれかが主体的に決めたのではなく、システムが動いていつの間にかそうなってしまった。経済なら経済、公的機関なら公的機関のそれぞれの中心はあるが、いざという時、そのシステムを動かす最終的は主体(中心)がなかった。
原発事故の避難者から見た解決スキームも、まず第1に、崩壊した人生設計をたてなおす生活再建、第2に地域再生、第3に心身の健康問題であるべきなのに、「賠償」と除染ですまそうとしている。
<中心ー周辺>の呪縛は、自治体間の支援の弊害にもなった。多くの市町村が、上位機関の県の調整や指示をひたすら待っていた。
若者が都市(中心)に集まり、その子や孫の世代は、もはや田舎(周辺)を知らない。周辺を理解しない人々が、周辺にとって重要な決定をくだす時代になってきた。地方への補助金は、かつては「仕送り」だったが、今は「ムダ」とされる。一票の格差問題は、バランスの悪い人口配置を元にもどす議論をすべきなのに、「都市住民が損をしている」としか見なくなってきた。
周辺(地方)から中心はよく見えるが、中心から周辺は見えない。すり鉢の真ん中と縁のような関係だ。首都圏にいる地方出身者は日本という国を実感するが、いまや大半を占める首都圏出身者は大量の情報のなかにいるのに身近な暮らししか知らない。地方を知らない人間が集まる首都ですべてが決められている。
中心にはシステムを動かす主体性はないが、中心は周辺を切り捨てることができる。東北でも、被災自治体の再編統合を叫ぶ人がでてきた。能登半島地震でも「集落再編」「漁港再編」などと都市住民が言いだしている。<中心ー周辺>関係が浮き彫りになってきた。
昭和の大合併までは、より大きなものへの小さなものの下位化(疑似親子化)であり、合併前の単位を基本的に温存し自治を維持したが、平成の合併は、効率の悪い小自治体を解消し、国のシステムを効率化(巨大システム化)することが目的とされた。合併された小地区の自治は淘汰された。
「限界集落」論も同じ流れにある。「高齢化率50%以上」という数字でムラあつかい、どうせなくなるのだから早く消えたらよいという議論が、一定の世論を構成するようになってきた。
地域レベルを見ると、1980年代まで地域の「中心」だった中心商店街が90年代に衰退した。「周辺のなかの中心」が消え、周辺は「中心」の草刈場になってしまった。
東日本大震災は、広域システムの問題をあらわにしたのだから、国家・経済大国・科学という中心的価値に対し、地方主権・暮らし・生活の知恵といった周辺的な復権こそがとえられるべきだった。国民全体で、長期・広域にわたる支援体制を確立し、時間はかかっても着実な復興が実現できるよう、見通しを示すべきだった。だが実際は、広域システムは地道な復興を阻害し、急がせ、場合によってはその基盤をも破壊するものとなってきた。能登の場合は「長期の支援体制」どころか、わずか半年で忘れられようとしている。
東日本大震災の復興への動きは阪神大震災に比べて極端に遅かった。阪神では、仮設住宅ができはじめ、緊急避難期から復旧期へと舵が切られたのが地震発生2カ月半後だった。東日本では、発災から半年2011年8月ごろようやくこの時期になった。災害の規模の差が要因のひとつとされた。だが能登半島地震は東日本よりははるかに小規模なのに、東日本大震災よりもさらに復興のペースは遅い。また東日本について「半年のあいだに被災地以外は平静へと押し戻されてしまった」と筆者はしるすが、能登半島地震はわずか2,3カ月でメディアから消えた。
発災3カ月のボランティア数は阪神は延べ約117万人。東日本の岩手・宮城・福島の災害ボランティアセンターを通じて活動した数は3カ月半で約48万3000人で「ボランティア失速」と報道された。2016年の熊本地震は、ボランティアセンターなどを通じて活動した人は約10万人だった。一方、能登半島地震では3カ月でわずか1万4453人(県集計)だ。
阪神にくらべ東日本のボランティアは「パターナリズム」の問題が出た。効率的に支援活動が進んだ反面、参加する個人や被災地周辺の小さな活動が周辺化してしまった。 田舎の生活を知らない者が多く、被災現場へ行くことをおそれるためか、活動のパターン化も見られた。
能登半島地震の石川県が管理する官製ボランティアはそれに輪をかけて、役所の下請け無賃労働者化してしまっている。
今後、首都直下地震、東海・東南海・南海の地震が予想され、これらが一体となった南海トラフ地震では最悪死者32万人と想定されている。原発事故のさらなる展開、経済メルトダウン、地方地域経済破綻の可能性といった予言は、経済再成長や夢の新エネルギーといった希望の予言よりはるかに真実味を帯びてきた。発展の時代から破局リスクの時代に足をふみこんでいる。
「主体」が見えない広域システム、<中心-周辺>の構造をこのままにしておけば破局は避けられない。広域システムの際限ない合理化に抗するには、日本社会では、「個人」ではなく、小さな共同体の意志としての主体性、社会的主体性をはぐくむ必要がある。そのためには人々がつながり、集団化しなければならない。「ムラ」の再生、ということだろう。
「東北の地は、そうした旧くて新しい社会形成のための実験場として再生しなければならない」
この結論はそのまま能登にもあてはまる。