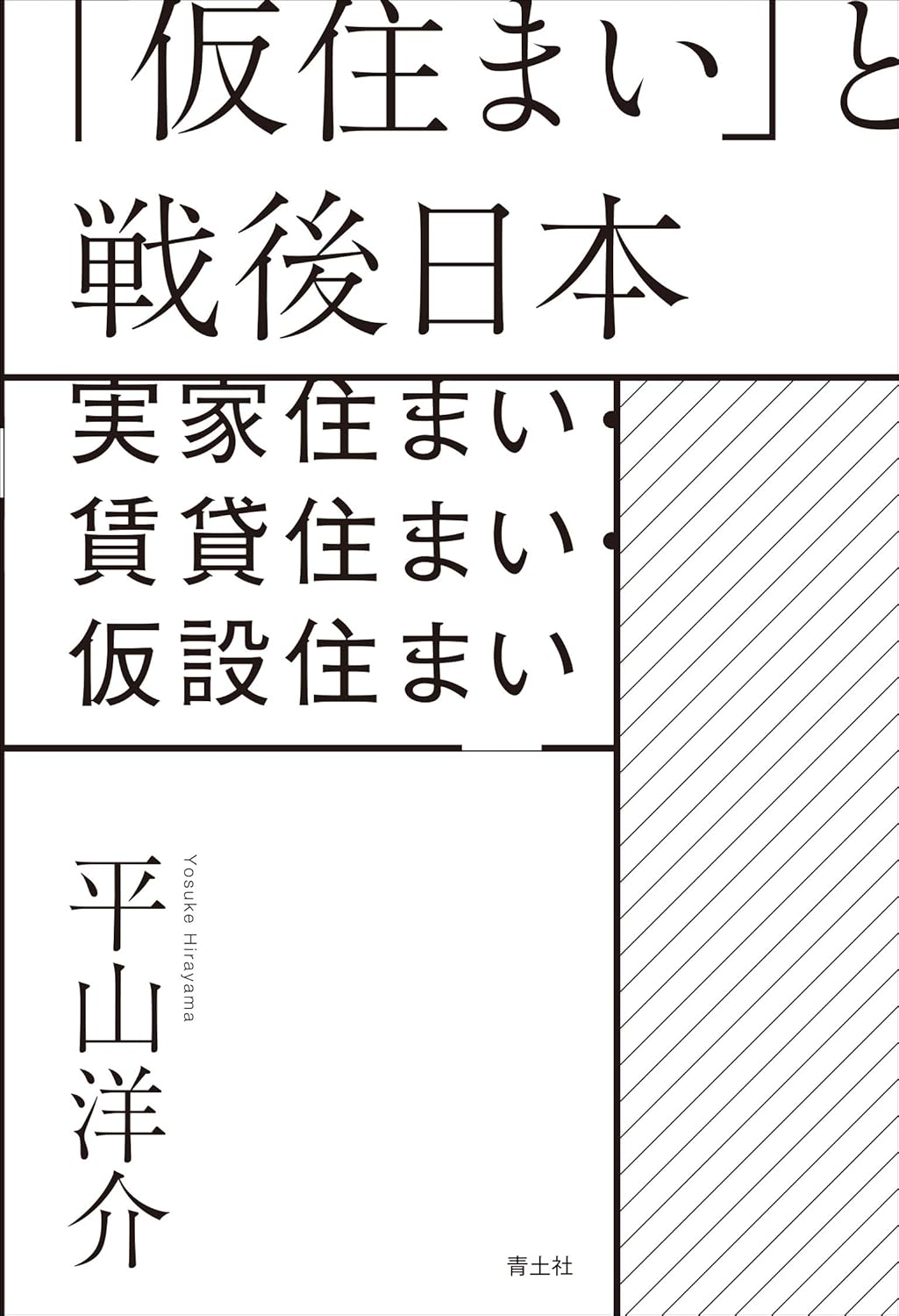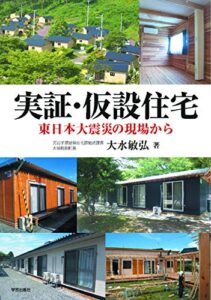■青土社
戦後日本の住宅政策は、1950年代に整備され、住宅金融公庫法(50年)、公営住宅法(51年)、日本住宅公団法(55年)を3本柱とした。だが中心を占めたのは、住宅ローン供給をになう公庫だった。
住宅ローン供給の拡大によって、高度経済成長までは「貯蓄」によって持ち家を入手したのが1970年代になると「借金」に依存する度合いが高まった。持ち家の普及は「財産所有民主社会」を安定させる意味をもっていた。
オイルショック、第2次オイルショック(1979)、プラザ合意(85)、バブル経済の破綻(90年代初頭)といった景況後退のたびに景気刺激のため住宅金融公庫の融資を拡大した。
賃貸セクターの居住条件は劣悪で政策支援が少ないから、低収入の世帯も持ち家にみちびかれた。
戦後民主社会の中心を占めたのは、マイホームを所有する「独立・自立した世帯」だった。 単身であることは家族をつくるまでの一時的な形態と考えられ、政策支援の対象にならなかった。金融公庫は、単身者に住宅ローンを供給せず、公営住宅も当初は単身入居を認めなかった。
1990年代半ばになると、新自由主義の影響で、住宅政策は大幅に縮小し、住宅ローンも市場にゆだねられ、金融公庫は07年に廃止された。
結婚と家族、雇用と所得、住まいの安定が人生のセキュリティをつくったが、社会・経済が不安定になると、雇用の安定は失われ、所得は下がり、未婚が増えた。「独立・自立した世帯」(核家族)の形成がむずかしくなり、多数の若者が「親の持ち家」に住みつづけるようになってきた。
世帯内単身者の割合は1980から2015年にかけて、25~29歳では24から40.7%に。35~39歳でも2.9から18,9%に増えた。 生涯未婚率(50歳時の未婚者の割合)は2015年は男性23.4、女性14.1%。2040年には男性は29.5、女性は18.7%になると推計されている。
戦後欧州の多くの福祉国家は、低所得層むけに社会賃貸住宅を拡大したが、日本は、公共賃貸住宅の供給を少量にとどめ、民間家主および企業の社宅に低家賃住宅を供給させた。
西欧・北欧の国々は、1960年代ごろまで社会賃貸住宅が大量にたてられた。80年代に住宅政策の市場化が進んだが、2018年の社会賃貸住宅の割合は、オランダ37.7、デンマーク21.2、オーストリア20.0%。日本は、社会賃貸セクターを構成するのは公営住宅のみで、その比率は3.6%にすぎない。ドイツは2.9%と日本より低いが、住宅手当受給世帯が7.2%を占める。日本では、公的家賃補助はほぼゼロだ。
日本は公営住宅がわずかで公的家賃補助もないなかで、新自由主義の政策改革を推進したから、住宅のほとんどが市場化し、低所得者の住宅確保はきわめて困難になった。低所得者向け住宅政策のスケールが過度に小さいことが、住宅困窮を解決できない根本原因となり、収入が少ない若者は親の家に住みつづけるしかなくなった。
成長後の時代に入った日本では、持ち家促進の政策を支えた社会・経済条件が失われたにもかかわらず、「中間層」「家族」「持ち家」支援に傾き、「低所得」「単身」「借家」層を軽視する住宅政策は変化していない。
「たまゆら」などの無届け施設で低料金かつ危険な住居を、生活困窮者の受け入れ先として、生活保護行政が利用してきた。
これらの施設は、最低居住面積水準(単身者で25平方メートル、2人以上の世帯で10平方メートル×世帯人数+10平方メートル)をまったく満たしていない。公的機関がナショナルミニマムである水準を無視している。
それについて、「多くの一般世帯が最低水準未満の住居に住んでいる状況のもとでは、被保護者のために最低水準を満たす住居を確保することはかならずしも必須ではない」という見解を厚労省はしめしている。生活保護で生活している人たちの住まいは、一般世帯より良質であってはならず、政府が定める最低水準さえ充足する必要はないとされてきた。
成長後の超高齢社会では、社会的に利用可能な住宅ストックをたくわえ、家賃補助制度をつくることで、貧困の拡大を食い止める必要があるという。
災害対応の阪神と東日本の比較と考察も興味深かった。
仮設住宅は、阪神・淡路では「プレハブ仮設」を単純にならべる団地だけだった。東日本大震災では、共用空間を備えた「プレハブ仮設」団地を建設し、さらに「みなし仮設」を供給した。
住宅対策は、阪神・淡路は被災者の9割が借家人だったから公営住宅の建設・供給が中心だった。郊外での大規模団地開発ばかりだから高齢者の集中と孤立をもたらした。東北では、大型団地だけではなく、共用空間をもつ低層公営住宅がたてられた。
持ち家の再建は、阪神ではいっさい支援がなかったが、被災者生活再建支援法が1998年に制定され、04年と07年に改正された。制定時は、全壊世帯に最大100万円の支援金給付だったが、07年の改正で、最大100万円の「基礎支援金」と最大200万円の「加算支援金」に再編された。東日本は持ち家が8割超を占めた。ローンをのこしたまま家を失ったケースへの残債を処理する方法が試され、住宅再建に対し、融資だけではなく、補助が供給された。ただ、300万円だけでは再建できない人が続出し、再建を断念する世帯が増え、公営住宅需要が拡大した。
復興構想会議は、「単なる復興ではなく、創造的復興」を提案し、400キロにおよぶ巨大防潮堤や土地のかさ上げなど、大規模な地域改造をすすめた。
こうした「土木復興」は、大量の時間を使うことから、人口と雇用の流出を招き、地域の持続をより困難にした。土地のかさあげで多くの宅地を生み出したが、工事が長期間にわたったため多くの世帯が流出し空地がめだっている。大型かつ大量の復興事業は、被災者の生活再建の条件を傷つける側面もあった。
新自由主義の市場化政策がすすむなかで、かろうじて存続していた公営住宅供給や都市再生機構、公的住宅融資などの手段が、大災害からの住宅復興を支えた。しかし公共セクターをさらに圧縮する施策がつづけば、たとえば地方公共団体は公営住宅を建てる能力を失ってしまう。日ごろから住宅困窮者に対応する住宅政策を展開することで、災害時の住宅復興にもとりくめるようになるという。