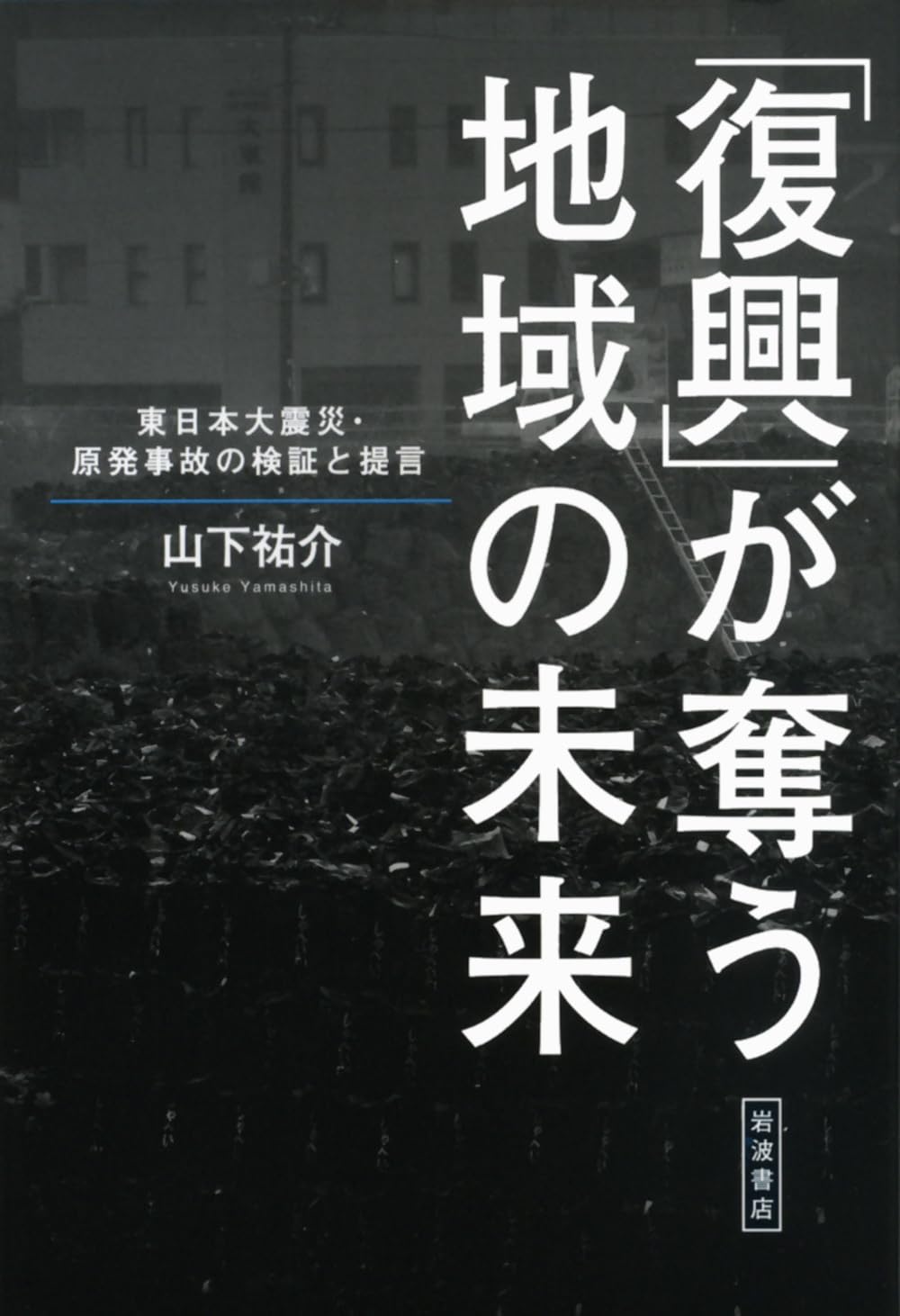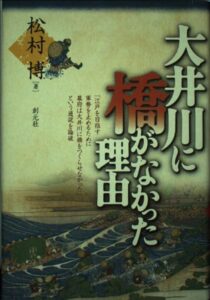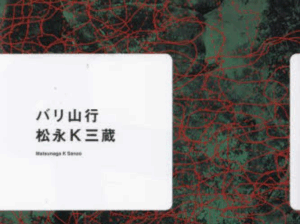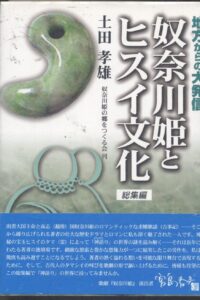■岩波書店 241225
能登半島地震の復興の問題となにかつながるところがないかと手にとった。 2017年出版した時点で東日本大震災の復興政策は失敗だったと断じている。
本質的な問題は、震災以前からつづいているという。
大店法改正にともなう郊外の乱開発と中心市街地の解体、ゴルフ場・スキー場・宿泊施設の乱立に終わったリゾート開発。市町村合併は合併特例債という奇妙なカネつきの、東京発の公共事業だった。リスクを特例債で相殺する手法によって合併をうながし、その結果、吸収・合併された地域は衰退し、「だまされた」となってしまった。
これらの実行と失敗は、自治体が主体的に選択した形をとらされた。「国が示したものだから間違いはない」という見解が先行し、失敗しても「だまされた」と口に出せず、同じような構造を再生産しつづけてきた。
プロセスが東京発で、利益が東京と地方で分配されるが、失敗の責任は地方が負う。こうした非対称の関係は、原発事故の問題構造も同じだった。
東京がもたらす計画の虚妄性、絶対大丈夫と無責任にもちかける欺瞞性こそが問われなければならない。東京からの働きかけがなければだれも原発など望むはずがなかったからだ。
中心と周辺のこうしたゆがんだ関係は、医療制度改革、年金問題、公共交通問題、教育改革など……普遍的な構造となっている。
小さな社会を解体し、大きなシステムへととりこんで中央に従属させる。その過程で生じるリスクと失敗を、一時的に巨額な利益をつかませることでひきとらせ、結果として小さな社会へ負担を押しつけてきた。
そのなかで原発立地自治体だけが唯一、十分な財源を確保し、少子高齢化を克服してきたかに見えていた。しかし一度事故がおきると壊滅させられた。
原発事故の避難者は十分に結束できず集団として抵抗できない。だから、東電のめちゃくちゃな賠償のロジックもまかり通ってしまう。また原発事故は国が加害者だ。被害者を守る立場の避難元自治体は壊滅的な打撃をうけてしまった。その結果、国や電力会社の言うがままにされてきた。
避難者たちに対して帰還か否かの二者択一を迫るのではなく、時間をかけて通い、安全をたしかめ、「通いながらの長期復興」という道筋であるべきだ。そのためには、帰還するまでのあいだの地域外自治体を制度的に補償するため、二重住民票と二重行政サービスを実現する必要がある。避難元自治体に住民票をもちつづけることで、自治体が、加害者である国や電力会社に対抗して個人を守る最後の砦となりうるという。
津波被災地では、巨大防潮堤建設が進められ、その背後には住宅建設が認められないことから、地域からの被災者の追いだしが進んでいる。
防潮堤建設と高台移転などの事業に限定されて復興過程が形成されることで、被害者の選択肢はせばめられ、被災地再生の足枷になっている。被災者は、その政策に「のる」か「のらない」かの二者択一が迫られ、支援は「のる」被害者だけのものとなっている。
本来「減災」を前提に、コミュニティ回復をまず優先して、無理のない防災を計画するべきなのに、防災を絶対視することで、コミュニティ再生を阻害して減災を担う主体そのものを破壊している。巨大防潮堤という大規模土木事業をすべての前提にしたため、復興政策を進めるほど地域社会は破壊され、人間の暮らしの復興を阻むという悪循環になってしまった。
震災直後の「復興が遅い」というパニックのなかで、被災地に急いで帰れという「復興パターナリズム」と、なにがなんでも津波から命を守れという「防災パターナリズム」が生じ、復興の方向性を規定してしまった。現実の状況に適合しない、復興を破壊するような復興政策が展開されることになった。
防災を実現しながら原地で暮らすこと、「減災」による原地復興の道を探るべきなのだ。
戦後長らくつづいた上意下達の政策形成は1990年代から、官民共同、住民参加を基本にしたものへと転換しつつあった。97年の河川法改正でも住民参加が柱のひとつだった。なのに、東日本大震災では、完全に古い体制にもどってしまった。
東日本における「市民社会が不在だった」という指摘も重い。
阪神・淡路大震災のボランティア活動は、国家と市場の失敗に対する、新しい市民社会への期待とみなされ、市民活動がもつ、既存勢力への対抗性・変革性を重視する「市民社会論的アプローチ」が盛んになされた。98年のNPO法もこの文脈からできてきた。
だが東日本では、市民社会に期待されていた政府に対する対抗性や社会の変革性はほとんど見られなかった。
体系的で効率的・効果的な支援が実現し、95年にくらべれば、はるかに大規模に活動できた。だが他方で、しばしば「人の見えないボランティア」といわれ、ボランティア活動における無力感もただよっていた。ボランティアが「助けあい」ではなく、場合によってはNPOの道具になってしまった感さえあった。
「ボランティアはこう動くものだ」との常識が積みあげられ、災害後の「速やかな救援」という機能性が重視され、95年にあった躍動感や創発力、活動参加にともなう充実感、工夫や遊びといったものが縮減してしまった。
NPOは新しい業界として2000年代には定着した。市民活動領域を広げたように見えるが、活動維持のための補助や助成が必要になるという逆転現象も生じ、大震災においても、市民活動の政府の下請け化という形が見えた。政府への批判の声があげられないという事態になってきた。
この本が指摘する「東日本」の問題点は、能登の問題を先取りしている。
「死者3万2000人の明治三陸津波と比べると、システムは私たちの命を守ってくれた。だが広域システムは、壊れた際のリスクが非常に大きく、復旧は難しい」という指摘は、土木工事によって普及させた「水道」が老朽化することで、数カ月も水のない生活を強いられることになった能登の現実を示している。広域化だけでなく、井戸をのこす「ハイブリッド」であったなら、地震後でも生活を維持できる集落は少なくなかったろう。
「国の手にも負えない事態が明らかになってきたときに……一部地域ではシステムからの切り捨てが行われるのではないか」という懸念も、能登半島地震後、「過疎の集落を復興するのは無駄」という声がSNSのみならず政府関係者からもあがるようになっている。
「みなどこかで遠慮して、声の大きい人にひっぱられて、やるべきでないことを容認し、それが失敗すると、たいていは弱者に責任を押しつけようとする」(245ページ)という指摘も2,3年後を見るように思える。
「東北社会の復興は、東北に暮らす人々自身で決めていかなければならないはずだ」とも言う。
権威主義的で住民の声を聞きたがらない役所があり、それに対抗する市民社会が脆弱なとき、「復興を暮らす人々自身が決める」ってどういう形になるのだろうか。