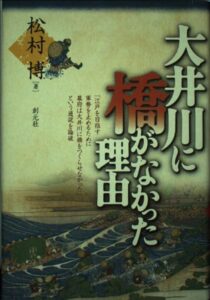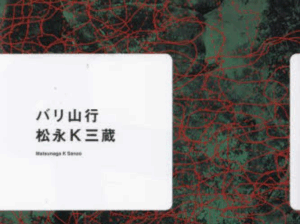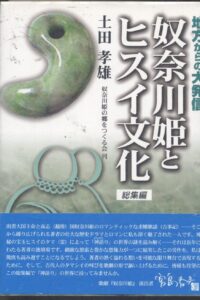■NHKテキスト250117
阪神大震災のとき、避難所や仮設住宅の住民をささえつづけた精神科医・安克昌さんはそのときの体験を「心の傷を癒やすということ」という本にまとめた。だが数年後、39歳で亡くなった。彼の名前は知っていたが具体的な活動はこの本ではじめて知った。
阪神大震災は「ボランティア元年」であるとともに「心のケア元年」と言われる。あれ以来、PTSDや心のケアに光が当てられた。だが、「心のケア」という単語が独り歩きをすることで専門家が「治療」する対象、「被災者の苦しみ=カウンセリング」という短絡的な図式が広まってしまった。
「”心の傷を癒やすということ”は、精神医学や心理学に任せてすむことではない。それは社会のあり方として、今を生きる私たち全員に問われていることなのである」「心のケアを最大限に拡張すれば、それは住民が尊重される社会を作ることになる」と安は説く。
心の傷は、専門的医療よりも、 社会での生活を豊かにすることによって、少しずつ楽なつきあい方を見つけ、癒やす必要がある。人間・コミュニティ・社会をまるごととらえ、人権が尊重されるやさしい社会や人間関係をつくることが心の傷を癒やすという。安と交流してきた筆者もおなじ視点で社会や人を見ている。だから文章がやさしくて、視野が広い。
災害直後、生き延びるために多くの人が協力しあい、ある種の共同体感情の下で身をよせあう「ハネムーン期」がある。強い不安や恐怖を感じると、そばにいる誰かに思わずしがみつく。不安なときこそ、精神的にも物理的にも、やさしさやあたたかさを肌で感じたいと思うものだ。
時間が経つにつれて、バラバラになったり分断が起きたりすることも多いが、ハネムーン期に肌で感じたやさしさや思いやりはかけがえのない思い出として残り、新たなつながりをはぐくむ土壌になり得る。
被災した町が表面上は復興しても、社会はどうせ不公平で冷たいんだという虚無感が被災地を覆っていく。それは輪島などの町を見ているとよくわかる。虚無感を癒やすのは、隣人どうしで助けあった記憶など、人との結びつきしかない。
被災者の心のケアで大切なのは「安全な環境」「安全な相手」「時間をかけること」。PTSDとして長期化することを予防するには、体験を語り感情を表現する必要がある。救援者やボランティアが一緒に作業したり散歩したりして、被災者のコトバを聞くことが<心のケア>になる。心のケアは、医師やカウンセラーだけではなく社会全体で担うものなのだ。
災害から立ち直るには、物理的に安全な場だけでなく、ある集団のなかで自分の位置が確保されている必要がある。能登の場合はそれが「集落」だった。年寄りがそこから引き離されたとき、たとえ安全なアパートであったとしても、植物が根っこからひきぬかれたように、生きる力を失い、認知症を悪化させ多くの人が亡くなった。
死別の喪失感とトラウマとは、トラウマ体験は、なるべく避けたい出来事だが、死別体験はむしろそこに引きつけられ、そのことばかりを考えてしまうというちがいがある。逆に、「なぜ私だけ生き残ったのか」というサバイバーズ・ギルトなどはよく似ている。
また死別にはかならずしも「時間薬」は有効ではない。「十分に悲しむ」作業がまず必要で、葛藤のなかで考え、感じ、話すことによって、喪失が受容されていく。「表現」を通して当事者が精神的にもがきつづけることでトラウマを癒やすのと似ている。
日本を傷ついた人が心を癒やすことのできる社会にするには、園芸療法や音楽療法、芸術療法のような要素が、日々の生活のなかに息づいていることが大事だと筆者は言う。畑をつくり、みんなで歌って踊り、手仕事でさまざまなものをこしらえる……これって、生業が息づく集落のありかたそのものだ。日本のムラは、癒やしの基盤にもなりうるんだなぁと思った。