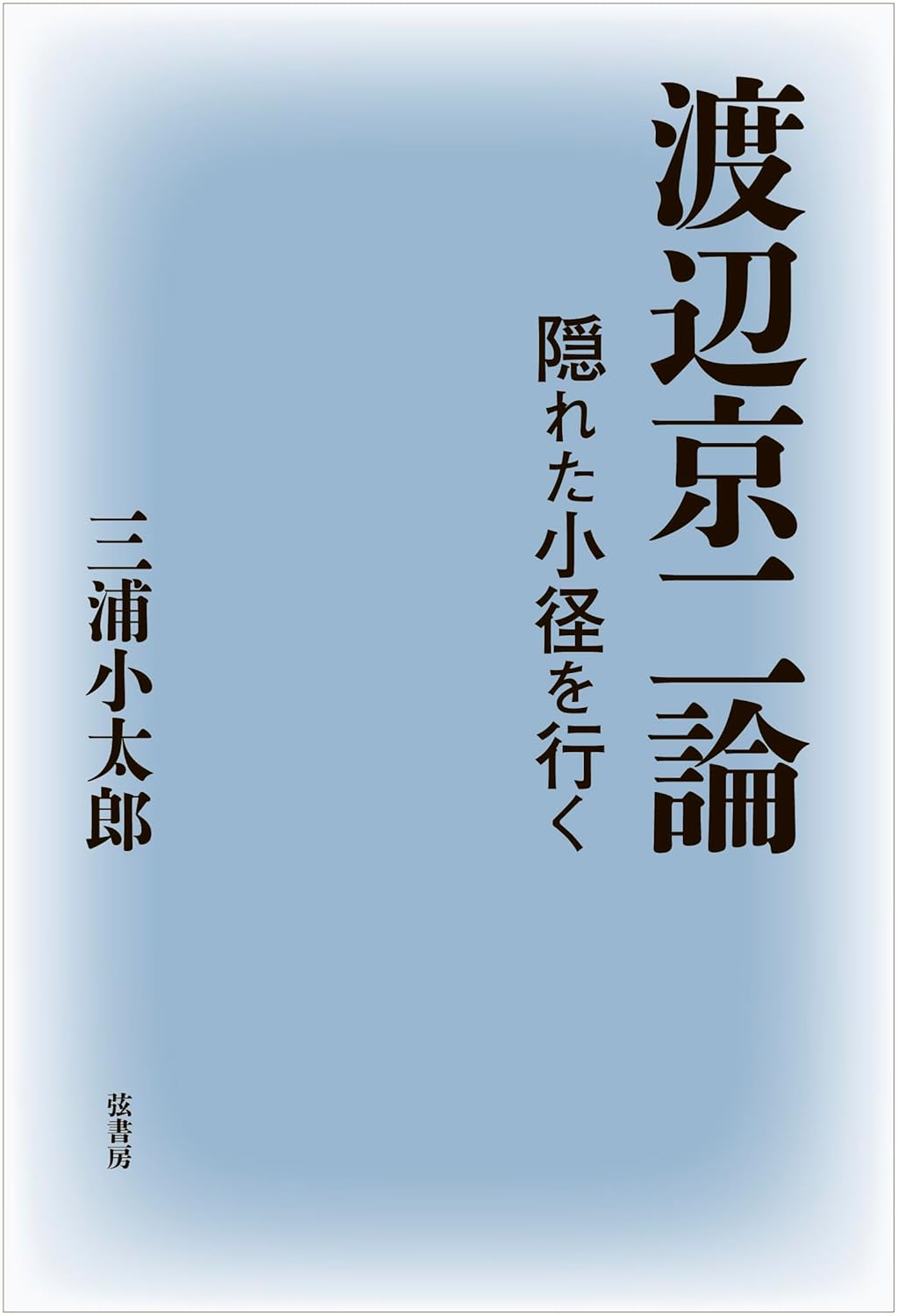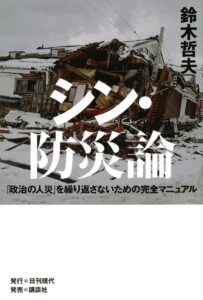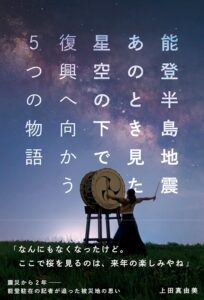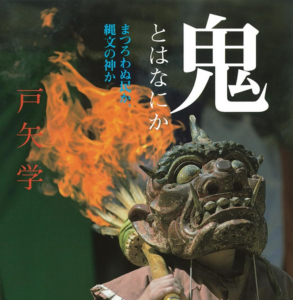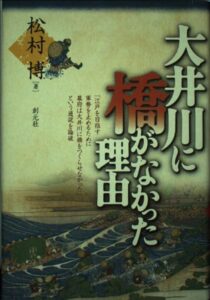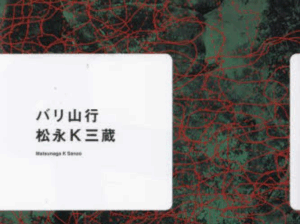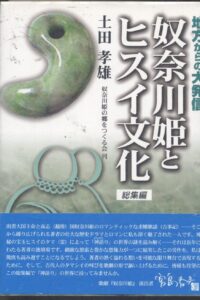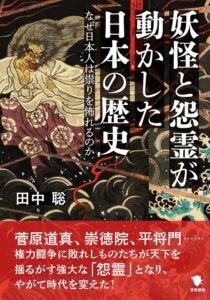■弦書房250201
渡辺京二の人物論や文学論は、渡辺自身がその人と同調して、なりかわって自分の内側から自分の思想として論じてきた。著者の三浦もまた、渡辺に直接会ったのは数えるほどしかないのに、作品を通じて渡辺になりきって内在的に渡辺の思想を読み解いていく。
渡辺は、水俣の運動をつくりあげたリベラルな人というイメージだったが、右派の三浦が描く渡辺は、どろどろした土着の世界と庶民の幻視する「もうひとつこの世」という根っこをもつ、ドストエフスキーのような人物として浮かび上がってくる。三浦の描く渡辺だけが渡辺だと思うと、ちょっと危険が気もするけど、ついついひきこまれてしまった。
日清・日露戦争においては、「世間に顔出しができぬ」という「部落共同体に対する古風な義務感」が国家への忠誠につながっていた。
1930年代、伝統社会秩序が崩壊し、大衆社会が出現した。伝統的な共同体が解体され、個々人が疎外され、「共同性への飢え」をもたらした。 中間イデオローグの右翼的言説に導かれ、疎外感からの解決を「天皇制共同体」の幻想に求めていく。「このような病的な飢渇感は、かつてこの国の伝統にはなかったもの」であり「この飢乾は天皇制共同体神話とのあいだに、おそるべき共鳴を引き起こした」
支配エリートが民衆支配の道具として天皇制イデオロギーを基層生活民に注入し、それで培養された天皇制的共同体幻想を中間イデオローグが右翼ナショナリズムのイデオロギーに変形して支配エリートを脅迫するという形になった。支配エリートや知識人は、基層民の共同性への飢餓感と、「正義」を求める声に応えることができず、支持を得られなかった。
現在、世界はふたたび、「リベラリズム」と市場優先のグローバリズムに対する「反動」的民衆の対立という図式が生じている。ポピュリズムに対してリベラル派が無力なのは、排外主義的に見える民衆の欲求に内在する民衆共同体の夢を理解しないからだと筆者は言う。
戦後、渡辺は共産党の活動家になるが、4年間をすごした結核療養所での患者=民衆との出会いによって、民衆は政治運動家の啓蒙によって「覚醒」するような存在ではないと知り、共産党の「前衛」理念のむなしさを悟った。共産党が武装闘争路線を転換し、資本主義体制のなかにスターリン主義の村社会をつくり「平和共存」する路線を選ぶとともに渡辺は離党した。
「軍国少年から共産主義者へ変身した私は、なにも変わっていなかった、…天皇制的政治理念を最高の真理と信じ……軍国少年であったように、スターリニズム的政治理念を最高の真理と信じ、歴史は共産党という前衛が指導する世界変革の方向へ進むと理解したからこそ共産主義者であった」
渡辺にとってのスターリニズムとは、超近代国家の権力が、民衆にイデオロギーを注入し、生活共同体を破壊して民衆の精神をも支配しようとするものだった。近代国民国家が前近代民衆を「国民」として統合することと本質的に変わらなかった。中国の文革を「国家をのりこえたコミューン」と考えていた毛沢東主義者に対しては「党権力によって指導される政治的反対派の追放運動を、人民そのものによるコミューン運動と見誤るほどに幼稚」と冷静に批判した。
1950年代から60年代、吉本隆明と谷川雁に出会う。とくに吉本隆明は師のような存在だった。吉本から学んだのは、「……人は育って結婚して子どもを育てて死ぬだけでよいのだ、そういう普通で平凡な存在がすべての価値の基準なのだ」ということだった。
日本読書新聞社を退職して熊本にもどると、山本周五郎の小説を読みまくり、「義理人情とは日本の伝統的な民衆の共同性への見果てぬ夢」ととらえる。
渡辺にとって水俣病闘争とは「義理人情」の地点から、チッソに代表される日本近代に挑むたたかいだった。
渡辺は、「公害問題」としての裁判闘争は利害調整行為にすぎないから興味を覚えなかった。彼が水俣病闘争にのめりこんだのは、患者たちの運動に「基層民」の自立した闘争が垣間見えたからだった。
近代社会が最後まで浸透できないもっとも基本的な民衆の心情や論理を残す人々を渡辺は「基層民」と呼んだ。基層民の「人間的道理」の次元においては資本制の常識も論理も通用しない。
石牟礼道子の描く「生きとし生けるものが照応し交感していた世界」は、近代化によって徹底的に破壊され、破滅と滅亡に向かって落下していく「小さきもの」(患者)=基層民たちの世界だった。患者たちは、現実の村共同体からも疎外されており、現実の村への回帰によっては救われない。現実には存在しない「もう一つのこの世」ににじり寄るしかなかった。
水俣病闘争はしだいに「市民運動」の枠内に撤退していく。1973年の第一次訴訟判決のころには、弁護団や市民会議と、告発する会との間には距離ができ、患者同士の対立も生じていた。渡辺にとっての水俣病闘争は裁判の「勝利」とともに終わった。
渡辺は、地方と都会の対立を思想めかして語り、「辺境」に近代資本制の重積した圧力と矛盾を見出そうとする井上光晴流の視点は根拠がないとみなした。70年代後期から80年代にかけ、日本左翼の一部は「第3世界民族解放闘争論」「辺境論」(世界の辺境にこそ革命の基盤があるとする論理)にすがりついた。私も学生時代ニカラグア革命に希望を感じていた。渡辺はそうした左翼のロマンチシズムも否定した。
ではなぜ、ドストエフスキーや北一輝らの右翼の流れを評価したのか。
19世紀ロシアでは、西欧近代の価値観と、民衆を「市民」「国民」に改造するシステムが「民衆の存在形態」を解体する危機にあった。ドストエフスキーはこの危機意識と近代への違和感を受け止めていた。19世紀のロシア民衆を見るドストエフスキーと、水俣病闘争における漁民の声をきく石牟礼や渡辺は共鳴しあっていた。
西郷隆盛は、明治維新後の近代化に抵抗し、鹿児島に帰郷後は、土地は村コミューンが所有することを唱え、「共同体農民の国家」を夢想した。彼の描いた兵農一致国家は毛沢東思想と共通するものがあった。
近代とのたたかいは、西郷が原点になり、宮崎滔天や北一輝がひきついだ。
北は、明治維新を家長国から民主国への革命とみた。民主国は「法律的公民国家(ブルジョワ市民国家段階)」をへて「法律・経済両面における完全な「経済的公民国家(社会主義社会段階)」に発展すると考えた。日本帝国は法律上において社会主義の理想を掲げているのだから、社会主義の実現は啓蒙活動や普通選挙権獲得によって可能だとみなした。だからせっかく生まれた民主国を、国体論によって家長国に引き戻そうとする思考を拒否し、教育勅語批判を通して、国家権力は個人の内面を支配してはならないという原則を打ち出した。一方、社会を個人の集合にすぎないとする市民主義も拒否した。社会は有機的な共同社会(コミューン)でなくてはならなかった。
外国人の視点から江戸時代の社会を描いた「逝きし世の面影」で渡辺は有名になった。だが「日本はよかった」「日本ばんざい」的な読まれ方をきらい、「日本人のアイデンティティなどに私は興味はない。私の関心は近代が滅ぼしたある文明の様態にあり、その個性にある」と言う。
幕府権力は年貢徴収などの国政的レベルの領域外では、民衆生活や共同体の自治には干渉しなかった。近代的な意味での自由や自治ではなく、「村や町の共同体の一員であることによって、あるいは身分や職業による社会的共同体に所属することによって得られる自由」だった。そうした前近代的共同団体の自治権は明治の革命によって断絶した。
「これほど学問なさってさえも善い人であったのに、もし学問なさらなかったら、どれほど善い人であったかなぁ」という老婆の言葉は、学問や知識などと無縁で近づきもせずに、しかも幸福に生きることが可能だったことを示す。「かわいらしい人物」に好意を抱き、世間離れした言動を愛した時代でもあった。
「いつでも死ねる」という、あっけらかんとした明るい諦観も特徴だった。
「16歳にならぬうちに花魁を買う」「出会い放題に性交する」「死ぬまで鰒を食う」という博多っ子の資格をあげ、江戸の面白さは徹底を回避して、とことんはぐらかすところに生まれたと指摘する。……こだわりを捨ててこそ「粋」なのだ。しかしその「はぐらかし」は思考の停止・放棄につながり、深みのある文学は生み出せなかった。
江戸時代の「豊かな」生と「自由」とは、共同体内の存在として自らを規定することから生まれた。近代は、個々人を疎外し、心の垣根によって人々を隔てた。だがそれは「個であることによって、感情と思考と表現を、人間の能力に許される限度まで深め拡大して飛躍させうるということだった」
近代を経験した私たちは前近代の世界にもどることはできないのだ。
日本の近代文学は、近代化がコスモスと共同体を解体するとき、そこに生まれた孤絶感を近代的な自我に即して描く道を選んだ。前近代の感性を捨て去ったため、農民・漁民世界の表層しか描けなくなった。石牟礼文学は「その孤絶感を、近代と遭遇することによってあてどない魂の流浪に旅立った前近代の民の嘆きと重ね合わせた」。それによって文字なき民のコスモスが再創造された。
石牟礼は前近代の感覚をもつ人だった。能登の出会ったおばあさんたちの海や山と交感する言葉もそうした前近代の感性の名残りなのだろう。
網野善彦らの「中世」研究を「読めば読むほど腹が立つ……」とまできらっていたことはこの本ではじめて知った。
鎌倉幕府末期から南北朝、戦国時代にいたる「乱世」を、網野らは、民衆による「自由」で「自立」した空間が「無縁」社会として存在したと評した。一方、豊臣政権から徳川幕府にいたる統一国家出現は、自由を抑圧し、自立した空間を「悪所」に封じ込める抑圧体制の完成と見た。
渡辺は、中世の「自由」が「弱肉強食の自由」であり、中世社会は、現代の「新自由主義」をさらに推し進めた、「自力救済原理」「当事者原理」に貫かれていたと指摘した。武装した農村が互いに用水や山林の権益を巡って衝突し、相手に暴力をふるっても罪とされなかった。豊臣以後の統一政権が各集団の暴力紛争を禁止し、犯罪者を処罰したことを渡辺は評価した。
網野は共同体を脱出した人々が、寺社、楽市、自由都市などで、社会的束縛から解放されて自由に生きる空間、「無縁」社会が存在したことを描き出した。
網野が「自由な空間」とみたものは、各集団の武装衝突が激発するなかで、犯罪者が復讐を恐れて逃げ込む[「縁切り寺」、「商売のために手打ちして生まれた休戦地域」としての「楽市」、大商人に寡頭支配され、ハリネズミのように武装した「自由都市」にすぎなかった……と渡辺は批判した。
そうした乱世に生まれた親鸞の浄土真宗は乱世の現実を正面から引き受け、人間には徹底して救いがないことを原点とした。「人間はどんなに努力精進しても自力では救われぬ、と絶望の果てでつぶやいた人」と親鸞のことを渡辺は評する。「絶望のないところに救済の要請があるはずはない。救われぬからこそ、救われねばならぬのである。他力とはこのこと以外を意味しない」
現実が絶望に満たされているからこそ、逆にすでに救済されている「もう一つのこの世」を親鸞は感知した。それは石牟礼が水俣病患者という絶望のかなたに、美しい自然と精霊たちが行き交う「もう一つのこの世」を見出した姿勢にも通じるという。