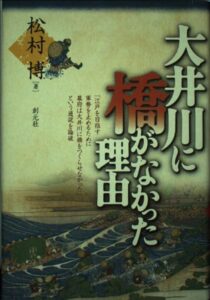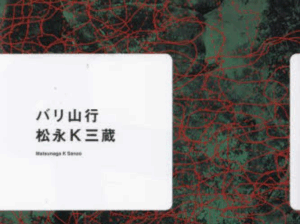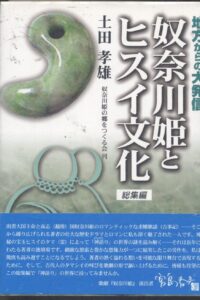■朝日新聞出版 251217
筆者は、能登に駐在する記者の募集にこたえて能登半島地震3カ月後に東京から赴任した。
新聞記事は、事実を早く端的に伝えようとするからもれてしまうものがある。「新聞記事からこぼれ落ちてしまうけれど伝えたいこと」を「with NOTO 能登の記者ノート」というデジタル版のコラムで連載した。そのうち5つの現場をさらに深く取材してこの本をまとめた。
私は発災後のメディアの報道に、ときに違和感をかんじてきた。海岸の孤立集落の取材でかちあった若い東京の記者は「孤立集落のなにがつらかったか教えてください」と取材を申し込んでいたのに15分ほどで帰ってしまった。「あわてたかんじでいくつか質問されて、すぐ終わったわぁ」と取材をうけたおじさんはキョトンとしていた。
「支援物資がとどかず食べ物がなくてひもじい思いをした……」と報じられた集落にいくと、「子どものミルクがないのはつらかったけど、おせち料理をもちよって、毎晩大ごちそうやったわぁ……」。「孤立集落の飢えについてきいてこい」とデスクに言われて、その枠にはまる事実だけを書いたのだろう。そうした違和感が、#能登のムラは死なない を書くきっかけになった。
一番悲しくつらかった元日の夜の美しい星空。亡くなった隣人を悼みながらもみんなで酒盛りをしたこと……。一見矛盾する描写や行動だけど、そこにこそ、人間の強さや不思議さがある。悲しくつらい日々、たとえば家族の看取りの時でも、プッと笑いがふきだす一瞬があるものだ。
筆者は、問題意識で切り取ったり、感情に訴えたり、「よくある悲劇」のストーリーに回収することを避け、こまかなエピソードをひろう。だから、苦しみと豊かさが、悲しみと笑いがときに共存することがよくわかる。
「伝える」ことの大切さもくりかえし強調されている。
たとえば被災直後から営業をつづけた輪島市町野町のスーパー「もとや」の男性は9月の豪雨で壊滅的被害をうけた際、「地震のとき、メディアを通じて発信することで全国から支援していただいた。だから、今回も発信しなければと思った」と情報を発信しながら復旧にとりくんだ。その結果、「地震の後も水害の後も涙が出んかったのに、いま、人にこんなに助けてもらっていることに、涙がでるの」「しんどくてやる気が出なくてどうしようという時期もあったけど、いいことだって、いっぱいあるげんて」と男性の母親はかたった。「町野町の住民全員の署名を集めてでも、なんとかもとやを支援したい」という住民がでてきた。
豪雨で31歳の姉を亡くした男性は、災害FM局の開局にあたって「(自分が)やります」と手をあげた。そのエピソードを読んで、内戦中の中米エルサルバドルで、帰国した難民たちが開局したFM局が、家族を戦争で失った人たちの心をむすぶツールになっていたのを思いだした。
伝えること、表現することは、発信する本人だけでなく周囲の人たちの「あきらめ」をふせぐ力になるのだ。
1995年に輪島で撮影した映画「幻の光」の再上映を実現させたプロデューサーは、山田太一さんの「次の世代に何かを渡していく。前の世代と次の世代の自分はつなぎ目なんだという意識」という言葉をひいて、「30年前の偶然の出会いによってできた映画は、きっとどこかで未来につながっている。その『つなぎ目』としての役割を、信じたいと思う」と言った。これは、能登で記事を書きつづける筆者の思いでもあるのだろう。
「必要としてくれることが、うれしい」といった言葉もあちこちにでてくる。
一般に、欲望の実現によって「幸せ」が得られると思われがちだけど、被災地での喜びは、人からもとめられ、人のために役立つことだった。「生きがい」「幸せ」は人とのつながりのなかにこそあることが、極限状況のなかで浮き彫りになっていた。
いま能登には上田記者と、北陸中日新聞の前口憲幸記者が、住民の思いを丹念に取材しつづけている。2人が上梓した本を読んで、外から通って取材する必要はもうないかな、と思った。
上田記者が転勤で能登をはなれたら、朝日新聞は能登の思いを報じなくなるだろうから、そのころまだ私が元気ならば、また通うことにしようか。