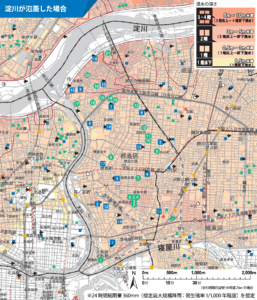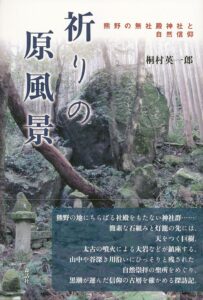■新潮文庫20230317
はじめは新聞記者の文章だなぁと思って読みはじめた。ところがしだいに石牟礼道子や渡辺京二が乗り移ったように現実と幻の境をふみこえたり、もどったりする。
正気と狂気、この世とあの世、前近代と近代、陸と海のあいだの渚。 合理主義や大量生産によって失ってしまった、多様性が息づく「あわい」を生きてきた人として石牟礼道子をえがく。
「浜辺に立ちますと、目に見えるものもですが、目に見えないものたちの気配もいっぱい充ちています。それらが混ざり合って浜辺は『生命たちの揺籃』というか、生まれたものもですが、まだ生まれない「未生のものたちの世界」でもあるように思います」
この語りは道子をもっともよくあらわしている。
「苦界浄土 わが水俣病」は、水俣病の悲惨を描くとともに、つつましく義理堅い庶民の感覚を丹念に拾うことで、人と自然が調和していた前近代的世界に光をあて、それを破壊した近代工業社会の残酷さを浮き彫りにする「私小説」だった。
石牟礼たちの水俣病のたたかいは、チッソを自分たちの目の前に立たせ、「近代」の罪をあらわにすることをめざした。だから道子は近代を前提とする「市民」という言葉を嫌った。そのかわり、患者も支援者も「死民」を名のった。おどろおどろしい「死」という文字に、ぼくは1980年代に水俣にかよっていたころ違和感をおぼえた。「公害」のはるか先を道子らが見通していたことを理解できていなかった。
道子らにとって法廷は敵を目の前に引きずりだすための手段にすぎなかった。加害者と被害者が相対で魂のぶつかりあいをしたかったが、司法制度はそれを許さず、金銭の交渉ごとに終わってしまった。
緒方正人は、相手のチッソや行政に人間の顔がなく、すべてがカネに換算されることに疑問をかんじ、「患者ち言われとうなか。チッソは俺じゃったかもしれんし」と語り、「苦海(苦界)の受難の記憶」をとりもどしたいと願った。杉本栄子は「人間の罪、それは患者である私が引き受けた」「憎んでばかりおれば、敵討ちせんならんと思っておれば、きつか。許すことにした。憎めば、きつか。チッソも許すことにした。私たち一家を汚なかもののように差別した人たちも許す」と言った。
道子の生き方をたどることで、裁判の勝ち負けと次元が異なる水俣病の本質が見えてくる。
道子は幼いときから「生きにくさ」をかかえ、何度も自殺をこころみた。人生はつらいもの、と思い定め、「もうひとつのこの世」をもとめてきた。
でも人の苦しみは見ておられない。水俣病患者によりそい、チッソ本社前数人で座りこんだ。勝算などない。患者の積年の怨恨をしめす浪花節的行動だった。いつしか「水俣病闘争のジャンヌ・ダルク」と呼ばれた。
道子の祖父の吉田松太郎は石工で、天草から水俣にやってきた。新興の実業家で、だれでも迎えいれる自由な家だったが、道子が幼いときに破綻する。道子は、田舎から売られてきた「女郎」たちにかわいがられ、精神を病む祖母の「おもかさま」とすごした。
父の亀太郎が死んだとき、母のハルノは、夫や自分や子どもの生年月日も知らなかった。近代的な「数字」「制度」とは無縁の、万物と交歓する前近代のヒトだった。
旧家の石牟礼家への嫁入り後は、畑仕事がない雨の日に図書館にかよい、高群逸枝の著作に出会う。東京・世田谷にあった逸枝の自宅兼研究所に5カ月間滞在して逸枝の評伝を書いた。
道子は、旧家の次男の嫁の立場から離陸し、水俣病闘争と作家活動に没頭し、夫の住む水俣を離れて熊本市に転居する。息子の道生は「母は父の求める妻としては早くにその役目を自ら放棄していました。……静かで優しい父は黙認しました」とふりかえる。
道子51歳ぐらいからは渡辺京二が、原稿の清書や資料整理だけでなく食事もつくってささえた。
夫の弘が2015年に亡くなるとき、「普通の嫁になれなくて、ごめんね」「あなたと結婚して本当によかった」と言い、意識が混濁しはじめた夫は「うーん」とうなって道子の手を強く握ったという。
原田正純は2012年に急性骨髄性白血病で死去する直前、妻とともに道子を訪れた。「……つくづく庭をながめて、バラの花というのは、こんなにきれいだったのかななんて言いましてね。……ああやっぱりこの世の時間がなくなってきたんだなと私も思うんですよ」と原田の妻は語り、今が幸福だ幸福だと夫妻はくりかえした。その様子を「聖なる時間に私もおらせていただいているような気がした」と道子は表現した。
人の心の琴線をかんじとる感性に圧倒される。たぶんこの感性は彼女の「生きにくさ」から生じるのだろう。だとしたら、「生きにくさ」をかんじながら生きることもそれほど悪くない。
学生時代の自分になにがたりなかったのかもこの本をとおして見えてきた。
水俣とかかわって心が動かされたのは、患者さんの子どものころの話や、ごちそうになった魚や貝のおいしさだった。でも当時はそれらを「勝訴」をめざす裁判闘争の「おまけ」ぐらいに考えていた。
「生きているうちに救済を」というスローガンは、「救済」が患者さんの言葉と思えないなあとはかんじていたが、深くは考えなかった。自分の心を動かしてくれたものを「主」と考えていたら、もっと豊かなものが見えてきたのになあ、と今になって思う。