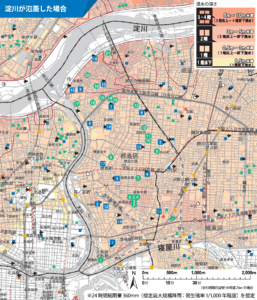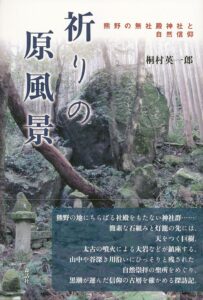■(日本農業新聞)
農協の中枢にいて政治とも密接なつながりもっていた一楽照雄がなぜ、政治的には革新に近い、ある意味で農協と敵対する有機農業研究会をたちあげたのか、以前から不思議だった。
この連載は、戦前から「協同組合主義」を体現し、協同組合としての農協を育てようと志しながら挫折し、有機農業に軸足をうつしていく過程がえがかれている。日本の農業や社会はいまようやく一楽の思想に近づきつつあるようだ。
以下はあらすじ。
東大を卒業した一楽は「産業組合中央金庫」の協同組合の思想に共鳴して就職するが、戦時体制下、協同組合としての性格を捨てて国家協力団体になってしまう。
戦争遂行のために農業団体を統合した農業会は戦後解体され、農業協同組合が設立される。協同組合運動意識の強い役職員は戦争中に組織を抜けていたため、協同組合の理念は戦後の農協に十分に伝わらなかった。
農協は、営農改善や流通過程の合理化といった経済面だけでなく、組合員の生活面にもとりくむべきだと一楽はかんがえ、1961年の第9回全国農協大会で「生活改善活動の積極化」を決議した。
「農業は学者から『経済学の対象外だ』と放り出してもらったほうがいい」と言い、資本主義の論理にまきこまれてはならないと考えた。だから農業基本法のかかげる「選択的拡大」「農業の近代化」も反対だった。農協が信用事業に依存することも批判した。
徹底した協同組合主義者である一楽は、農民にもっとも近い単位農協が「主」であり、上部団体の県や全国レベルを「支店」「支所」と位置づけた。単位農協は、農家の暮らしのすべてを背負うが、県や全国組織は生活からはなれ、「カネ」にしかかかわらないからだ。
農協は「火の見櫓が見える範囲」の規模が望ましいとし、「家庭の結集体である生活圏に基礎を置いた協同組合であってこそはじめて民主的な組織になりうる」とした。電話も自動車もない時代、「旧村規模」が適正と考えたのだ。
ところが1950年代なかばの市町村の大合併とともに行政主導で農協も合併をもとめられる。「機械的な拡大は農協と組合員の結びつきを弱め、農協を弱体化する」と一楽は説いたが、大量生産・大量流通に対応するため、合併の流れはとまらなかった。
「手入れのよい農地に囲まれ、住宅団地が形成され、団地住民と農民の間に密接な交流が行われる地域社会」である「農住都市建設構想」も構想した。1979年には「協同組合図書資料センター」を開設し、過去の知恵からまなぶことを重視した。
だが農協は、一楽の思想と正反対の方向にむかう。大規模合併をくりかえし、信用事業や化学肥料・農薬の販売でもうけ、本来の主人公である農民を利益の対象ととらえるようになっていく。「農住都市」は頓挫し、「資料センター」は2011年に解体された。
1970年には一楽は農薬被害に注目し、自然農法の福岡正信さんや農薬被害をあばいた梁瀬義亮医師らを「経営研究所」のセミナーで講師に呼ぶ。1971年に日本有機農業研究会を旗揚げした。