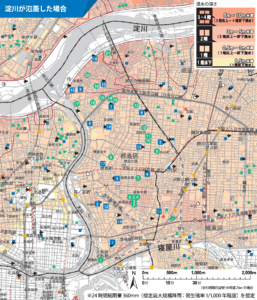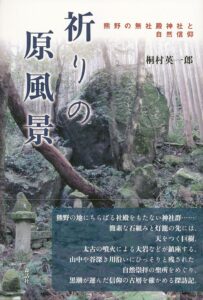■平凡社新書20230320
シャーマンのような石牟礼と、娘世代の詩人伊藤の「死」をめぐる対談。
いつも「死」の隣にいて、死のうとする人によりそい、自らも自殺未遂をくりかえした石牟礼だからこそ、伊藤の「死」についての直球の疑問に真正面からこたえる。
石牟礼は生涯、生きにくさをかんじて鬱状態だというが、ひょうひょうとして、「それまでの耐えがたい苦しみが消える……最後の、とっておきの最大のたのしみ。終りの刻が、必ず来ると思えば、何という救いであろうか」「現世はどっちみち苦しい。誰でも苦しい。だからせめて、後生を願いに行く」と死を心待ちにする。現世を苦ととらえると、重いはずの死が軽くかんじられる。
鶴見和子が2006年に死ぬ直前に弟の俊輔にのこした「死ぬというのは面白い体験ね。こんなの初めてだワ。こんな経験するとは思わなかった。人生って面白いことが一杯あるのね。こんなに長く生きてもまだ知らないことがあるなんて面白い!! 驚いた!!」という言葉もすばらしい。
人が死ぬと、身内が風呂にいれて、一人ひとりどこかを洗って(湯灌)、「良か所に行きませな」と言って拭いてあげた。そうやって石牟礼は父母を送った。それが近代以前の「死」の形だった。
「いつお腹を減らした若い人が来るかもわからん、足らん足らんで炊くな。4、5人分くらいは多く炊け」と石牟礼の母は、いつも来客にそなえていた。
乞食のような人を「勧進どん」と呼び、「弘法大師様の生まれ変わりであんなさるかもしれない」「粗末にするとちゃんと見ていなさる」「(米などを)差し上げる役目は子供でなくちゃいかん。大人が出ていくと、乞食さんが気兼ねをなさる」と大切にした。
ぼくの熊本の祖母も見知らぬ旅人(巡礼や物乞い)にふるまい、「客が来てくれないような家にしていかんばい」と言い、毎朝仏壇の前で法華経と祖先の名をとなえていた。それが近代以前からつたわる倫理だったのだろう。
そういう倫理も、故人を家で見送る習慣も消えてしまった。ぼくの祖母の最期は病院だった。
近所の若い女郎が殺されたとき、みんなが「南無阿弥陀仏」ととなえたという。「かなしいね」「かわいそうに」ではぴったりこない。南無阿弥陀仏にかわる言葉は意外に見つからない。簡単な経文が「救い」をもたらしてくれる。それもまた前近代の知恵なのだろう。
石牟礼はアニミズムを体現している。
「アニミズムの根本は生命ですね。……風土に満ち満ちている生命、カニの子供のようなのから、微生物のようなものから、潮が引いていくと遠浅の海岸に立てば、もうそういう小さな者たちの声が、ミシミシミシミシ遍満している気配がするでしょう」
後白河方法が編纂した「梁塵秘抄」や「日本霊異記」、世阿弥の「風姿花伝」などの話も興味深かった。