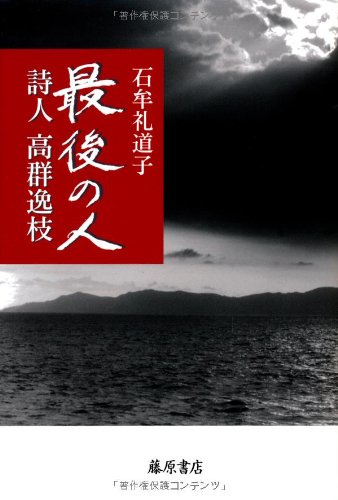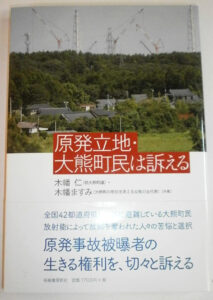■藤原書店202303
高群逸枝と石牟礼道子は出会ってはいない。でも石牟礼は高群を母か姉のように思い、逸枝とその夫の橋本憲三は石牟礼のことを後継者のようにかんじていた。
逸枝が亡くなった2年後の1966年、道子は逸枝と憲三の住まいだった東京・世田谷の「森の家」に数カ月滞在する。
「先生」と呼ぶ憲三とくらす日々の描写からはじまる。
理解できない表現が多い。途方に暮れながら読み進めると少しずつ、道子の心の森にわけいっていくような錯覚をおぼえる。道子は「森の家」で憲三と交流することで、逸枝の心と同化していくのだ。
この本は最初から順番にすべてを読む必要はない。わからないところは飛ばせばよい。ところどころ、道子=逸枝=憲三の宇宙につながる穴があいている。「評伝」ではなく、3人の宇宙につながるバイブルか経典のようだ。
高群逸枝と橋本憲三は熊本に生まれる。逸枝は、観音様の生まれ変わりと呼ばれ、みずからもそうかんじていた。24歳で遍路をした「娘巡礼記」はみずみずしく若々しい感性があふれている。女性としても魅力的だったらしい。婚約者の憲三とほかの男性との三角関係に悩んだ末の巡礼だった。
教師をやめて26歳で上京すると、憲三もそれを追って東京にでて、平凡社の創業にかかわる。当時の左翼の文化運動などにもかかわり、2人の家はたまり場になっていた。それがいやで逸枝は家出をするのだけど、その時に憲三にあてた手紙は、「あなたをとても好きです」というラブレターだった。それを見て憲三は飲み友だちをつれてくるのをやめ、平凡社をやめ、逸枝のための専属編集者になった。
そして、鹿鳴館の材料を活用したという「森の家」を入手し、「面会お断り」の看板を掲示する。家事を担い、逸枝の研究生活をささえることに献身する。
逸枝は、日本の婚姻は「嫁入婚」ではなく招婿婚だったことをあきらかにする。だから嫁姑の問題などはなく、女性が死んだとき、夫の実家ではなく自分の実家の墓にはいった。皇后は、女御や内侍として入内し、事後的に選ばれて立后するが、死ねば氏族の墓地に葬られた。天皇家に厳格な意味で嫁取婚が発生したのは明治以後だという。
政治的にリベラルな男でも家ではいばることは多く、「共産党、家に帰れば天皇制」といわれるが、逸枝と憲三の関係は日本的な「家制度」とは正反対だった。
「男の一生を棒に振って女房につくした」と言われても憲三は気にしない。それどころか「日本の家庭の爆破にいささか協力しただけですよ」という。
憲三は心から逸枝を愛し支えていた。こんな人はもう二度とあらわれない。石牟礼はそう確信して「最後の人」というタイトルをつけた。
1964年、逸枝は重い病で入院する。ある夜、「われわれはほんとうに幸せでしたね」「手をにぎってください」。そう言ってわかれた夜に亡くなった。
「私がいかにあなたを好きだったか、いつでもあなたが出てくると、私は何もかもすべてを打っちゃって、すっ飛んでいった。『火の国』はあなたにあとを委せてよいと思う。もう筋道はできているのだし、あなたは私の何もかもをよく知っているのだから、しまいまで書いておいてください。ほんとうに私たちは一体になりました」
そう言い残した逸枝のために、憲三は「火の国の女の日記」にとりかかる。泣きながら浄書するあいだは、さびしさをまぎらすことができた。
「世にもすばらしい女性でした。70歳になって病気になるまで、彼女の魂も女体も少女のようにつつましくきよらかで、完璧でした。…僕でなくても他の男性であっても、彼女は相手にそのような至福をあたえずにはやまないものを無限に持っていた女性でした」
主がいなくなった「森の家」で憲三は、「火の国の女の日記」をしあげ、「高群逸枝全集」を編纂する。それが完成して「森の家」を手放すことになった。膨大な本を古書店に売り、逸枝のマンドリンを焼く。跡地は児童公園になった。その最後の日々を石牟礼はともにすごした。1966年末、憲三は水俣にもどった。
逸枝よりも憲三の思いを描いているのだけど、その後ろにシャーマンのような逸枝の存在をかんじられる。それは道子自身の姿でもある。道子は逸枝であり、逸枝は道子なのだ。